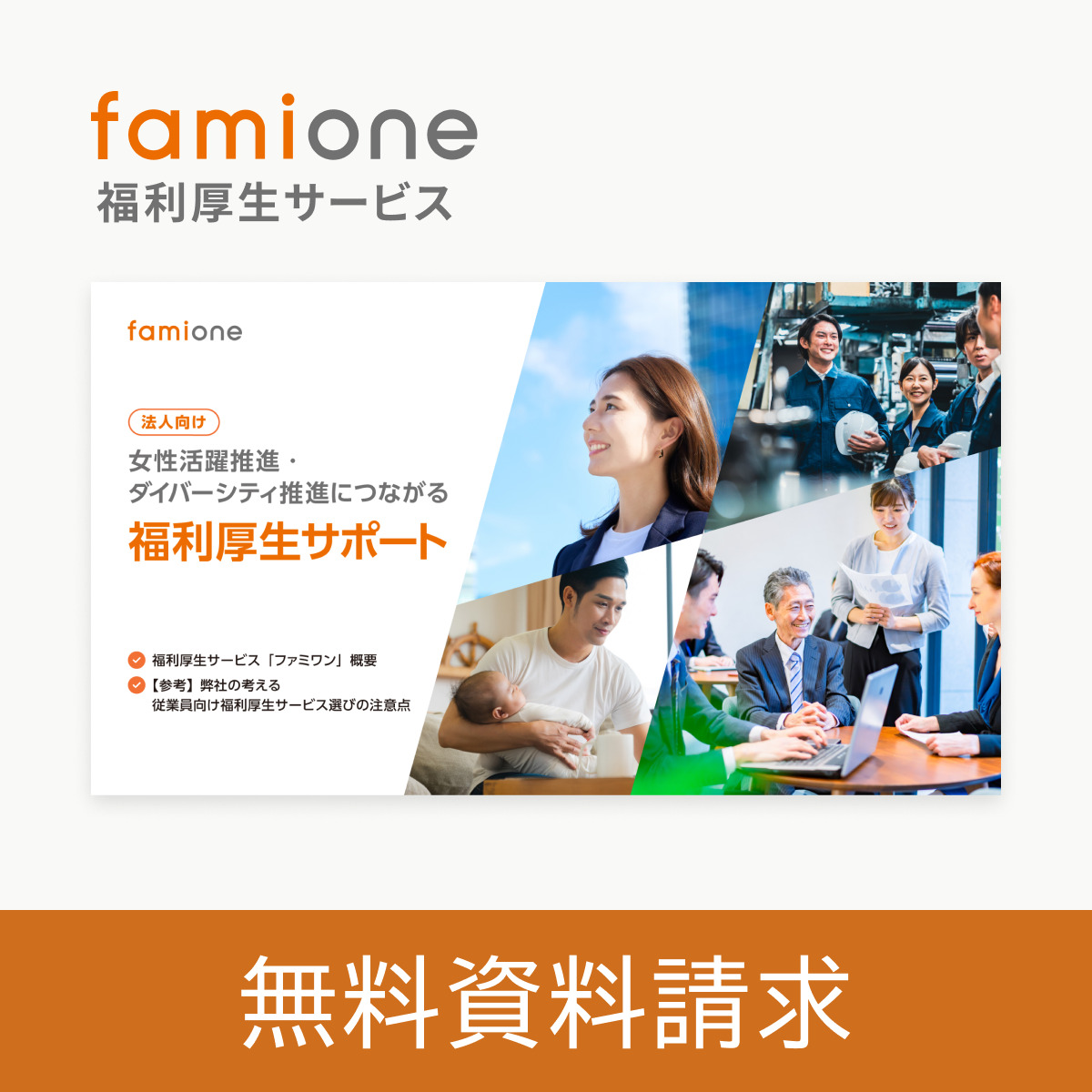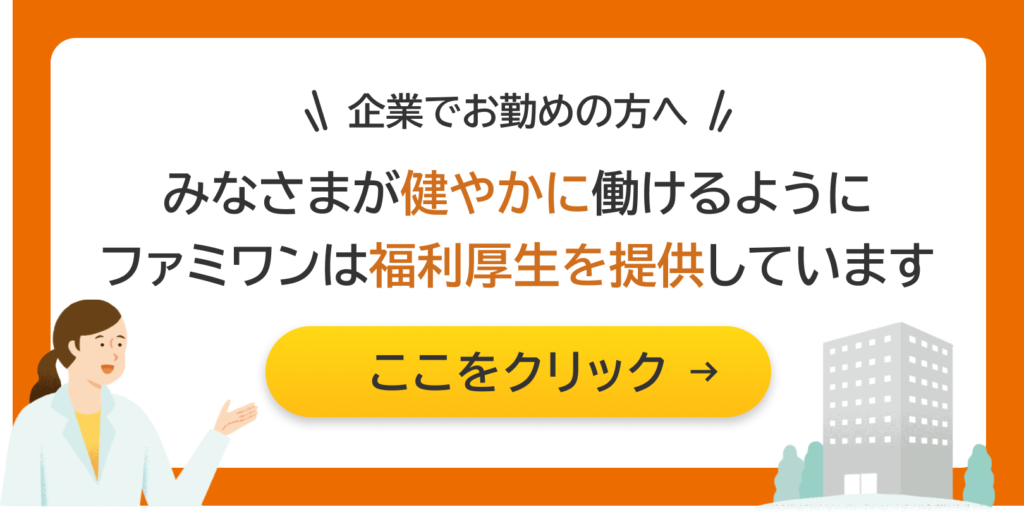子育てをしていると「熱性けいれん」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
今回は、「熱性けいれんとはなにか?」「どんなときに起こるのか?」「どう対処すればいいのか?」と気になる方に向けて概要をまとめていきます。事前に知っておくことで、万が一のときにも落ち着いて対応できる力になりますよ。
熱性けいれんとは?
熱性けいれんとは、「38度以上の発熱に伴って起こるけいれん」です。主に生後6か月〜5歳ごろの乳幼児に見られ、体温の急な上昇などをきっかけに脳が一時的に過敏になってけいれんを引き起こすと考えられています。10人に1人は熱性けいれんを経験すると言われているので決して珍しいものではありません。
発熱によって一時的に起こるものであるため、多くの場合は時間の経過とともに自然におさまります。初回の発症は1歳〜2歳ごろが多いとされています。
どんな症状が見られるの?
熱性けいれんの症状は、次のようなものが一般的です。
・38℃以上の発熱に続いて突然けいれんが起こる
・白目をむいたり、手足がピクピクと震えたり、突っ張るような動きをする
・呼びかけに反応せず、意識がないような状態になる
・けいれんは数秒〜5分以内で自然におさまることがほとんど
初めて見たときは「息が止まってしまうのではないか」「命に関わるのではないか」と不安に思うと思いますが、ほとんどの場合は命に関わることはなく、後遺症が残ることもありません。
熱性けいれんには2つのタイプに分けられる
単純型
・全身のふるえ(全般発作)が15分未満で自然におさまる
・意識は一時的に失う
・熱性けいれんの90%以上がこのタイプ
・通常、24時間以内に2回以上は起こらない
複雑型
・発作が15分以上続く
・体の片側だけがふるえる
・24時間以内に2回以上の発作がある
・ごく一部に、将来てんかんなどのけいれん性疾患を発症するリスクがわずかにあります
熱性けいれんの原因は?
風邪や突発性発疹、インフルエンザなどで高熱となる場合にけいれんが起こることが多いとされています。家族の中に熱性けいれんを起こしたことがあると、可能性が高まります。
てんかんとの違いは?
熱性けいれんは「一時的な発熱による現象」で、ほとんどが成長とともに自然に治ります。一方で、てんかんは「慢性的な神経疾患」で、繰り返す発作に対する継続的な治療と観察が必要です。
けいれんが起きたときの正しい対処法
けいれんを起こしたとき、どのように行動すればよいのかを紹介していきます。
やるべきこと
①慌てないようにする。
命に関わることは少ないので、まずは落ち着く。
②安全を確保する
平らな場所に寝かせ、頭を打たないように注意する
③けいれんの観察
・衣類をゆるめ、呼吸がしやすいようにする
・けいれんの時間を測る(発作が何分続いたかを確認)
・手足の動きや目の向き、顔色の観察
・吐きそうな様子があれば、顔を横向きにする
記録をとるのは難しいかもしれないので、医師に見せるために動画に残しておいてもいいでしょう。
④けいれんがおさまったら
呼びかけに反応するかを確認。体温も計測する。
やってはいけないこと
・強く体をゆすったり、抑えつけたりする
・呼吸を促そうとして口にものを入れる(窒息の危険があります)
・大声で呼びかけるなど、過度な刺激を与える
けいれんが起きている間は、何かをするより「見守る」ことが一番の対応です。親として「何もできない」ことが不安になるかもしれませんが、無理に止めようとするよりも安全を確保し、様子を観察することが大切です。
受診が必要なケースとは?
熱性けいれんの多くは自然におさまり、大きな問題を起こすことはありませんが、以下のような場合には、速やかに医療機関を受診しましょう。
・けいれんが5分以上続く
・顔色が悪く、呼吸が止まりそうになっている
・発作後も意識がはっきり戻らず、ぐったりしている
・同じ日に複数回けいれんが起こる
・けいれんに左右差がある、または熱がないのにけいれんを起こした
これらは「複雑型熱性けいれん」と呼ばれ、脳波検査やMRIなどの精査が必要となる場合があります。救急車を呼ぶか迷う場合でも、初めてのけいれんの場合は、速やかに病院へ向かいましょう。
再発はするの?
熱性けいれんは、初回発作後の30〜40%で再発するとされています。特に、1歳未満で発症した場合や、家族にけいれんの既往がある場合は再発率がやや高くなります。
ただし、何度もけいれんを起こすからといって、それが「てんかん」になるというわけではありません。熱性けいれんの多くは成長とともに自然に消失していきます。5〜6歳を過ぎるころには再発のリスクもほとんどなくなるため、過度に心配しすぎる必要はありません。
医師の判断により「ダイアップ坐薬」などの予防薬を処方されることもありますが、使用の有無や頻度はお子さんの状態に応じて異なります。自己判断での使用は避け、医療機関でよく相談しておきましょう。
保育園や幼稚園での対応は?
自宅で熱性けいれんを起こした際は、必ず園にも報告しましょう。
予防薬の預かりに関しては園の方針によって異なるため、事前に確認が必要です。
発熱した場合は早めのお迎えを依頼されることも多いため、保護者としても心構えをしておきましょう。
けいれんと似ている「泣き入りひきつけ」
乳幼児が激しく泣いたあとに、呼吸が止まり意識を消失することを「泣き入りひきつけ(息止め発作/憤怒けいれん)」といいます。乳幼児の5%に見られ、6ヶ月〜2歳でよく見られます。ほとんどは数秒〜数十秒で意識回復し、後遺症も残さない予後良好な疾患です。
6ヶ月以下や2歳以上で初めて起こしたときや1分以上意識が戻らないときは速やかに受診しましょう。
まとめ
子どもが突然けいれんする姿を見るのは、親にとってはとても怖く不安な経験です。ただ、「熱性けいれん」という症状について知識をもっていれば、慌てることなく、落ち着いた対応ができますよ。
医療機関に相談することをためらう必要はないので、初めてのけいれんで不安なときはすぐに受診しましょう。
参考文献
①”熱性けいれん”.MSDマニュアル家庭版.2023/3.https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/23-%E5%B0%8F%E5%85%90%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E5%B0%8F%E5%85%90%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%96%BE%E6%82%A3/%E7%86%B1%E6%80%A7%E3%81%91%E3%81%84%E3%82%8C%E3%82%93 .(2025/5/15)
②病気がみえるvol15.小児科.株式会社メディックメディア.2022
③ママ%パパにつたえたい子どもの病気ホームケアガイド第5版.医師薬出版株式会社.2020