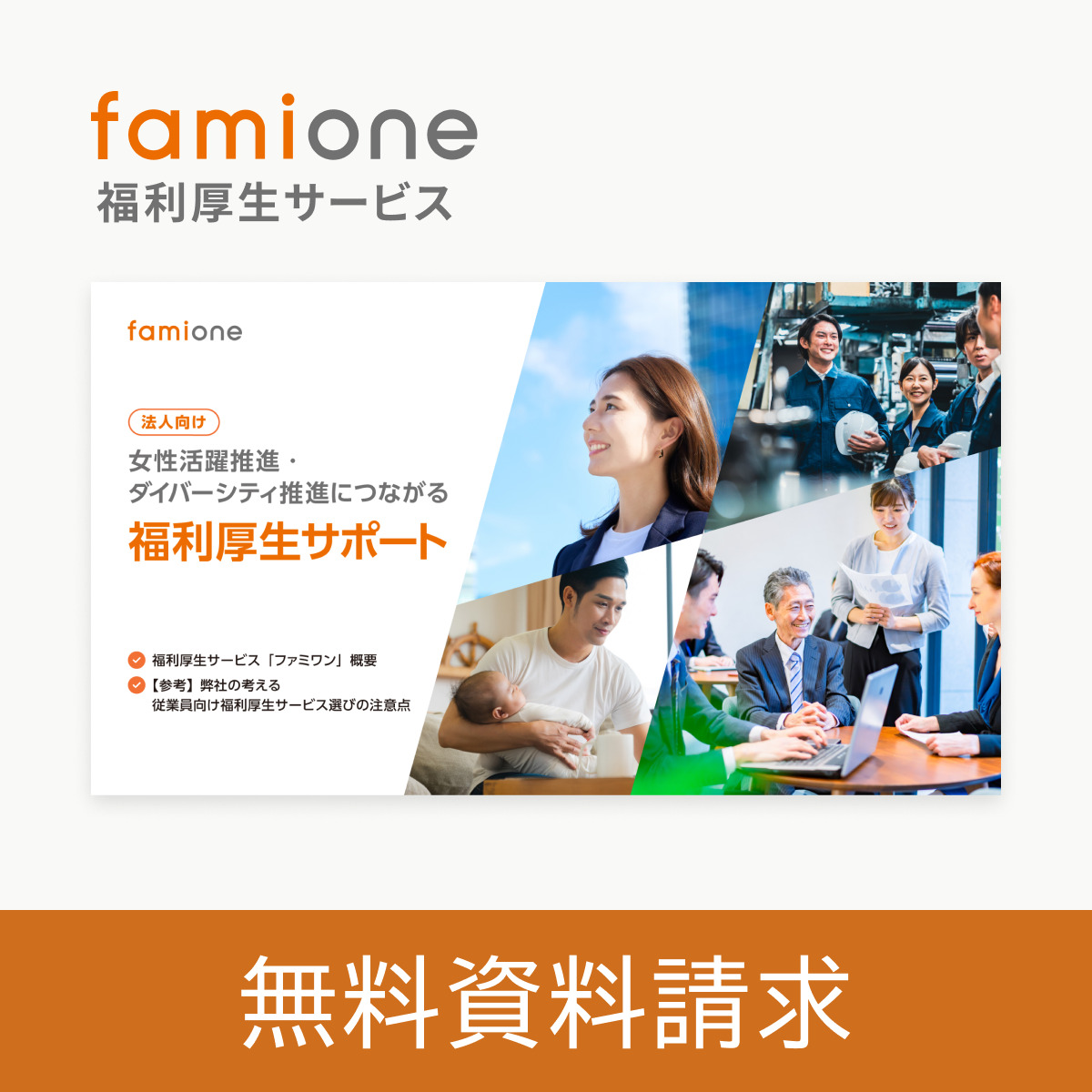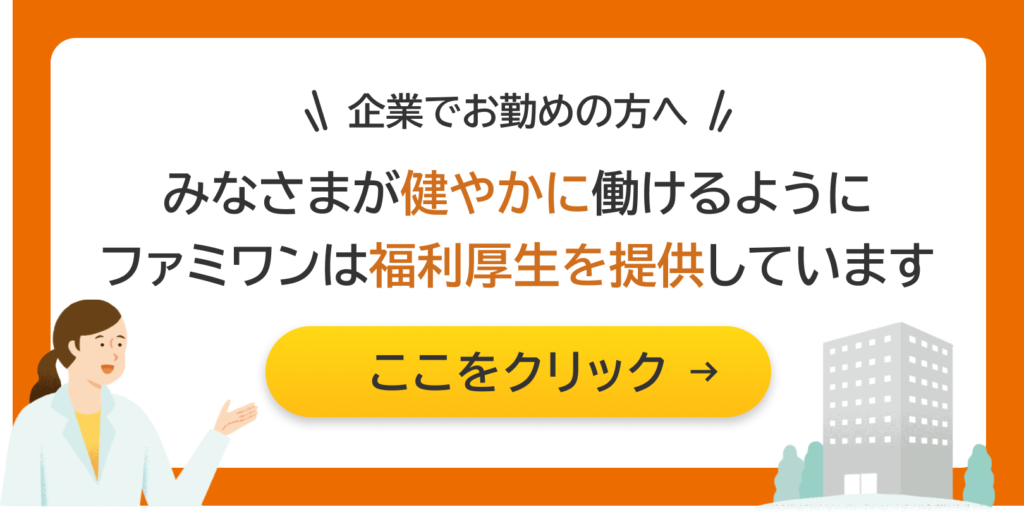子どもが入院すると長時間ベッド上で過ごす時間が多く、遊びの種類に限りがあります。
患者様の利便性を向上する目的で、院内にもフリーWi-Fi が設置されるなどタブレットやゲームの使用が院内でも容易にできる環境にあります。
入院中にタブレットやゲームを使用しスクリーンタイムが多くなりすぎてしまうと悩むご家族も多いのではないでしょうか。
また治療が優先ではありますが、子どもにとっては生活の場でもあります。
入院中は治療に関するストレスも増しますが、生活環境が変化したり、生活の場を制限されるストレスも感じることと思います。
発散できる場が限られるため、より慎重に心理的なケアが必要とされます。
① 入院生活が子どもたち及ぼす影響
入院生活が子どもたちに及ぼす影響は発達段階や年齢、環境、個々の性格により様々です。
たとえ家族が付き添い入院や面会で近くにいても入院生活は大きなストレスを感じます。
入院生活が子どもたちに及ぼす影響を年齢や発達段階に沿って説明します。
乳児期(1 歳まで)
環境の変化と母子分離が大きなストレスに。
特に母親への愛着形成や基本的な信頼感を獲得する時期であります。
生後 6~7 か月頃になると両親を認識でき、それ以外の人への人見知りが始まります。
この時期の子どもは、母 との安定した関わりを「安全基地」と捉えます。
そのため、入院によって母との分離が増えると、安心感を得る 機会が減り、基本的信頼感の発達が妨げられてしまうのです。
親しい人とそうでない人の区別がはじまると、分離不安による情緒的な反応サインとして啼泣、不機嫌、食欲不振などが現れます。
幼児前期(1 歳~3 歳まで)
母子分離への不安がもっとも強い時期です。
両親が安全基地として確認されることで、次の探索行動に向かうことができます。
この時期の子どもには「自分でやってみたい」という気持ちが芽生え、「自分で決める」「自分で遊ぶ」ことに喜びを感じます。
よって、入院による遊びや行動の制限は、大きなストレス源となるのです。
また、母子分離不安が特に強い時期であり、不安をコントロールすることができません。
母がそばにいないと泣き続けたり、一緒に過ごす時間が普段より少し短くなっただけでも、夜泣きが増えたりすることがあります。
幼児後期(4 歳~6 歳まで)
病院や医療者への警戒心や恐怖心が強まる時期です。
基本的生活習慣を自主的に実施するようになり好奇心旺盛になります。また集中力が伸び、好奇心がよりいっそう旺盛になり、周囲のものやできごとに対して「どうして?」
「なぜ?」と疑問や興味をもつようになります。入院していること、症状、医療行為などに対して「どうして?」と疑問を抱きますが、説明を聞いても十分に理解できるところには達しません。
そのギャップが、この時期の子どもを苦しめることになるのです。
また、医療行為や処置に対する恐怖心が強まるのもこの時期です。
緊張や怖さのあまりに暴れたり、逃げたりすることがあります。
指しゃぶりや夜尿など、何らかの退行現象が現れることもめずらしくはありません。
そして、入院生活に慣れてきた頃や医療介入が減少していった先にも「看護師さんが会いに来てくれなくなった」「一緒に遊ぶ人がいない」などと、孤独感を感じることがあります。
学童期(7 歳~)
学年が進むにつれ仲間意識が高まります。
具体的な思考から抽象的な思考へ進み、友達や学校の先生など、家庭外での人との結びつきが重要な時期です。
この時期に入院を余儀なくされると、友達との分離の辛さ、学校へ通えないことへの焦りや劣等感などを感じやすくなります。
また、病状や治療について自分で考えられるようになるあまり、想像から不安や恐怖が発生しやすくなるのも学童期にみられる特徴です。
そして、「治療=受け身」の状態もまた、ストレスを感じる一因です。
「自分でやりたい」「自分で考えたい」という気持ちが強いのにも関わらず、治療方針が医師や親によって決められていうことにストレスを覚えることもあるでしょう。
② タブレットやゲーム使用について
近年入院中にタブレット視聴をしている子どもが多く、メリットやデメリットがあり非常に難しい問題です。
長時間タブレットを視聴すると、視力の低下や睡眠障害・依存症といったデメリットがあります。
入院中に限らず、家庭の中でも問題になっている事案であります。
対策
- ・1 日のタブレット使用時間の上限を決める。
- ・1 時間ごとに 5 分程度、目を休ませる休憩時間のルールを決める。
- ・1日のスケジュールを立て、治療や学習とのバランスをとる。


図参照 KF STUDIO キッズ生活 予定表
時間軸が理解できる年齢であれば、時計や表を活用し1日のスケジュールをあらかじめ決めます。
児の状態によっては一緒にスケジュールを考え、上記のような紙に記載すると効果的な意識づけになります。
また病室内の見える場所にスケジュールを貼ったり、家族内だけでなく医療者側とも共有することが大切です。
スケジュールを組む前に、医療者側へ当日や明日の日程を聞いておくといいでしょう。
その際は年齢や子どもの性格によっては採血などの侵襲的な処置がある場合、前日に処置があることがわかってしまうと不安を覚え夜間不眠になることも少なくありません。
家族と医療者ですり合わせ、子どもにとって侵襲的な処置をどう伝えるか慎重に協議する必要があります。
③ 連携したい職種
病院には多職種が連携し子どもの入院生活を支えています。
どのように介入していて、どんなことをサポートしてくれるか理解をしておきましょう。
医師
治療のスケジュールや病状把握。診察を行い必要に応じ、検査を指示します。
病棟看護師
日常的なケア方法や子どもの様子を一番近くでサポートします。医師の診療の補助や、実際に採血や与薬、検査の介助や準備を行います。患者様と医師、患者様と多職種など円滑に治療が進むように間に入りサポートしていきます。医師に言いにくい、こんなこと聞いていいのか?など少しの疑問でも身近に相談できます。
薬剤師
薬の作用や副作用はもちろんのこと、内服方法の提案や注意点も家族と一緒に考えてくれます。
栄養士
疾患の症状や薬の副作用、入院中のストレスで食事に影響することがあります。年齢や体重当たりのカロリー数や栄養面の評価を行ってくれます。
病棟保育士
病室でできる遊びの提案。安静度によってはプレイルームの活用もおすすめです。
子どもの嗜好に合わせた関りをし、信頼関係を築き子どもが心を開きやすい存在です。
また付き添い入院中は付き添い者も環境の変化や子どもの介護で疲弊します。
子どもとも離れる時間が必要であり、病棟保育士に預け、介護者はリフレッシュするなど、子どもをみんなでみていく環境を作りましょう。
④ 医療者と連携するにあたり
子どもの入院生活環境を考えるにあたり医療者と連携が重要となります。
しかし多忙な業務や他の患者の対応など話しかけずらいな、、、。と感じる方も多いのではないでしょうか。
医療者へのより良いアプローチ方法については以下の通りです。
・質問したいこと、疑問に思うことをメモに残す。
・気になる症状が出現した場合写真や動画に残す。
・医療用語でわからないことがあればその場で質問する。
・家族内でも子どもの病気や入院生活についてコミュニケーションをとり共有する。
・重要な説明や決定事項は一人で抱え込まず両親、祖父母などに立ち会ってもらう。
・長期入院されている患者様や、退院後長期に渡りフォローしていく必要がある疾患の中に、コミュニティを作り活動している場合があります。
情報共有や相談の場とされており患者様だけでなく家族も積極的に活動されています。
各協会や学会などが主催している場合もあり、医師に相談してみるのもよいでしょう。
入院中の子どもは大きなストレスを抱えながら治療に専念されています。
よりよい治療の場、生活の場を子どもを中心とした家族や多職種で支えていくことが重要です。
タブレットなどの使用や制限を考慮する中でも、労いの言葉かけも必要です。
少しでもストレスが軽減した毎日が送れるよう、気軽に医療者に相談していきましょう。
〈参考文献〉
・看護教育研究学会 子どもへの看護師のかかわり
・日本小児科学会 入院しているこどもの家族支援
・日本家族看護学会 入院中の病児をもつ家族が看護師に期待する家族支援