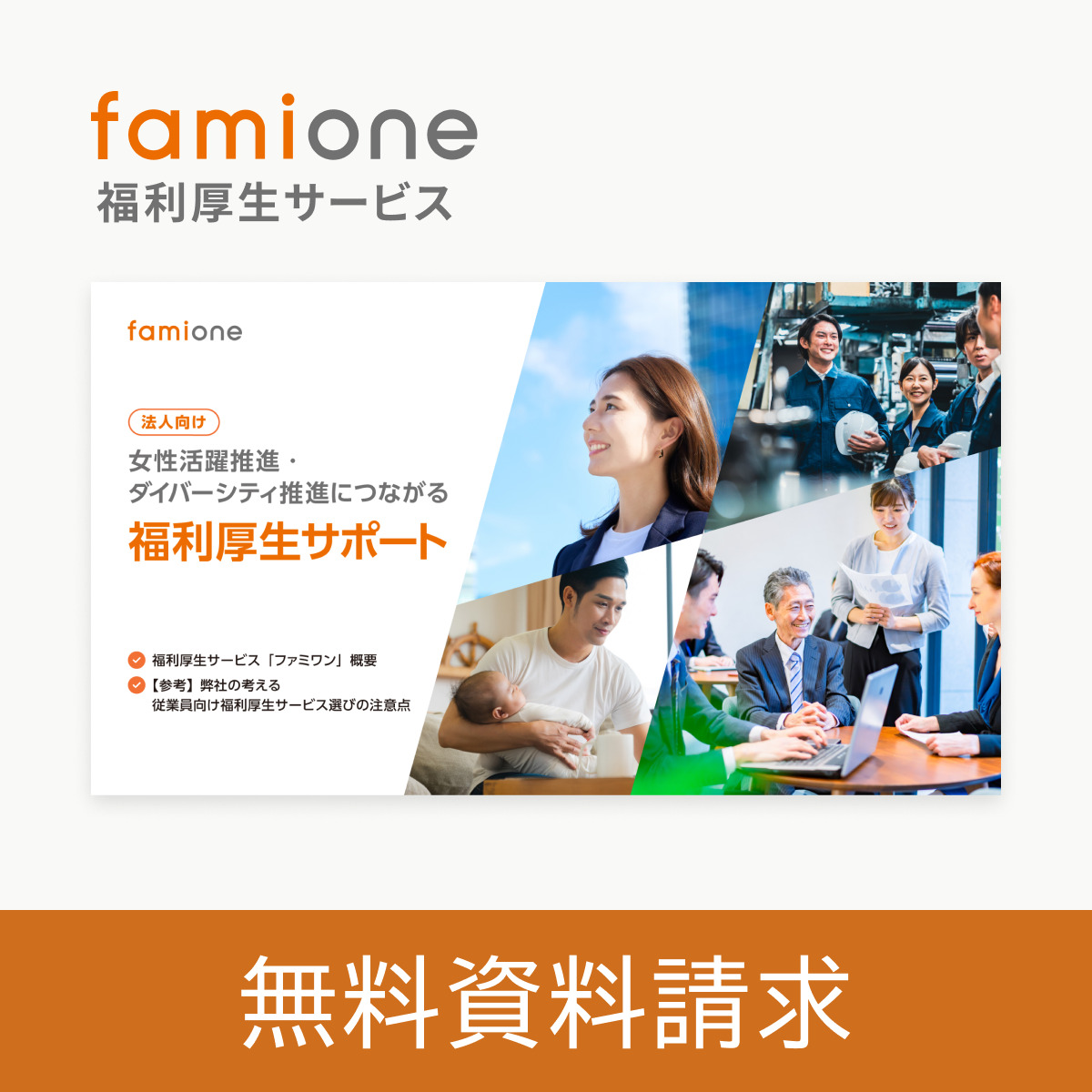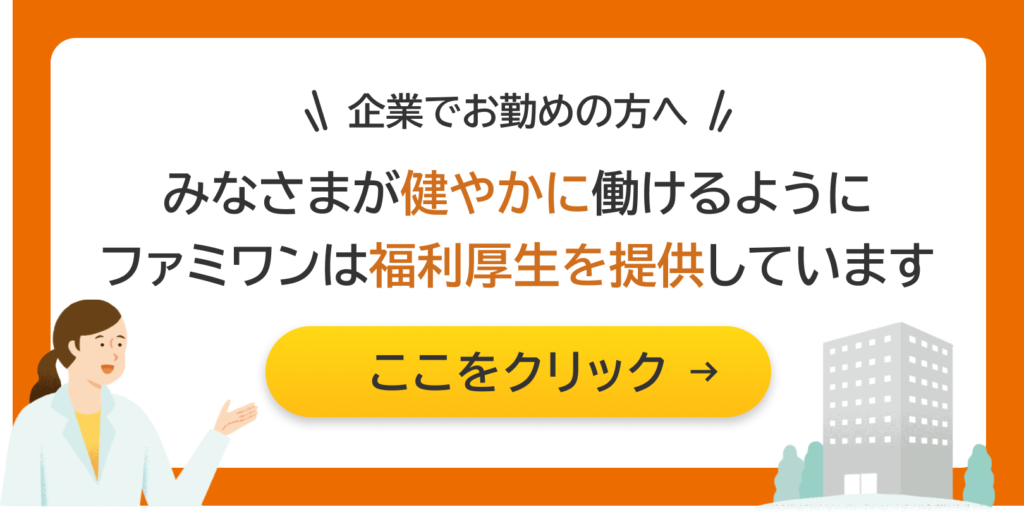はじめに
「最近、生理が不規則になってきた」「量が変わってきた」「周期が読めない」
40代になると、そんな生理の変化を感じることが少しずつ増えていきます。
これは、30代半ば頃からゆるやかに卵巣の働きが低下し、40代半ばにはその変化がより大きくなることで、女性ホルモンの分泌にゆらぎが生じるために起こるものです。
生理の変化は、身体が次のステージへ移ろうとしていることを教えてくれる、わかりやすく大切なサインでもあります。
「これって大丈夫?」「もう更年期に入っているのかな?」と不安に感じることもあるかもしれません。
でも、その変化にはきちんと理由があります。
自分の身体の仕組みを知ることが、セルフケアの第一歩です。
今回は、更年期世代の生理に起こる変化について、身体の声に耳を傾けながらお伝えします。
生理のしくみと更年期に生理が乱れる理由
生理が起こる一連の周期は、「脳」「卵巣」「子宮」がチームのように連携して働くことで成り立つ「女性ホルモンのリズム」です。
このリズムを支えているのが、主に2つの女性ホルモン、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)。
まず、脳から分泌される「卵胞刺激ホルモン」によって卵巣の中で卵胞が育ち、成熟の過程で「エストロゲン」が分泌されます。
エストロゲンは子宮内膜を厚くして、妊娠に備える準備を整えます。
排卵が起こると、卵胞は「黄体」に変化し、もうひとつの女性ホルモンである「プロゲステロン」を分泌します。
このホルモンの働きで、子宮内膜は受精卵を迎え入れるためにさらにふかふかの状態になります。
妊娠が成立しなかった場合、エストロゲンとプロゲステロンの分泌が低下し、厚くなった子宮内膜が剥がれ落ちて生理として体外に排出されます。
このように、生理は「脳」「卵巣」「子宮」の連携と、女性ホルモンの繊細なバランスによって起こっています。
ところが、30代半ばを過ぎた頃から卵巣の働きは少しずつ衰えはじめ、40代半ばになるとその変化がより顕著になります。
年齢とともに卵のもとである「原始卵胞」の数が減少し、さらには卵胞がうまく育たなかったり、排卵が起こらない「無排卵周期」が増えたりすることで、エストロゲンやプロゲステロンの分泌が不安定になります。
その結果、
- ●月経周期が短くなったり長くなったりする
- ●経血量が増えたり減ったりする
といった、生理のリズムの乱れが生じてきます。
つまり、生理の変化は、卵巣機能の低下によって女性ホルモンのリズムが少しずつゆらぎ始めているサイン。 それは、身体が次のステージへと移ろうとしている、自然で大切な変化なのです。
閉経までの生理の変化
閉経とは、「1年間生理が来ない状態」を指します。
その前には、個人差の大きい「移行期」があり、この時期には生理周期や経血量が不安定になることが多くみられます。
よくある変化には、次のようなものがあります。
- ●周期が短くなったり、長くなったりする
- ●経血量が少なくなったり、多くなったりする
- ●出血がだらだらと続く
- ●突然大量出血が起こる
- ●生理なのか不正出血なのか判断しにくい
このように、閉経までの道のりは人それぞれ。
一般的には、生理周期が短くなったあと、徐々に間隔があいて閉経へと向かうケースが多いといわれています。
ただし、「どのパターンが正常」という決まりはありません。
自分の身体のリズムを観察し、変化を記録しておくことが大切です。 カレンダーやアプリに生理周期や生理の状態をメモしておくと、体調の変化を客観的に把握でき、受診時にも役立ちます。
過多月経と貧血
更年期の生理では、一般的には経血量が少なくなっていくことが多いものの、ホルモンバランスの乱れによって「過多月経」が起こることがあります。
「女性ホルモンのせい」「更年期だから仕方ない」と放っておくと、鉄欠乏性貧血につながることもあります。
貧血になると、疲れやすい、めまい、立ちくらみ、動悸、息切れ、気分の落ち込み、やる気の低下など、日常生活にじわじわと影響を及ぼします。
こうした症状に“慣れてしまう”のが怖いところ。
さらには、慢性的な貧血は心臓に負担をかけ、心不全を引き起こすこともあります。
貧血は「身体の小さなサイン」ではなく、「生活の質(QOL)」を左右する大きな問題なのです。
また、過多月経の背景にはホルモンバランスの乱れだけでなく、子宮筋腫・子宮腺筋症・子宮内膜ポリープなどの疾患が隠れている場合もあります。 出血量が増えた、出血が長引く、体調がすぐれない、そんな変化を感じたら、早めに婦人科で相談しましょう。
不正出血にも注意
更年期は、ホルモンバランスの乱れに加えて、婦人科系の病気が増える時期でもあります。
経血量の変化だけでなく、生理以外の出血(不正出血)が起こることもあります。
不正出血はホルモンバランスの乱れでも起こりますが、
子宮体がん(※子宮頸がんとは異なります)、萎縮性腟炎、子宮筋腫、子宮ポリープなどの疾患が原因のこともあります。
出血が「生理なのか不正出血なのか分からない」ときは、自己判断せず早めに受診を。
おりものの変化にも注目
更年期には、生理の変化とともに「おりもの(帯下)」の変化を感じる人も少なくありません。
おりものは、腟や子宮頸部から分泌される液体で、腟内を潤し感染を防ぐ大切な役割を担っています。
その量や状態は、女性ホルモンの影響を大きく受けます。
エストロゲンの減少によって、おりものが減り、腟の乾燥や不快感を感じやすくなることがあります。
一方で、乾燥を補うために頸管粘液の分泌が増え、おりものが多くなる人もいます。
また、腟の乾燥から炎症(腟炎)が起こり、その刺激でおりものが増えるケースもあります。
【注意すべき異常なおりもののサイン】
- ●色がいつもと違う:黄色っぽい、緑色、茶色、黒っぽい、灰色など、普段見慣れない色
- ●臭いが強い:生臭い、ツンとする、腐敗臭のような不快な臭い
- ●量が異常に多い
- ●性状がいつもと違う:泡状、カッテージチーズ状(酒粕状)など
- ●症状を伴う:外陰部のかゆみ・痛み・ヒリヒリ感・灼熱感など
こうした変化は「治療が必要なサイン」であることも。
気になるときは、ひとりで抱え込まず、早めに婦人科で相談しましょう。
「かかりつけの婦人科」を持つことが大事
更年期は誰にでも訪れる自然な変化です。
しかし、その現れ方や感じ方は人それぞれ。
だからこそ、自分の体を長期的に見守ってくれるかかりつけの婦人科を持つことが、何よりの安心につながります。
婦人科は「病気になったときだけ行く場所」ではありません。
生理やおりものの変化、体調のゆらぎを気軽に相談できる場所です。
日々の変化をカレンダーやアプリに記録しておくと、受診時の情報共有にも役立ちます。 信頼できるかかりつけの婦人科を上手に活用しましょう。
まとめ
閉経までの道のりは、まさに“変化の連続”。
生理やおりものの変化は、身体が次のステージへ移ろうとしているサインです。
女性ホルモンの仕組みを理解し、変化を「怖いこと」ではなく「自然のリズムの一部」として受け止めることで、更年期は“終わり”ではなく、“再スタートの準備期間”になります。
不安なときは我慢せず、早めに相談を。
そして、日々の小さな変化を感じ取りながら、自分の体と穏やかに付き合っていきましょう。
参考文献
- 1. 医療情報科学研究所(編集).『病気が見える vol.9 婦人科・乳腺外科〔第4版〕』.岡庭 豊 (発行者),株式会社メディックメディア,平成30年.
- 2. 対馬 ルリ子,吉川 千明.『「閉経」のホントがわかる本 更年期の体と心がラクになる!』.集英社,2020年.