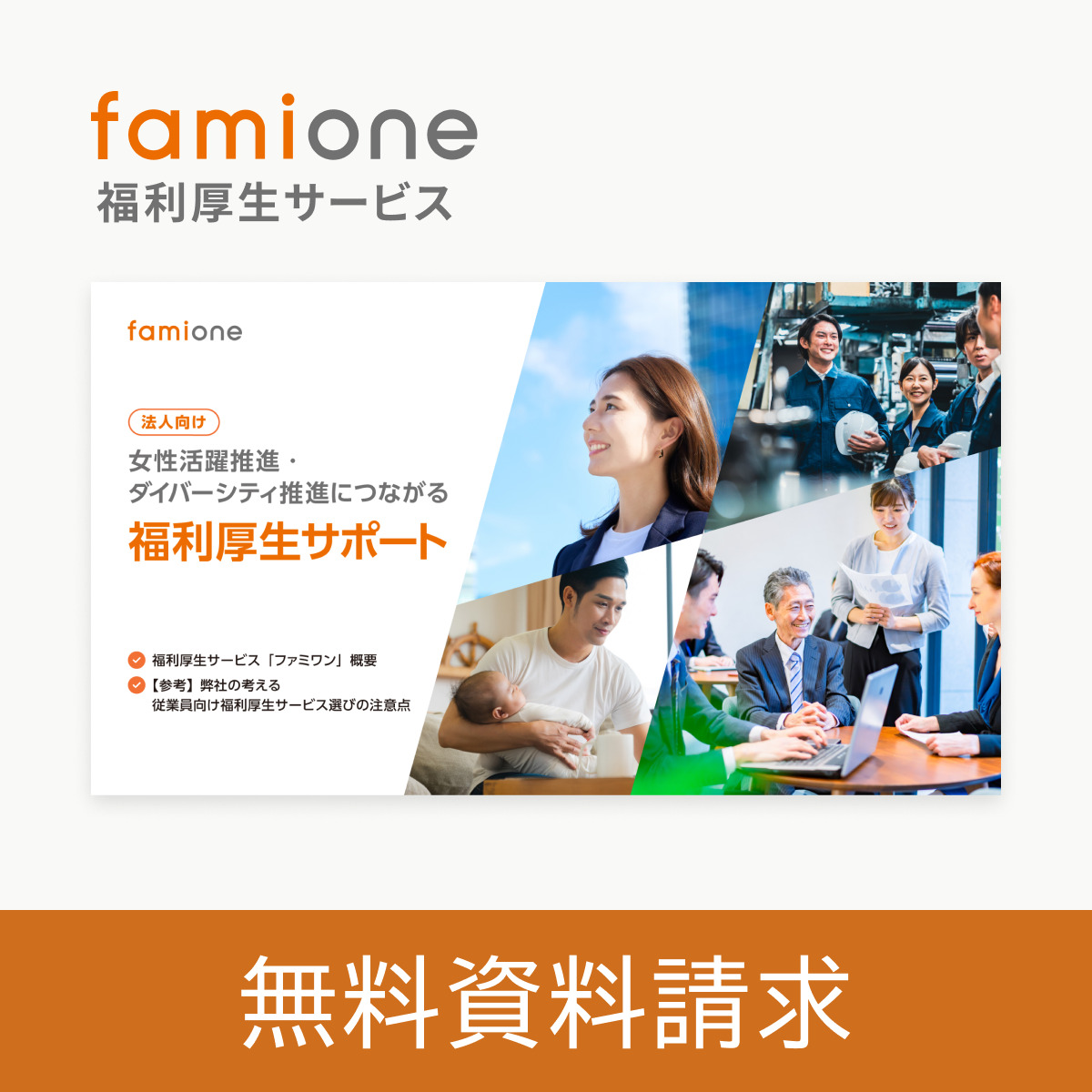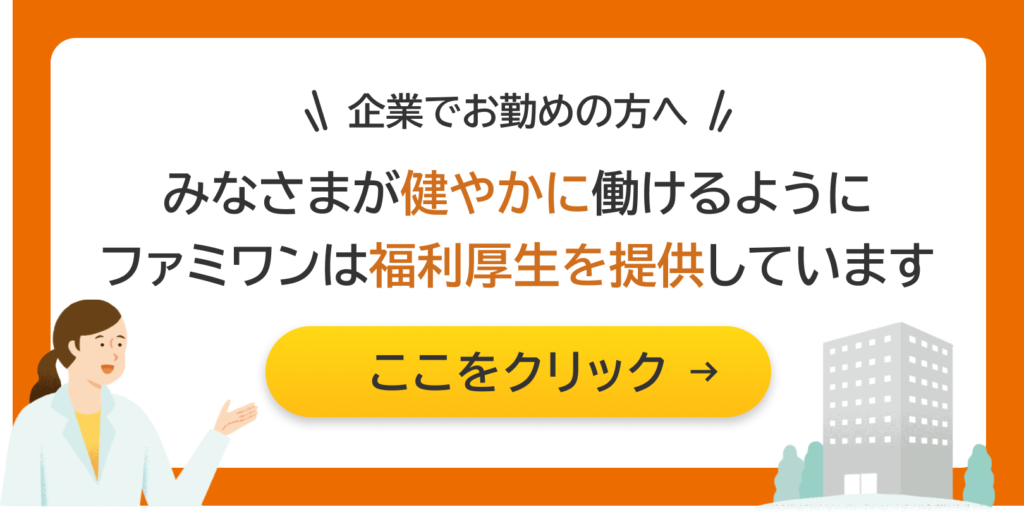ご家庭に常備している薬、お子さんの手の届くところにありませんか?
子どもは予測のつかない動きをすることもあります。気をつけているつもりでもほんの一瞬の隙に思わぬ事故につながることもあるので、注意が必要です。
今回は、子どもの薬の誤飲食を防ぐための対策、もしも事故が起こってしまった時の対処法についてお伝えします!
医薬品の誤飲食の現状
最近の調査報告によると、誤飲食の事故を起こした年齢は特に自ら包装を開けて薬を取り出せるようになる1〜2歳児にかけて多くみられるとされています。
医薬品の誤飲食事故は毎年事故原因の上位を占め、後を絶ちません。
また、子供の事故においては9割が自宅で発生しているというデータもあります。
なぜ子どもは薬を誤飲するのか?
子どもが誤飲食をしやすい原因として、子どもの好奇心と探索行動があげられます。
誤飲食の事故は何でも口に入れて確かめようとする生後6ヶ月ごろから起こりやすいとされており、身近にあるものへの興味や関心が高まる時期の行動特性が影響しています。
特にシロップ剤や錠剤などは子どもの視点からお菓子やおもちゃのように見えることもあり、何気なく口の中に入れてしまいやすいのです。
また、保護者の認識不足・油断から「これくらい大丈夫だろう」「見ているから」という安易な考えが事故を招くこともあります。
例えば、飲みかけの薬をテーブルに置きっぱなしにしたり、保管を適切に行っていなかった時、保護者が目を離した隙に、など日常のふとした油断が事故につながるケースも多いです。
実際に、子ども本人に処方された薬を誤飲する事例よりも、別の家族に処方されたものを誤飲食してしまう事例が多いとされています。
誤飲食の影響
医薬品には向精神薬、血圧降下薬、血糖降下薬、抗凝固薬など乳幼児にとって危険な薬効を持つものが多くあります。
大人の1錠分は、乳幼児では何倍もの用量にあたるため、医薬品の誤飲食は重い中毒症状や命にかかわる危険が伴います。
処方されるお薬だけでなく、市販薬やサプリメント、漢方薬なども例外ではありません。
▼実際に発生した誤飲事故の例
・「母親がトイレに行っている間に、バッグに入っていた風邪薬を誤って飲み、入院することになった」
・「医師から処方されたシロップの薬をジュースと誤って飲んでしまい、ふらつきが出た」
・「家族が置き忘れた精神安定剤を誤って飲んでしまい、子どもが意識混濁に陥った」
・「下剤をお菓子と誤認し飲んだことで、下痢の症状が出た」
上記の例からも誤飲食の事故はどの家庭でも起こりうる非常に身近なものであることがわかります。
大切なお子さんが思わぬ事故にあわないよう、大人がしっかり対策をすることが重要なのです。
子どもの薬誤飲を防ぐための対策は?
①手の届かない場所・見えない場所に保管する
鍵のかかる引き出し、高い棚、チャイルドロック付きの戸棚などで子どもの目線で手が届かない場所に保管しましょう。
誤飲食事故または誤飲食未遂発生時に、子どもが手に取った医薬品の高さは、足場がない場合では0歳でも3歳以上でも50cm程度であったことから、まずは医薬品を一定以上の高さに置くことが大切です。
足場がある場合では2歳以上であれば100cm程度となっており、年齢が高くなるにつれ、高いところの医薬品を手に取る傾向にあります。
大人が思っている以上に子どもの発達が早く、子どもの年齢や発達段階によって事故防止をする必要があることも意識しておきましょう。
②使用後はすぐに元の保管場所へ戻す
先述した通り、事故は大人のちょっとした油断で起きてしまいます。
薬を出した後は放置せず、必ず元の保管場所へ戻すことを意識しましょう。
③子どもの前で薬を飲まない・薬の話題を出さない
子どもが薬に興味を持つきっかけを作らないための配慮となります。
分別が付く年齢であれば日頃から「これはお菓子ではないよ」と教えておくことも重要です。
④来客時や外出先でも注意
これからの時期、夏休みなどで実家や友人宅、旅行先などを訪問する機会も多いでしょう。
普段と違う環境においても誤飲食のリスクがあります。
子どものおじいちゃん・おばあちゃんにあたる高齢者は普段から薬を飲んでいるケースも多く、保管場所にそこまで注意が行き届いていない可能性があります。
他人の薬にも注意を払い、事前に注意喚起もしておきましょう。
もしも誤飲してしまったら?
まずは落ち着いて状況確認
お子さんのまさかの事態に親はどうしてもパニックになりがちですが、まずは落ち着いて状況確認をしましょう。
事故が起きてしまったとしても迅速かつ適切に対応することが重症化のリスク軽減にもつながります。
特に「何を、いつ、どのくらい誤飲食してしまったのか、子どもの状態はどうか」を把握します。状況を把握したら、直ちに専門の相談機関に連絡するか、必要に応じて医療機関を受診してください。
相談先としては、「小児救急電話相談(#8000)」や「公益財団法人日本中毒情報センターの中毒110番」があります。いざという時のために連絡先をメモして掲示しておくと安心です。
①「小児救急電話相談」
連絡先:■#8000
※全国同一の短縮番号(#8000)をプッシュすることにより、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送されます。
②「中毒110番・電話サービスの利用方法(一般専用)」
連絡先:
■大阪中毒110番(365日 24時間対応) 072−727−2499(情報提供料:無料)
■つくば中毒110番(365日 9時〜 21時対応) 029−852−9999(情報提供料:無料)
※意識がない、呼吸がおかしい、けいれんしているなど、緊急性の高い症状の場合は迷わずすぐに救急車を呼んでください。
さいごに
薬は時には子どもの命を守るものですが、誤飲食によって危険なものにもなり得えます。
大人が普段から子どもの安全のための意識と対策を講じていくことが非常に重要です。
お子さんの安心のために、ぜひ今一度ご家庭の薬の保管状況を見直しましょう!
●参考文献
・厚生労働省:子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策について
・消費者庁ホームページ