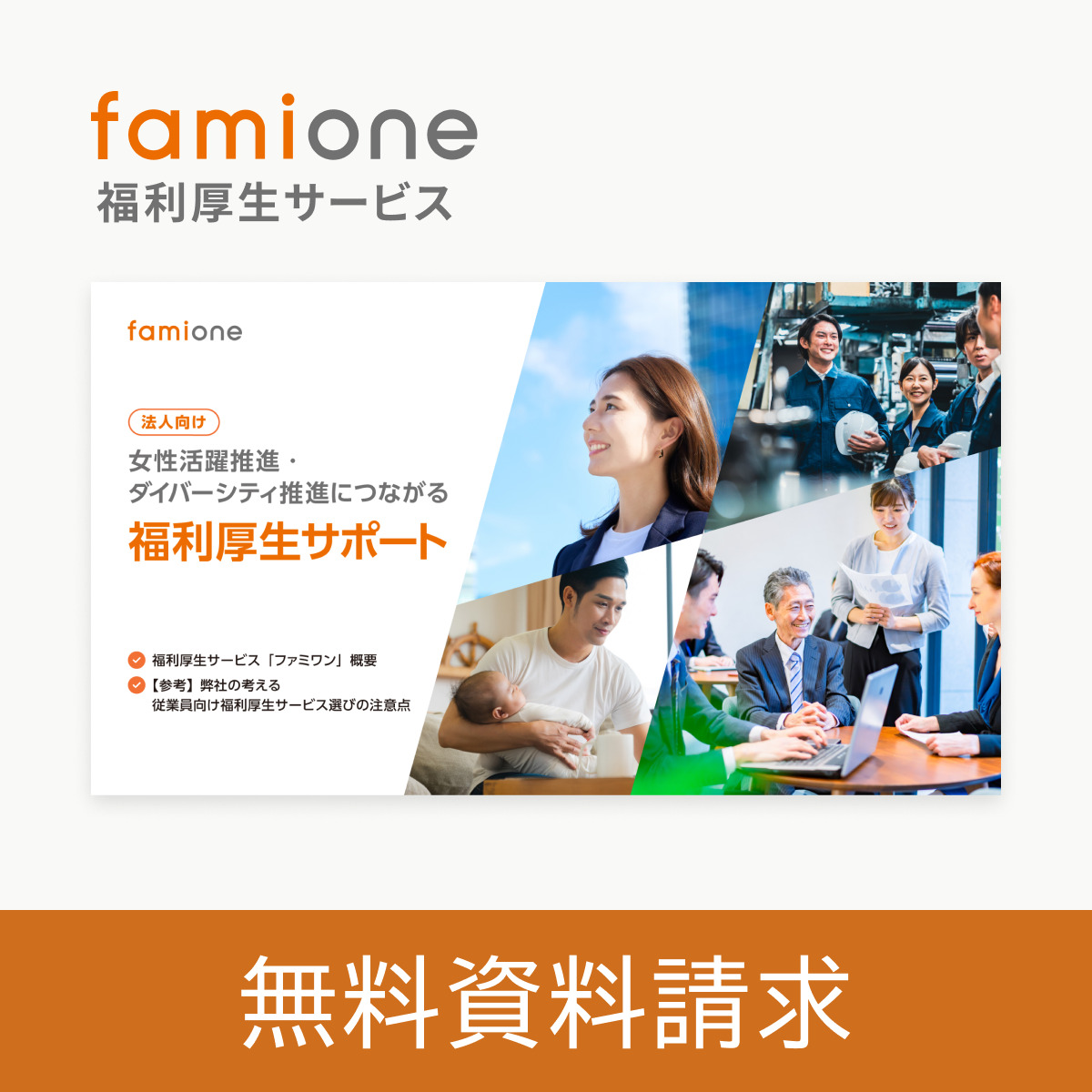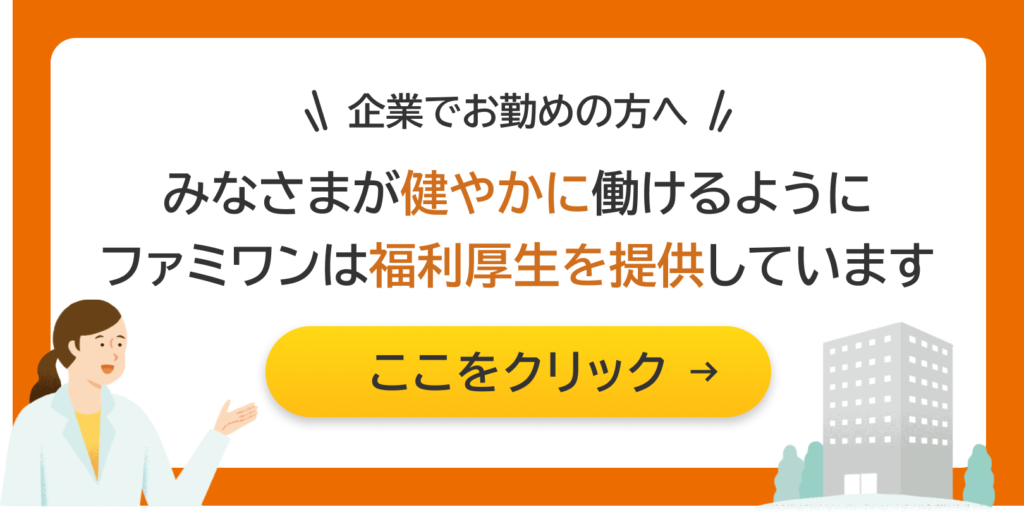冬の寒さが本格化すると、私たちの体は知らず知らずのうちに冷えにさらされています。
特に手足の冷たさを感じたり、時には痛みを伴ったりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな時に重宝する電気毛布や湯たんぽ、カイロなどの保温グッズ。とても便利ではありますが、ちょっとした温め方の油断で「低温やけど(低温熱傷)」を起こしてしまうことがあります。
今回は、日常生活でついやってしまいがちな“危険なあたため方”と、安全に体を温めるための工夫、さらに万が一低温やけどになった場合の対応についてお話させていただきます。
低温やけどとは?
低温やけどは、熱いものに触れた瞬間に起こる通常の熱傷とは少し性質が異なります。熱湯やストーブの炎に触れれば、瞬時に皮膚が赤くなったり水ぶくれができますが、低温やけどは 40~50℃くらいの「そこまで熱くはないけれど長時間触れる熱源」に皮膚がさらされることで起こります。
電気毛布や湯たんぽ、ホットカーペット、暖房器具などが典型的な原因です。重要なのは、「熱くない」と感じても皮膚の深い層まで熱が蓄積され、じわじわ損傷が進むことがある点です。皮膚は表皮、真皮、皮下組織の三層構造を持ち、低温でも長時間熱が加わると、特に血流の少ない手足の末端や圧迫されやすい部位では深部まで損傷が及ぶことがあります。
また、高齢者や糖尿病、末梢循環障害のある方は皮膚感覚が鈍くなっているため、自覚症状が出にくく、気づかないうちに低温やけどが進行しやすいです。乳幼児も皮膚が薄いため注意が必要です。
低温やけどが起こりやすい場面
電気毛布や湯たんぽ
冬は寝る前に布団を温めたくなります。しかし、毛布や湯たんぽを長時間同じ部位にあて続けると皮膚表面の温度がじわじわ上昇し、水ぶくれや赤みが出ることがあります。特に就寝中は無意識に同じ姿勢でいる時間が長いため、低温やけどになりやすいため注意が必要です。
ホットカーペットや暖房器具
足裏や膝の裏を直接あてて長時間座っていると、皮膚が熱をもってしまいます。冬場のソファやこたつでうたた寝すると、意外と深く損傷が及ぶことがあります。これは皮膚と床の間に熱がこもり、血流が限られた状態で熱が加わるためです。
衣類や靴下の重ね履き
厚手の靴下やカイロを重ねすぎると、皮膚と熱源の間の空気がこもり熱が逃げにくくなります。長時間熱が加わると、皮膚の表面血流が増えすぎて逆に損傷が起こることがあります。
低温やけどの症状と進行
低温やけどは、通常の熱傷より進行がゆっくりと進みます。そのため最初は自覚症状が軽くても、時間が経つと深く損傷が広がることがあります。
● 初期症状:皮膚の赤み、かゆみ、軽い痛み
● 進行すると:水ぶくれやただれ、皮膚の硬化
● 重症化:真皮や皮下組織まで損傷、治療に時間がかかることも
「触っても熱く感じない」「痛みが軽いから大丈夫」と思いがちですが、皮膚の奥まで損傷が及んでいることがあるため注意が必要です。
低温熱傷の診断と検査
低温やけどの診断では、損傷の広さ・深さ・部位の確認が非常に重要です。
必要に応じて、全身の状態を把握するために血液検査や尿検査が行われることもあります。特に重症例では感染の有無や全身の炎症反応を確認する目的で検査が行われます。
皮膚の損傷深度は以下の目安で分類されます:
● 表皮のみの損傷(1度熱傷):赤みや軽い腫れ、痛みのみ
● 真皮浅層までの損傷(2度熱傷):水ぶくれ、赤み、軽度の潰瘍
● 真皮深層~皮下組織まで(3度熱傷):皮膚の硬化、壊死、痛みを感じにくい
低温熱傷の応急処置と治療
低温熱傷を負った場合、まずは熱源から皮膚を離すことが第一です。
1. 冷却
低温熱傷は「熱が皮膚深層に蓄積」した状態です。流水で15~30分ほど冷やすことで損傷の進行を抑えられます。氷を直接当てるのは凍傷のリスクがあるため避けてください。
2. 清潔保持
水ぶくれが破れた場合は清潔なガーゼで覆い、感染を防ぎます。軟膏や抗菌薬は医師の指示に従い使用します。
3. 治療の種類(損傷度による)
・1度熱傷:乾燥を防ぐために保湿剤や軟膏で対応
・2度熱傷:感染防止のため洗浄後、軟膏や被覆材で治療
・3度熱傷:皮膚組織が壊死するため、広範囲では植皮手術が必要になることもあります。抗菌薬の投与が行われる場合もあります
4. 受診の目安
・水ぶくれが大きい
・痛みが強い
・皮膚の色が白や黒に変化
こうした場合は、早めに医療機関を受診しましょう。低温やけどは見た目より深く損傷していることがあるためご自身でこれくらい大丈夫と判断されずに医療機関に相談される事をおすすめします。
日常でできる低温やけどの予防法
寒い冬に体を安全に温めるためには、次のポイントを意識しましょう。
1.直接肌に熱源をあてない
薄手のタオルや衣類越しに使用することで、熱の蓄積を防げます。
2.使用時間を決める
長時間の使用は避け、タイマーを活用。就寝中はオフにするのがおすすめです。
3.体全体を温める
足先だけでなく、首、背中、手首なども温めると血流がよくなり、低温やけどのリスクが減ります。
4.血流改善を意識する
軽いストレッチや手足の運動、入浴で血行を促進することも効果的です。
5.皮膚の状態をこまめにチェック
高齢者や糖尿病の方は皮膚感覚が鈍ることがあります。手足の色、温度、感覚の変化を確認しましょう。
最後に
私自身も寒い日には湯たんぽやカイロに頼りがちですが、「ちょっと肌に触れすぎたかも」と思ったらすぐ熱源を離すようにしています。日々の小さな工夫が、低温やけどの予防につながります。
冬は寒さとの戦いですが、正しい知識と少しの配慮で、体を安全に温めることができます。体を温めることは健康にとっても大切ですが、低温やけどという“見えない危険”があることを忘れずに。皆さんも、温かく、でも安全に冬を乗り切ってください。
参考
-日本熱傷学会. 『熱傷診療ガイドライン改訂第3版』2022
-日本皮膚科学会. 『創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン(2023)―6:熱傷診療ガイドライ
ン』
-日本形成外科学会. 「低温熱傷(やけど)」公式サイト, 2024