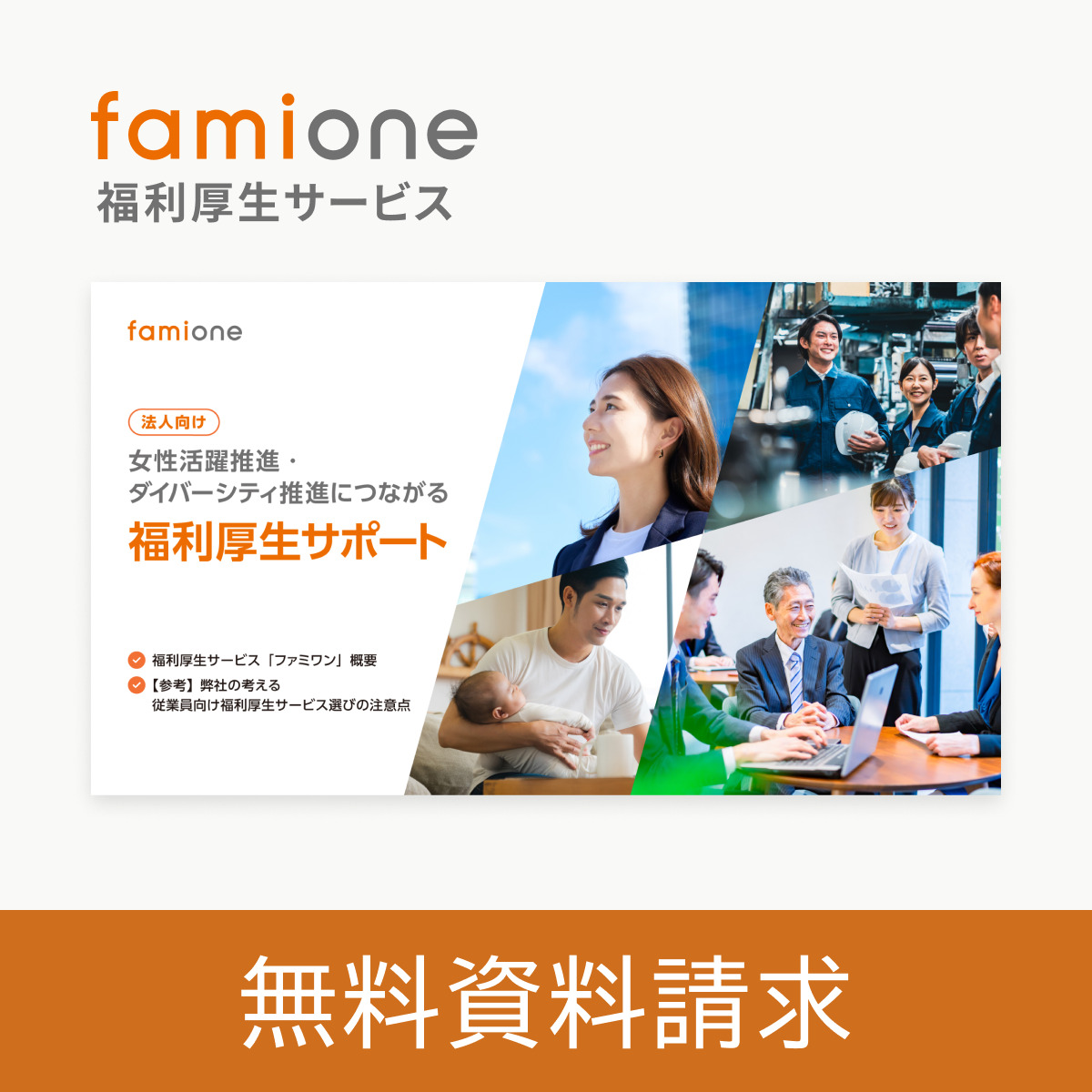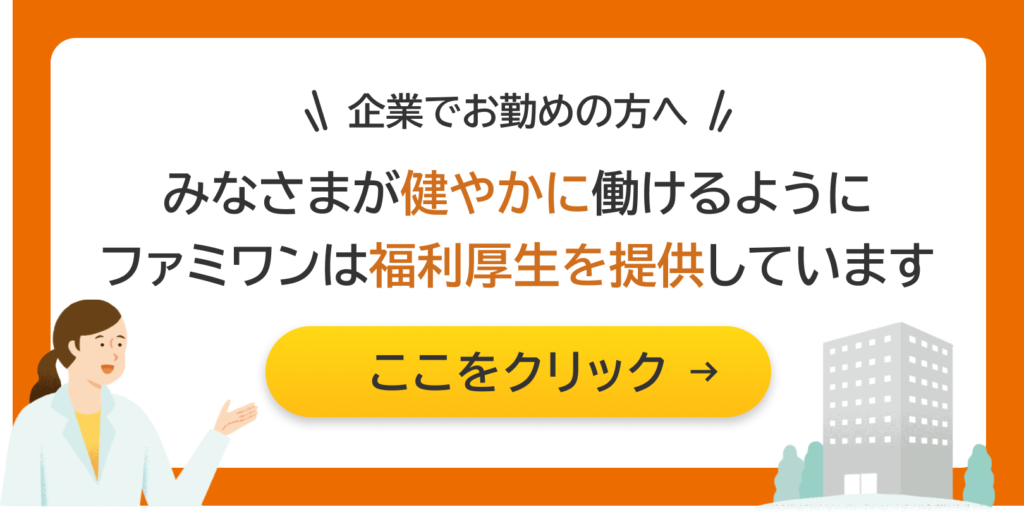はじめに
熱い夏が終わり、朝晩の空気がぐっと冷たく感じられる季節になりました。
「寒いけれど、まだ暖房をつけるのは早いかな」と思いながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。
冬は体が冷えやすく、知らないうちに体調を崩す方が増える時期です。中でも注意したいのが「低体温症」。雪山での遭難や極寒の環境で起こる病気だと思われがちですが、実は普段の生活の中でも誰にでも起こることがあります。
今回は、循環器看護師の立場から、低体温症の仕組みや症状、そして日常でできる予防法についてお伝えしたいと思います。
特に高齢の方やデスクワーク中心の方には、ぜひ知っておいていただきたい内容です。
低体温症とは?
人の体は、常に約36〜37℃の体温を一定に保つようにできています。これは、体の中の化学反応(代謝)を正常に保つための大切な働きです。しかし何らかの原因で深部体温(体の中心の温度)が35℃を下回ると、「低体温症」という状態になります。体温が1℃下がるだけでも、免疫機能が低下し、代謝が悪くなり、血液の流れも滞ります。さらに低下が続くと、脳や心臓などの重要な臓器の働きが鈍り、命に関わることもあります。
屋内でも起こる低体温症
「低体温症は屋外で起こるもの」と思う方も多いですが、実はそうではありません。
日本救急医学会の調査によると、低体温症の患者さんの約7割が屋内で発症しており、平均年齢は70歳前後。
特に冬の早朝や夜間、暖房を控えていた家庭で多く見られます。
高齢の方は、加齢によって体温調節機能が低下しているため、寒さを感じにくくなっています。
「自分では寒くない」と思っていても、体は静かに冷えていることがあるのです。
また、冬の住宅は部屋ごとの温度差が大きく、脱衣所やトイレでの急激な冷えがきっかけで体温が下がることもあります。このような環境で血圧が急上昇すると、心筋梗塞や脳卒中のリスクも高まります。
なぜ体温が下がるの?
体温の調節を担っているのは、脳の中心部にある「視床下部」という部分です。
ここが寒さを感じると、体を守るために次のような反応を起こします。
● 皮膚の血管を収縮させて熱の放散を防ぐ
● 筋肉を震わせて熱を作る
● 肝臓などの臓器で代謝を上げて体温を維持する
ところが、次のような要因があると、この体温調節がうまく働かなくなります。
● ストレスや疲労による自律神経の乱れ
● 筋肉量の減少(運動不足・加齢)
● 栄養不足、極端なダイエット
● 甲状腺機能の低下
● アルコールの摂りすぎ
● 脱水(冬でも水分不足になりやすい)
特に筋肉は「体のヒーター」と言われるほど、熱を生み出す臓器です。
運動不足で筋肉が減ると、基礎代謝も下がり、体温を維持する力が弱まります。
また、アルコールを飲むと一時的に体が温まったように感じますが、実際には血管が拡張して熱が逃げやすくなるため、体温は下がってしまいます。
低体温症のサイン
低体温症は、ゆっくり進行することが多いため、最初は自分でも気づきにくいものです。
軽度のうちは
● 強い寒気
● 体の震え
● 手足の冷え
● 体のだるさ
● 集中力の低下
といった症状が出ます。
中等度になると・・・
● 震えが止まる
● 言葉が出にくい
● 歩行が不安定になる
● 意識がもうろうとする
さらに重症化すると、呼吸や心拍が弱くなり、意識がなくなる危険もあります。
体が震えなくなったから「落ち着いた」と思っても、それは危険なサイン。
震えは体が自ら熱を作ろうとしている証拠なので、それが止まるのは危険信号です。
もし周囲にそのような方がいたら、すぐに暖かい部屋に移し、毛布で体を包んでください。
意識がはっきりしない場合や、呼びかけに反応しない場合は、すぐに救急要請を行いましょう。
室内での予防ポイント
寒い季節を元気に過ごすために、日常生活の中でできる工夫を紹介します。
室温は18〜20℃を目安に
WHO(世界保健機関)は、冬の室温を18℃以上に保つことを推奨しています。
高齢者や心疾患・呼吸器疾患のある方は、20℃程度を保つことが理想です。
光熱費を気にして暖房を控えるよりも、健康を守ることを優先しましょう。
エアコンやヒーターだけでなく、断熱カーテン・隙間テープ・床マットなどで熱を逃がさない工夫も有効です。
「首・手首・足首」を冷やさない
この3か所は太い血管が通っており、冷えると全身の体温が下がります。マフラーやネックウォーマー、レッグウォーマーを使い、外出時は手袋や帽子を忘れずに。寝るときには、湯たんぽや電気毛布で首元・腰回りを温めると安心です。
食事で内側から温める
食べ物には「体を温めるもの」「冷やすもの」があります。冬場は、生姜・にんじん・ごぼう・ねぎ・かぼちゃなどの根菜類を積極的に取り入れましょう。また、たんぱく質(肉・魚・卵・大豆製品)は熱を作るために欠かせません。特に高齢の方は食が細くなりがちですが、少しでも意識して摂るようにしましょう。カフェインを含むコーヒーや緑茶は利尿作用があり、体を冷やしやすいので、温かい麦茶や白湯もおすすめです。
軽い運動を習慣に
運動は筋肉量を保ち、冷えを防ぐ最も効果的な方法です。
デスクワーク中でも、1時間に一度は立ち上がって背伸びをしたり、肩を回したりしましょう。
また、高齢の方は転倒を防ぐために、椅子に座ったままできる足踏みやかかと上げなども効果的です。
無理のない範囲で毎日続けることが大切です。
お風呂で深部から温める
38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分ほどゆっくり浸かると、体の芯まで温まり、眠りの質も良くなります。入浴前後にはしっかり水分をとり、血圧の急な変動を防ぎましょう。特に高齢者の方は、浴室と脱衣所の温度差が大きいと血圧が急上昇する危険があります。脱衣所にも小型のヒーターを置くなどして、温度差を少なくする工夫をしてください。
高齢者への注意点
高齢者の方は、筋肉量が減るだけでなく、「寒さを感じる感覚」も鈍くなっています。そのため、自分では寒くないと思っていても、体温がじわじわ下がっていることがあります。さらに、血圧や心臓の病気、糖尿病、認知症などの持病があると、体温調節機能がより低下します。一人暮らしの場合は特に注意が必要です。
周囲の方が
• 部屋が冷えていないか
• 薄着で過ごしていないか
• 食事をしっかり摂っているか
を気にかけてあげることが、命を守るサポートになります。
最後に
寒さを「これくらいなら我慢できる」と思って過ごしていませんか?体は自分が考えている以上に冷えています。
冷えは血圧を上げ、血管を収縮させ、心臓や脳への負担を増やします。
循環器疾患をお持ちの方や高齢の方は、冷えを軽く考えず、少しでも寒さを感じたら早めに対策をとってください。
また、朝の体温がいつも35℃台という方や、疲れやすい、冷えが強いと感じる方は、甲状腺や自律神経の不調が隠れていることもあります。一度医療機関で相談してみましょう。
低体温症は、誰にでも起こり得る身近な症状です。「寒さを我慢しない」「冷えを放っておかない」ことが、健康を守る第一歩です。
温度計を見える場所に置く、体温を毎朝測る、湯たんぽを活用する。
そんな小さな工夫が、あなた自身やご家族の命を守ります。どうぞこの冬も、心も体も温かくお過ごしください。