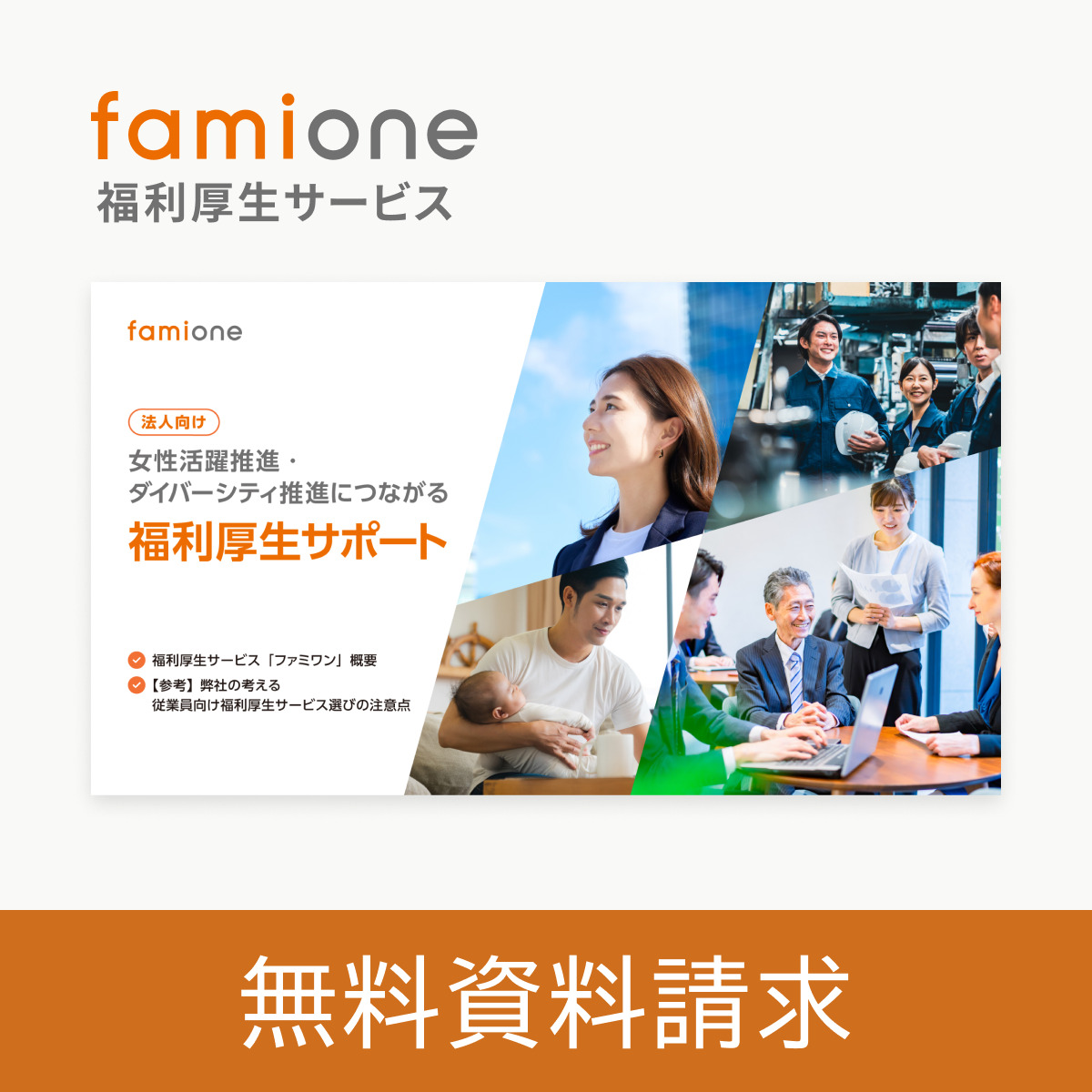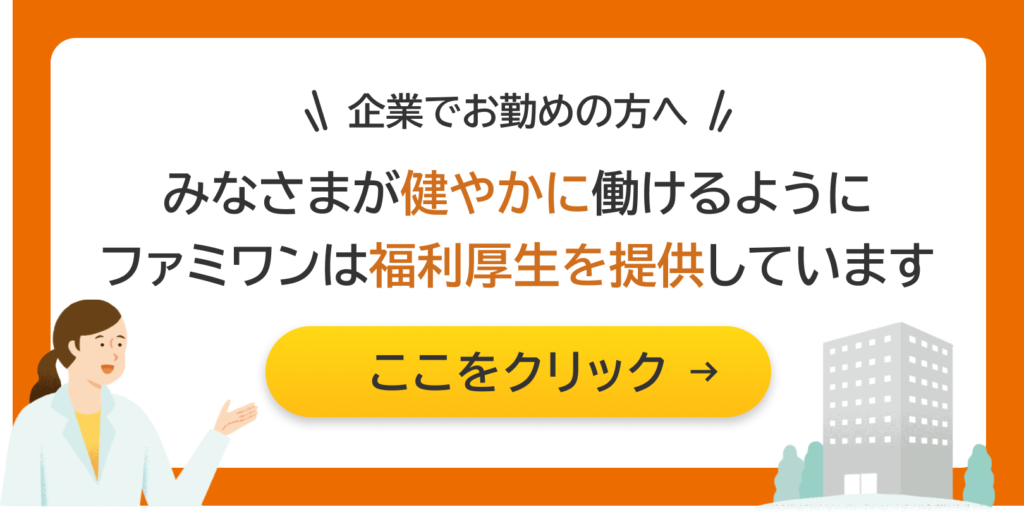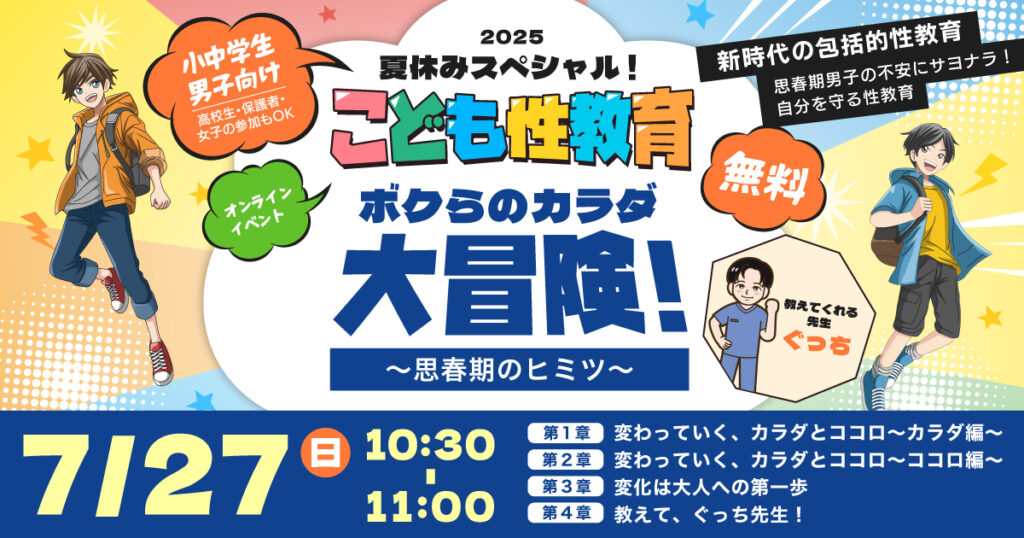子育てしていると必ず頭の中に何度も出てくる言葉
「ああ、今日も怒ってばっかりだったなぁ…」
仕事や家事の中で子どもに逆算して動いてもらうのって、本当に大変ですよね。
早く寝かせたいし、ご飯はなるべく好き嫌いしないでいろんなもの食べてほしい。
手洗いうがいもきちんとして、病気にもならないでほしい。そんな思いがたくさんあるからこそ、思い通りに進まないとどうしてもお母さんの気持ちも余裕がなくなり、怒ってしまう日もありますよね。
私自身、保育士をしてきて現場では同僚や上司から「声掛け上手だね!」なんて言われていました。
実の親からでさえも「あなたは保育士だから大丈夫よ!」と言われる…
これって保育士さんあるあるのようです。だから私もこれから始まる子育てなんて楽勝だ!と大きな誤解をしてきました。
怒りたくないのに怒ってしまう...
ところが、実際に始まった子育てでは、まるで鬼ヶ島の大将鬼のように子どもを怒ってはうまくいかないことだらけで、落ち込んでいました。
怒るだけならまだしも、特に言うことを聞いてくれない日には「鬼がくるよ!」なんて言ったりして、
本当はいけないよな…と反省していました。
優しく落ち着いた声掛けで子どもが気持ちよく行動できたら、それに越したことはありませんが、実際はそううまくいかないのが子育てです。
親になり保育の現場で働く中で「怒りたくないのに怒ってしまう」はお母さんたちの永久の課題であり、悩みであることにも気付きました。
子どもたちが感じていること
なんとか気持ちが軽く、自分を責めず、もっと前向きに子育てをしたいなと私自身が思ったのと、保護者の方にもそんな気持ちで子育てしてほしいな…と深く考えるようになり、現場の子どもたちと関わる際や、我が子との関わりの中で対話をしながら、怒られたことで子どもたちはどんなことを感じているのか探っていきました。
年長児20名ほどのクラスを持っていた時に、なんでもバスケットというゲームをしていてお題を私が出す際に、「お母さんかお父さんに怒られたことがある人!」と聞くとほぼ全員が動き始めました。
ゲーム終了後の振り返りにて、楽しかったことを話しながら
「そういえばさ、さっきほとんどお母さんに怒られたことがある人達だったね!先生(わたし)もついつい子どものこと怒っちゃう時あるけど、みんなお母さんに怒られたらどんな気持ち?」と質問してみました。
すると「嫌な気持ち!」
「僕のお母さんは僕が悪いことをしたら怒るよ!いつもは優しいけど」
「私のことが大事だから怒るって言っていたよ」
などいろんな返答がありました。
「怒られた」という経験の中でもいろいろな感じ方や学びはあるのだなと思ったのをよく覚えています。
その中の一人の女の子に話を聞いてみると、怒った後に必ずお母さんは「怒ってごめんね。だけど困ってほしくないし、お母さんはこう思ったよ」と補足しているような話をしてくれました。
思いの押しつけはよくないですが、自分がどう思ったのかを我が子に伝えるということは必要なことだと学びました。
「怒る前」と「怒った後」をセットにしてみる
私自身はそれまで「怒った」「叱った」という行動に問題を感じ、反省したり自己嫌悪になったりしてきましたが、少しずつ自分なりに気付いてきたのが、“お母さんが怒る前にどんな流れがあったのか” “怒った後はどのようにその出来事を閉じたのか”です。
様々な考えの人がいる中で最近は「怒ることはいけないこと」という風潮になってきています。
私は現場で働いてきた経験や自分の子育てを通して、怒らずに諭して促して、気持ちを汲み取って選択を子どもにゆだねて子育てしていくことが一番理想で良いことだとは思っています。
ただ、それを365日24時間やることってすごく難しいし、実際できている人って少ないと思います。
そこに囚われて、怒ってしまったから“悪いお母さん”ではないし、大事なことは、その出来事から子どもが、親が何を学ぶのかだと思いました。
言葉が通じるようになってきた子は特に、自我もはっきりと出てくるので、親の思うとおりには行動しないことが多いです。
成長の過程を見守り、時には待ったり、思う存分やらせてあげたりすることもあると思いますが、その中で子どもが約束を破ってしまったり、嫌なことをしたときには責任をもって怒ることもあると思います。
怒る前にどんな流れがあったか、怒ってしまった後のフォローはどうしたか、そこまでがセットなのだと感じました。
・だらだら怒らずに、要点だけを短く簡潔に知らせる
・いつまでも引っ張らず、仲直りをして出来事を閉じる など
「怒らない親」になるのではなく、怒っても大丈夫な関係を作る
そして、大事なことは怒らない親になるのではなく、怒っても大丈夫な関係を作るということ。
信頼関係がしっかりと築けているかだということも日々の中で学びました。
普段から会話をしたり、スキンシップをとったりして愛情を伝え合うことで信頼関係は徐々に育まれます。
いくら肯定的な言葉掛けを心がけていても、信頼関係ができていないことには子どもには伝わりません。そして肯定的な言葉をかければいいとだけ思っていても、それは怒らない人になれるというわけではありません。「怒らないことが良いこと」という考えが逆にストレスになってしまうこともあると思います。
逆に「怒らない子育て」ということは、いけないことをしたときや、約束を破ったときにも向き合わないことや、見逃してしまうということとはイコールになりません。
しっかり向き合って大事なことを伝えたいと思った経緯が大切です。
まとめ
お母さんはなんでもこなせるスーパーマンではありません。一人の人間です。
感情的に怒鳴ることや、行き場のなくなるような怒り方はよくないかもしれませんが、お母さんにも気持ちがあることを話すことも大切なのだと思い、我が家でも実践しています。
うまくいかなくて「こらー!」と怒る日もありますが、その日のうちに「大切だから困ってほしくなくて怒っちゃったよ!ごめんね!」と伝えるようにしています。
謝ること、反省することは実は親がお手本となることの大切さにも様々な文献から学びました。
子育ての情報も日々アップデートされています。
美化されている記事やSNSの情報だけにとらわれず、自分が我が子に伝えたいことや、自分の気持ち、感情と向き合いながらありのままで取り組めたらいいな、とママとしても保育士としても思います。