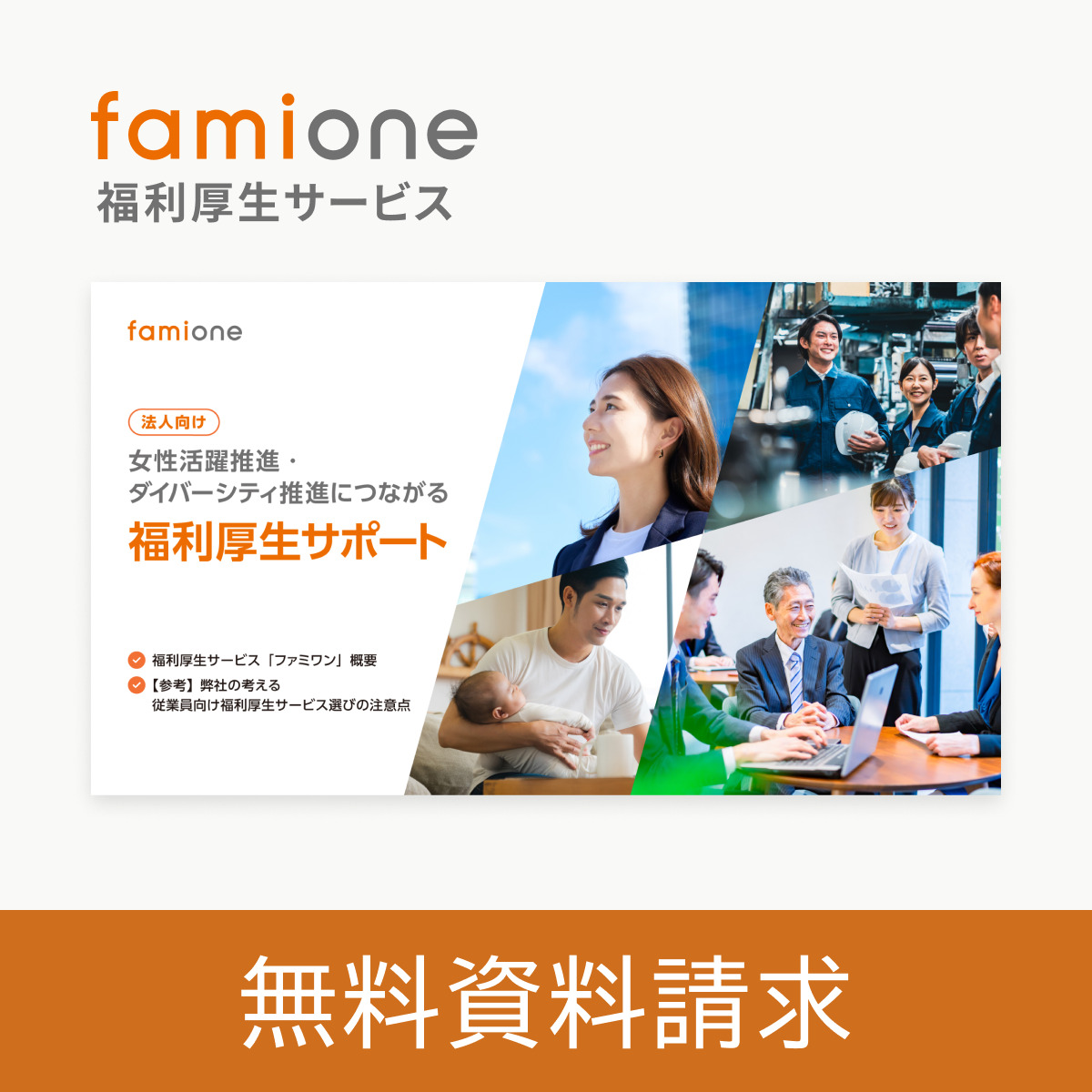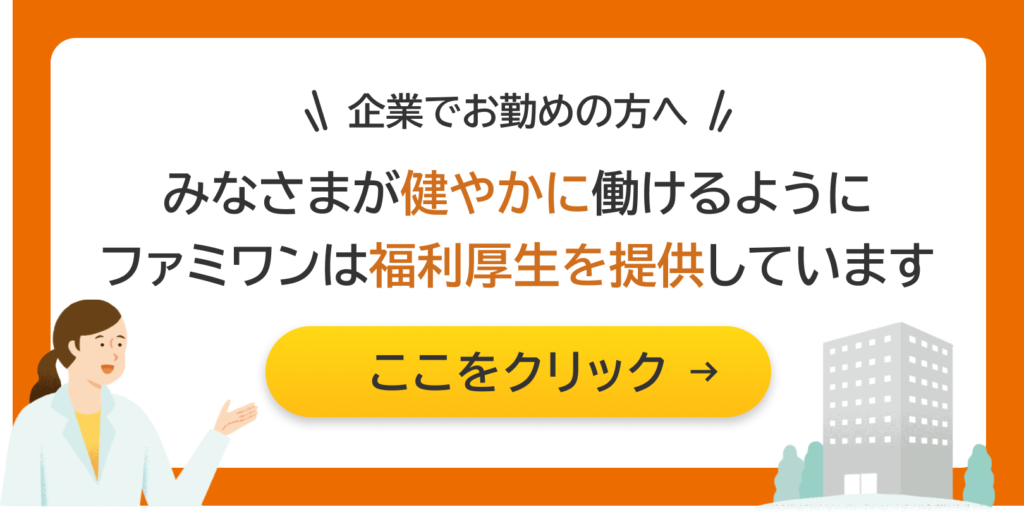はじめに
子どもが指をしゃぶる姿は、多くの保護者が一度は目にしたことがあるでしょう。特に乳幼児期には、眠いときや安心したいときに自然と指を口に運ぶことがよくあります。かわいらしい仕草に見える一方で、「いつまで続くの?」「歯並びや発達に影響は?」と心配になる保護者も少なくありません。本稿では、指しゃぶりの発達的な意味(役割)や長引いた場合の影響、そして無理のない対処法について解説します。
指しゃぶりの発達的な役割
① 自己調整のための行動
指しゃぶりは、生後すぐから見られる自己調整(セルフコントロール)の一つです。赤ちゃんは生まれてまもなく、自分の体を使って安心感を得る方法を自然に学びます。泣いたときや眠いとき、不安なときに指をしゃぶることで気持ちを落ち着け、安心感を得ています。これは大人でいう深呼吸や手を握るようなものです。
② 吸啜反射との関係
新生児期には、口の周りに刺激があると吸う動作をする吸啜(きゅうてつ)反射がみられます。これは母乳やミルクを飲むために欠かせない生理的な反射であり、その延長として指しゃぶりが見られることもあります。生後4〜6か月頃には反射的ではなく、自分の意思で吸うという能動的な行動に変化していきます。
③ 探索と発達の一部
口は、赤ちゃんにとって世界を知るための入り口です。手足や玩具をなめる、指をしゃぶるといった行動は、触覚や味覚を通して周囲の情報を取り入れる感覚統合の発達にもつながります。つまり、指しゃぶりは成長過程で自然に現れる学びの行動でもあるのです。
いつまで続く?発達の目安
一般的には、指しゃぶりは3歳頃までに自然に減少していくことが多いです。これは、言葉や手先の発達が進み、安心を得る方法が多様になるためです。ただし、就寝前や疲れたときに一時的に指をしゃぶる子もおり、それ自体は問題ではありません。4〜5歳を過ぎても頻繁に続く場合は、次のような要因が関係していることがあります。
- ●不安や緊張、環境の変化(入園・引っ越し・きょうだいの誕生など)
- ●愛着の不安定さ
- ●退行現象(成長段階で一時的に赤ちゃん返りをすること)
- ●習慣化による癖
そのため、年齢だけで判断せず、背景にある気持ちや環境を見つめ直すことが大切です。
長期的な影響
① 歯並び・口腔への影響
長期間続く指しゃぶりは、歯や顎の発達に影響を及ぼすことがあります。特に永久歯が生え始める5〜6歳以降も強く吸う習慣がある場合は
- 開咬(上下の前歯の間にすき間ができる)
- 上顎前突(出っ歯)
- 咬合不全(かみ合わせのズレ)
といった問題が生じることがあります。
【開咬(上下の前歯の間にすき間ができる)】

指しゃぶりが続くと、上下の前歯の間にすき間ができ、前歯で噛めなくなってしまいます
公益社団法人 日本小児歯科学会 小児歯科臨床写真
【上顎前突(出っ歯)】

指しゃぶりが続くと、上顎前突になってきます
公益社団法人 日本小児歯科学会 小児歯科臨床写真
ただし、3歳頃までの指しゃぶりであれば、自然にやめた後に歯並びが整うケースも多いです。
② 言語発達や発音への影響
指しゃぶりが長引くと、舌の動きに制限がかかり、サ行・タ行・ラ行などの発音に影響する場合があります。また、口が常に開いている状態が続くと、口呼吸の癖がつくこともあります。
③ 心理的影響
周囲から注意されすぎたり、「やめなさい!」と叱られたりすると、子どもが安心の手段を奪われ、逆に不安が強まることがあります。無理にやめさせるより、心の安心感をどう支えるかを意識することが大切です。
指しゃぶりへの上手な対処法
① 否定せず、気持ちに寄り添う
まずは、「やめなさい」と叱らないことが基本です。指しゃぶりは安心を得るための行動なので、叱ることで不安が増し、逆効果になることがあります。たとえば、「眠たいんだね」「ちょっと寂しいのかな」と言葉で気持ちを代弁してあげるだけでも、子どもは安心します。
② 手を使う遊びを増やす
手先を使う遊び(積み木、粘土、絵を描く、折り紙など)は、自然と指しゃぶりを減らす効果があります。手を動かすことで満足感が得られ、口を使う必要が減るためです。
③ 安心できる環境を整える
子どもがストレスを感じると、無意識に指しゃぶりが再燃することがあります。
- ●スキンシップを増やす
- ●規則正しい生活リズムを整える
- ●家族がゆったり過ごせる雰囲気を作る
こうした安心の土台が、行動の自然な減少につながります。
④ 代替手段を提案する
「眠いときはぬいぐるみをぎゅっとしてみよう」「ママの手を握ろう」など、安心できる別の行動を提案するのも効果的です。ただし、指しゃぶりが強い癖になっている場合は、時間をかけて少しずつ切り替えていくことが大切です。
⑤ 就寝前のルーティンを整える
指しゃぶりが特に寝る前に多い場合は、入眠前のルーティン(絵本を読む、音楽を聴く、抱っこしてトントンするなど)を決めておくと安心感を得やすくなります。眠る前に十分にリラックスできれば、指をしゃぶる必要が減っていきます。
専門的な支援が必要な場合
次のような場合には、小児歯科や小児科など専門機関への相談を検討しましょう。
- ●5〜6歳を過ぎても頻繁に指しゃぶりが続く
- ●歯並びやかみ合わせの異常が見られる
- ●指にタコや傷ができている
- ●強い不安や情緒の問題が背景にある
専門家による口腔チェックや心理的サポートを受けることで、本人に合った対応法を見つけやすくなります。
おわりに
指しゃぶりは甘えや悪い癖ではなく、子どもが自分を落ち着けるための大切な行動です。焦らず、安心できる環境を整えることが何よりの近道です。保護者がやめさせなきゃと過剰に意識すると、子どももプレッシャーを感じてしまいます。「今はそういう時期なんだな」「成長の一過程なんだ」と受け止め、温かく見守りながら少しずつ切り替えていくことが大切です。子どもの発達における自然な行動であり、成長の証でもあります。ただし、長期化して生活や発達に影響が出る場合は、家庭環境の見直しや専門家の支援が必要です。やめさせることを目的にするのではなく、安心と自立を育むサポートを意識して関わることが、健やかな成長への第一歩となるでしょう。
参考文献
・公益社団法人 日本小児歯科学会 小児歯科臨床写真
・日本歯科医師会 口腔習癖(指しゃぶりなど)
・東京都こども医療ガイド 指しゃぶりについての考え方