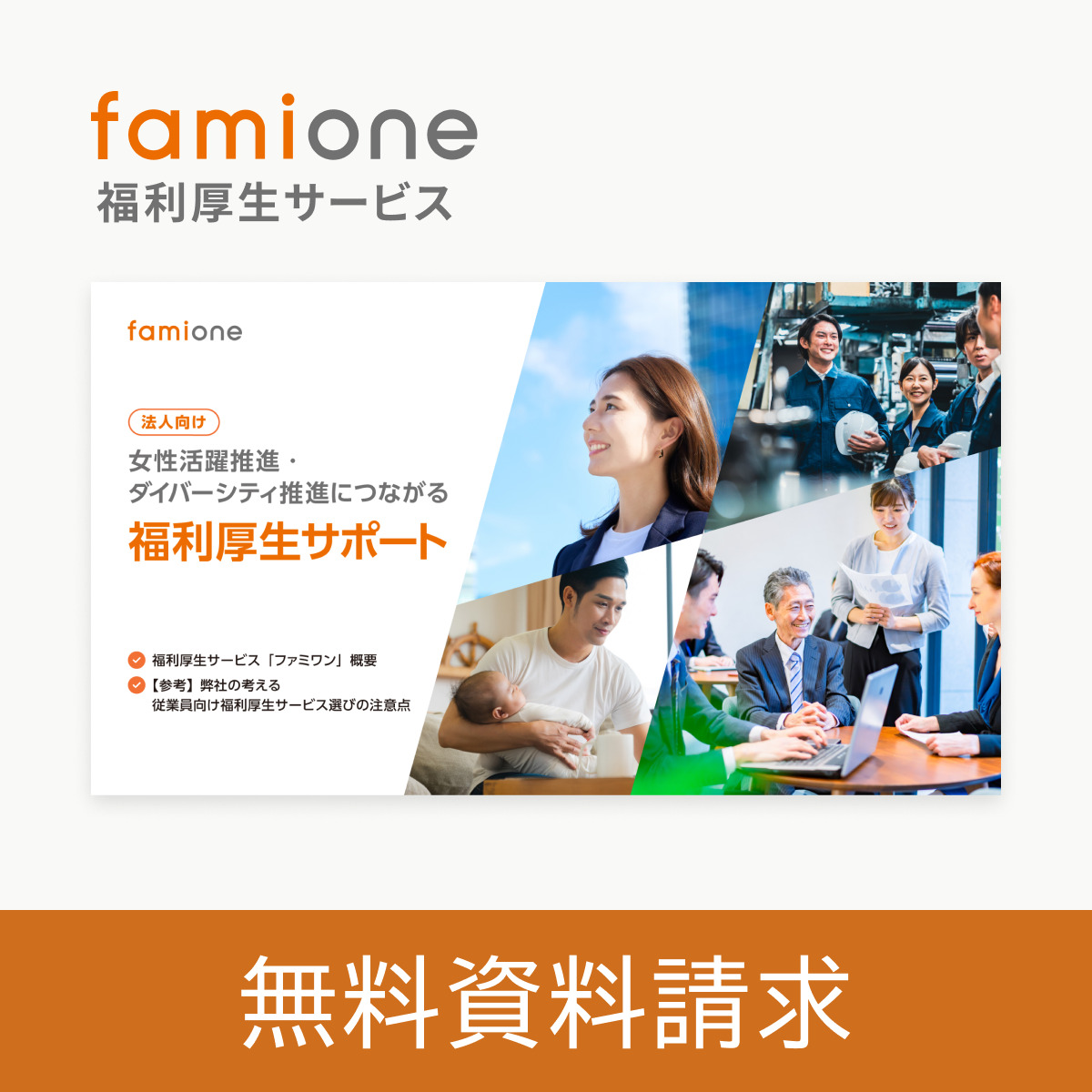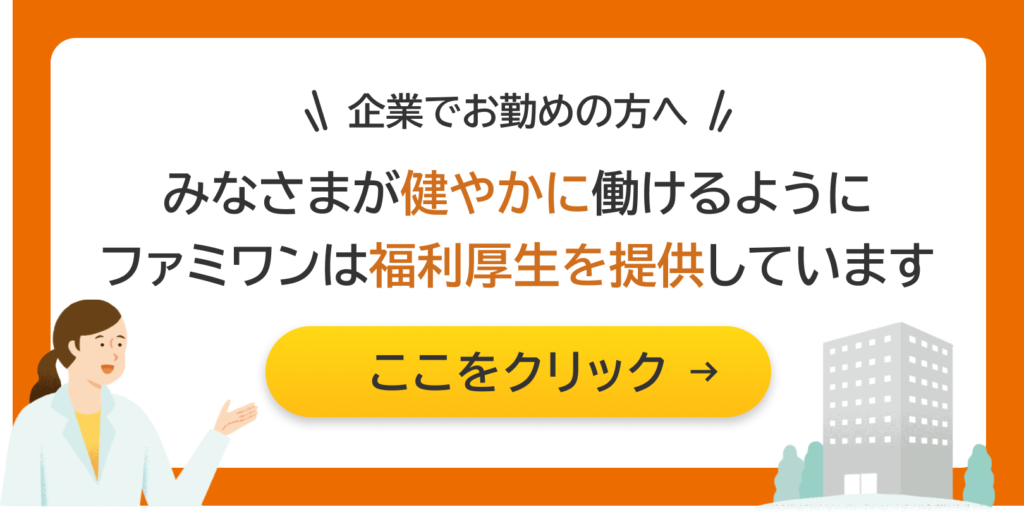更年期は、女性にとって大きな体調変化を伴う重要なライフステージです。閉経に伴いホルモンバランスが変化することで、心身の不調が現れることがあります。これらの症状が日常生活に支障をきたす場合を「更年期障害」と呼びます。今回は、更年期障害に対する薬物療法について詳しく解説し、それぞれの治療法の特徴を紹介します。
更年期障害の症状と原因
一般的に女性の平均的な閉経の年齢は50歳といわれており、閉経前5年と閉経後5年の合計10年間を併せて「更年期」と呼びます。また更年期に現れるさまざまな症状のうち他の病気に伴わないものを「更年期症状」と呼び、その中でも症状が重く日常生活に支障をきたす状態を「更年期障害」と呼びます。若い時は規則的だった月経周期も年齢が高くなるにつれ徐々に不規則になっていきますが、月経が12カ月以上ない状態が続いた場合に1年を振り返って「閉経」と診断されます。更年期障害の原因は加齢に伴い卵巣から分泌される女性ホルモンの一つ「エストロゲン」の分泌が大きくゆらぎながら減少することですが、それに加えて職場や家庭での人間関係や本人の性格も作用し、心身に不調が表れます。
更年期障害の症状は具体的に大きく3つに分けられます。
①血管拡張と放熱に伴う症状:ほてり、のぼせ、ホットフラッシュなど
②身体症状:めまい、動悸、頭痛、肩こり、冷えなど
③精神症状:イライラ、気分の落ち込み、不眠など
更年期障害の薬物療法
更年期障害は身体的・心理的・社会的要因が複合的に関与しているため、まずは医師との十分な問診が大切です。
更年期障害の薬物療法は大きく「漢方薬」「向精神薬」「ホルモン補充療法」の3つに分けられます。先述した通り、更年期障害の原因はエストロゲンの分泌減少ですので、エストロゲンを補う治療法が「ホルモン補充療法」です。また精神的な症状が強い時は漢方薬や抗うつ薬・抗不安薬などの向精神薬が著効する場合もあります。
ホルモン補充療法とは
ホルモン補充療法(HRT=Hormone Replacement Therapy)とは不足しているエストロゲンを必要最低量補う治療法で、更年期を迎えて卵巣の機能が低下し、卵巣から分泌されるエストロゲンの分泌が低下することによって引き起こされる様々な症状や不調を緩和し、更年期以降の健康リスクを予防する方法です。1930年頃より国内外で研究が重ねられてきた治療で、現在では様々なメリットが報告されています。
現在ホルモン補充療法による効能が認められ、保険適用となる症状は以下の通りです。
- ・のぼせ、ほてり、発汗
- ・動悸や知覚異常など自律神経系の不調の改善
- ・性交痛、膣や外陰の粘膜委縮改善
- ・骨粗鬆症による骨量減少を抑える
特にホットフラッシュや性交痛・膣や外陰の粘膜委縮症状の治療には有効で、短期間で効果を実感するという方もいます。また、ホルモン補充療法を行っている方では次のような作用があることも認められています。
- ・気分の落ち込みを和らげる
- ・動脈硬化を抑える
- ・血圧や血糖値の変動を防ぐ
- ・善玉コレステロールを増やし、悪玉コレステロールを減らす
- ・皮膚のコラーゲンを増やし肌の潤いを保つ。
ホルモン補充療法は、「子宮がある女性」と「手術などで摘出し子宮のない女性」で異なります。
子宮のある方の場合、更年期で分泌が低下しているエストロゲンに加えて黄体ホルモン(プロゲステロン)も使用されます。これはエストロゲンのみを長期間使用すると子宮内膜が増殖し、子宮体がんのリスクが高まるため、持続的(もしくは定期的)にプロゲステロンを使用して、子宮内膜の増殖を抑えるもしくは月経のような出血(「消退出血」といいます)を起こし子宮内膜をきれいにするためです。このとき月経が起こるときのような腹痛や下腹部の張り、月経前のようなむくみがみられることがあります。
ただし、経腟エストロゲン製剤については子宮内膜が厚くなるという報告がないためプロゲステロンを使用しなくても問題ありませんが、定期的に病院でエコーを受けると安心です。
一方子宮筋腫などの治療で子宮を全摘出している方の場合は子宮体がんのリスクを考える必要がないため、エストロゲンのみを使用します。この場合月経のような出血は起こりません。
ホルモン補充療法で使う薬には飲み薬・貼り薬・塗り薬といったようにいくつか種類があり、それぞれの特徴は以下の通りです。
飲み薬:
毎日服用する。エストロゲンと黄体ホルモンを両方含むものもある。
貼り薬:
1週間に2回貼り替えるタイプと2日に1回貼り替えるタイプがある。エストロゲンと黄体ホルモンを両方含むものもある
塗り薬:
毎日塗る必要がある。
ホルモン補充療法を始めると初期に不正出血や乳房の張りなどのマイナートラブルが起こる場合がありますが、治療を継続していくとホルモンの成分に体が慣れて徐々に症状は治まっていきます。もし副作用の症状が辛い場合は主治医に相談しましょう。また以前はホルモン補充療法による乳がんリスクの上昇について問題視されていましたが、現在ではホルモン補充療法による乳がんリスクは生活習慣などが原因による乳がんのリスク上昇とほぼ同等もしくはそれ以下ということも分かってきました。ただし日本人の乳がん罹患率は高いため、ホルモン補充療法を受ける・受けないにかかわらず定期的に検診を受けましょう。
ホルモン補充療法は、更年期の女性なら誰でも受けられるというわけではありません。妊娠中・授乳中、重度の肝障害、血栓性の病気、乳がん・子宮体がん、子宮内膜増殖症などの人は受けることができません。また喫煙者やてんかん・高血圧・糖尿病・片頭痛などの既往、60歳以上などの場合はホルモン補充療法を始めるにあたって注意が必要なため医師とよく相談することが大切です。
ホルモン補充療法は婦人科で受けることが可能です。始めるタイミングについて、閉経後10年未満もしくは60歳未満で開始した場合について心筋梗塞発症リスクが減少すること、一方で閉経後10年以上もしくは60歳以上で開始した場合にはその予防効果は消失し脳卒中や血栓症リスクが増加することが分かっています。更年期症状で生活に支障が出ている場合は、なるべく早く治療を開始するほどよいということです。またホルモン補充療法を辞めるタイミングについては決まった年数はなく、治療目的があれば継続することが可能です。ただし継続する場合は少なくとも1年に1回は医師と今後について話し合うようにしましょう。
その他の薬物療法について
更年期障害に対して、ホルモン補充療法以外に漢方薬や向精神薬が用いられることもあります。
漢方薬は自然由来の生薬を組み合わせたもので、カラダ全体のバランスを整えることで症状を緩和する治療法です。ホルモン補充療法と比較して効果が出るまでに時間がかかることが多く、また体質に合ったものを服用していないとなかなか効果を感じにくいですが、1つの漢方薬で複数の症状をカバーしてくれるというメリットがあり、持病でホルモン補充療法を受けられない場合などにも適しています。以下に更年期障害の症状別におすすめの漢方薬を紹介します。
ホットフラッシュや発汗
- 女神散(にょしんさん):ホットフラッシュやのぼせなど、血流の乱れによる症状に対応。
- 知柏地黄丸(ちばくじおうがん):発汗を伴う症状やのぼせ感を和らげます。
冷え、肩こり、むくみ
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):血流を改善し、冷えやむくみに効果的。
- 温経湯(うんけいとう):冷え性に加え、月経不順や肩こりにも有効です。
イライラや気分の不安定
- 加味逍遙散(かみしょうようさん):ストレスや不安感、イライラを軽減。
- 芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん):神経過敏や情緒不安定に効果を発揮します。
不安感や不眠
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):不安感、緊張感を和らげ、眠りの質を改善します。
- 帰脾湯(きひとう):精神的な疲れや不安、不眠に効果的です。
疲労感や倦怠感
- 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう):体力が低下しやすい方や病後の回復に。
- 人参養栄湯(にんじんようえいとう):慢性的な倦怠感や食欲不振を改善します。
漢方薬はドラッグストアなどで手軽に購入することもできますが、自分の体質に合ったものを服用してこそ効果を実感できるものであり、自己判断で複数の漢方薬を併用すると副作用が起こる可能性もあります。更年期障害に対して漢方薬を試す場合はまずは単品で服用することとし、またできるだけ産婦人科や漢方薬局などで体調について相談するとより体調改善の近道になりますよ。
また気分の落ち込みやイライラなどの精神症状に対しては抗うつ薬や抗不安薬などが使われることもあります。比較的新しい抗うつ薬は副作用も少なく、ほてりや発汗など血管の拡張と放熱に関係する症状にも効果があるという報告もあります。ただしホルモン補充療法と比較すると、服用初期に軽い副作用(眠気、消化不良など)がみられることや、エストロゲンの補充とはなっていないため骨折リスクが上昇したという報告もあるため注意が必要です。
まとめ
更年期障害は多くの女性が経験するものですが、適切な治療を受けることで日常生活への影響を軽減し、快適な生活を取り戻すことができます。医師との相談を通じて自分に合った治療法を見つけ、健康的な更年期を過ごしましょう。
[参考文献]
・日本産婦人科学会「更年期障害」
https://www.jsog.or.jp/citizen/5717
・あすか製薬「ホルモン補充療法とは」
https://www.aska-pharma.co.jp/general/menopause/hrt.html
・公益社団法人女性の健康とメノポーズ協会「ホルモン補充療法」
https://www.meno-sg.net/hormone/formulation/206/