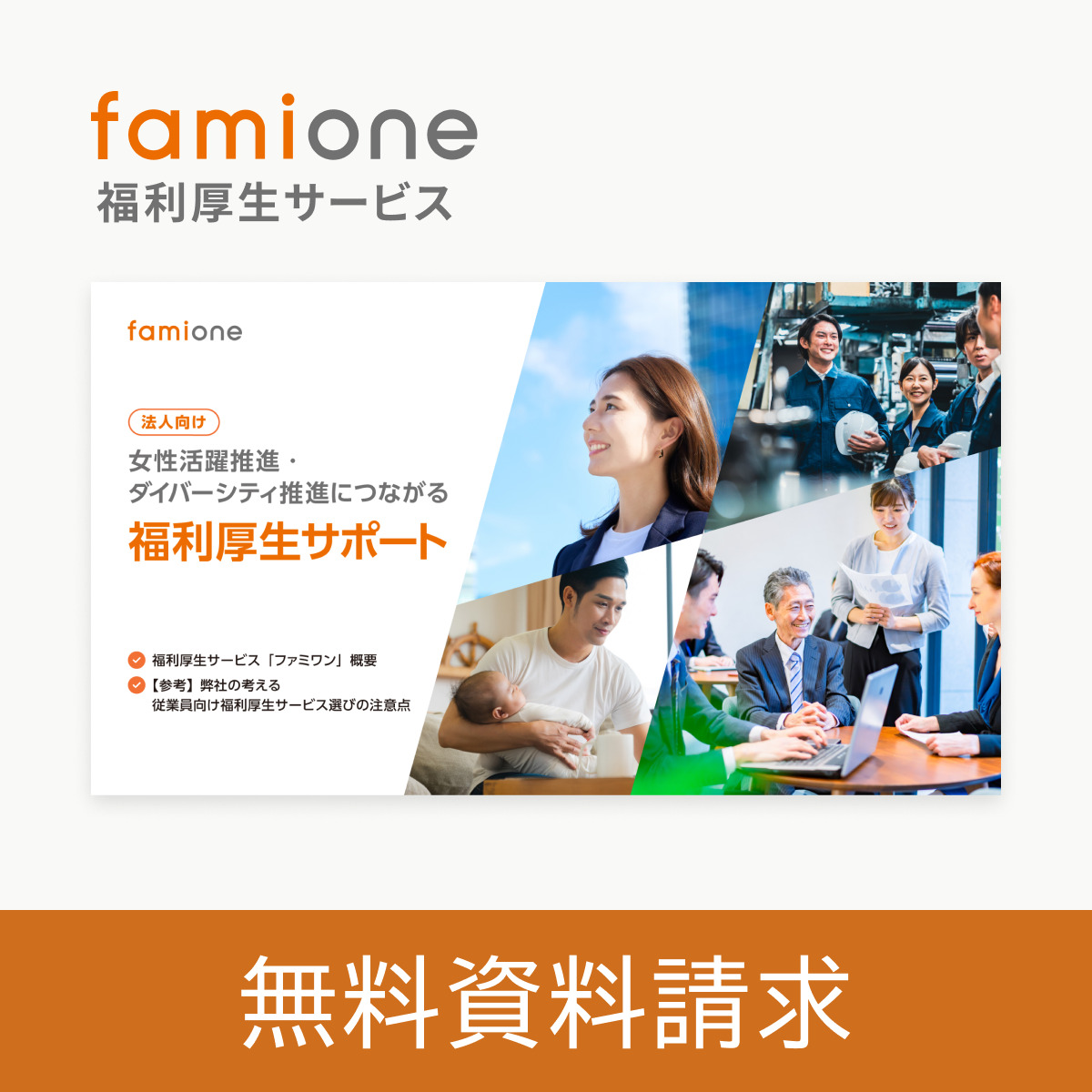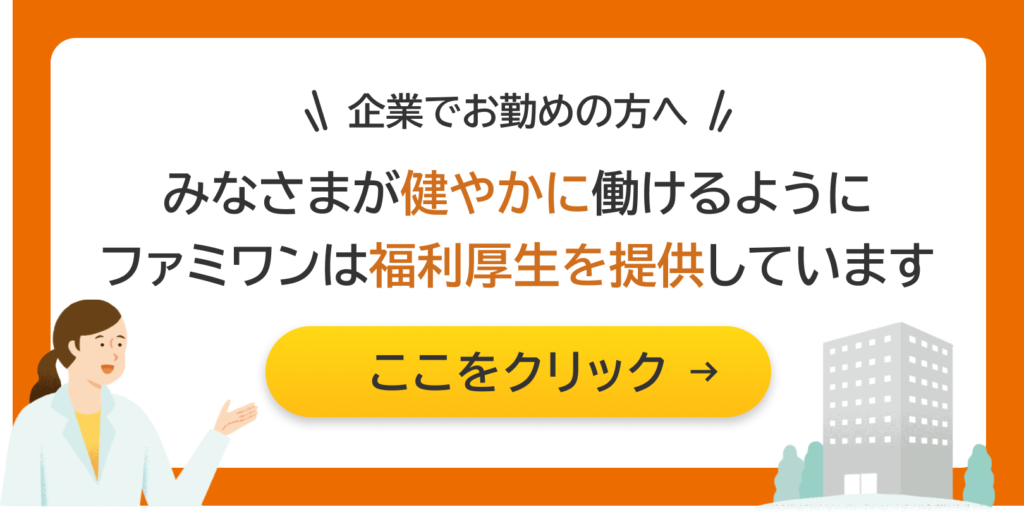皆さんこんにちは。胚培養士の川口 優太郎です。
とにかく毎日暑くて暑くて‥‥、むしろ“暑い”というよりも“熱い”日々が続いていますが、皆さんは体調などは崩されていませんでしょうか?
東京都心では、2025年8月27日の時点で最高気温が35.0度を超えて猛暑日となったため、観測史上、猛暑日の連続日数記録・年間日数記録ともに新記録となったそうです。実のところ、すでに一昨年、昨年と2年連続で今までの観測値からは考えられないほどの記録的な暑さを更新しており、今年は過去2年の記録をさらに塗り替える数値となっています。
毎日これだけ暑いと、ちょっと歩いただけで汗もダラダラ止まらないし、食欲も全然湧かないし、痩せてしまうのではないか?と考える方も多いのではないかと思いますが、実は『夏は太りやすい』という傾向があることをご存知でしょうか?
今回のコラムでは、『肥満と不妊』の関係について、最新の研究論文や海外の事例をご紹介していきたいと思います。
実は、夏は太りやすい!
そもそも夏が太りやすいと言われる主な原因には、などがあるとされており、これらの要因が組み合わさることで太りやすくなってしまうのではないか?と考えられています。
基礎代謝の低下
人間の脳には、体内の温度や、皮膚にある温度受容器からの情報を受け取り、体温を一定に保つようにコントロールする機能があります。気温が高いと、体温を上昇させる機能を使わなくなるため基礎代謝が落ちてしまいます。
自律神経の乱れ
冷たい飲み物やかき氷、アイスなどを摂取する機会や、食欲の低下から、そうめんばかり食べるなどの偏った食事習慣、エアコンによる冷えすぎや、外気温と室内温度の温度差などによって自律神経が乱れてしまいます。
活動量の低下
連日、猛暑日が続くことで外出や運動を控えるようになると、相対的に一日の活動量(エネルギー消費量)が著しく低下してしまいます。
などがあるとされており、これらの要因が組み合わさることで太りやすくなってしまうのではないか?と考えられています。
まだまだ猛暑が続く現代においては、太りやすい時期が続いてしまう可能性が高いです。そして、実は体重の増加(肥満)と不妊症は密接に関係していることが知られており、肥満が不妊の直接的な原因になるということが数多くの学術的な研究論文でも報告されているのです。
妊活・不妊治療を開始する前の取り組みが必要
2025年8月に、イギリスで権威ある医学雑誌のひとつであるAnnals of Medicineに掲載された論文では、『肥満と診断されている女性が妊活や不妊治療をスタートする場合、開始前に減量サポートプログラムに参加した女性と、減量サポートをほとんどまたは全く受けていない女性とを比較すると、プログラムに参加した女性では自然に妊娠する可能性が約47%高い』という研究結果を報告しています。
この研究は、イギリスのオックスフォード大学が主導し、国立医療研究所の研究助成資金を受ける形で行われ、約2,000人の女性を対象として12種類の国際的な規格に基づいた検査結果を分析しました。
栄養指導のほか、運動習慣の改善、オルリスタット(肥満治療薬の一種)、オゼンピックやウゴービ(2型糖尿病治療薬)などを含むGLP-1作動薬などの減量薬、といった減量を目的とした処置・処方の介入から得られた幅広いエビデンスを統合し、減量サポートプログラムを実施したケースと、ほとんどまたは全く受けていないケースでの妊娠率を比較検討しました。
減量サポートプログラムの介入を受けたグループの女性は、受けていないグループの女性と比較して、平均4.0kgの減量をしました。
イギリスでは肥満女性は治療費用の助成を受けることが出来ない
イギリスでは、不妊治療を受ける場合、一般的には英国国民保険サービス(NHS; National Health Service)の助成制度を利用して資金提供を受けることができますが、肥満度を示すBMI; Body Mass Indexの値が30.0を超える女性やその他生活習慣病などに起因する疾患が認められる場合になどには、NHSによる助成制度の対象外となってしまい、治療にかかる資金提供を受けることが出来ません。
論文著者である、オックスフォード大学のMoscho Michalopoulou博士は「本研究は、NHSが肥満女性をIVF助成制度の支援対象から除外する理由を裏付けるものである」と述べるとともに、「現在、肥満女性の多くは妊娠率の低さ(不妊率の高さ)とNHSによる助成制度から除外されるという二重の課題に直面している。我々の研究結果は、体系的な減量サポートプログラムを提供することで妊娠の可能性を高め、減量によって不妊治療へのアクセスの公平性を高めることで、より多くの女性がNHS資金による治療を受けられる機会を増やすことを示唆している」と著書の中で語っています。
赤ちゃんへの影響はより慎重に検討する必要がある
この研究では、
- 対象となった肥満女性のうち、低エネルギー食への食事代替プログラムを行った女性において生産率が最も増加したこと
- 減量サポートプログラムを介した場合、不妊治療・生殖医療による妊娠率は約21%上昇すること(※ただし、高度生殖医療(IVF)のみの影響は不明)
- 一方で、肥満と不妊の両方に関連する多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)に既往のある女性では、減量サポートプログラムの恩恵が少なかったこと
など、複数の項目について新たに明らかとなったことが報告されており、論文の中で「本研究は、肥満女性への減量サポートプログラムと妊娠に対する利点について、これまでで最も明確な見解を提供した研究の一つである」と述べられています。
その一方で、研究チームの責任者で、本研究を率いたオックスフォード大学Nerys Astbury准教授は、妊活・不妊治療の最終的な目標である、産まれてくる児への影響は「未だ不明瞭である」と強調しています。
これまでに報告されている数多くの研究論文において、肥満と妊娠については、妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群、胎児の先天性奇形、心臓疾患、神経管欠損、流産・早産・死産、乳児死亡などのリスクが顕著に増大することが知られています。
しかしながら、出生後の児の健康状態に関する情報について、妊娠する前、妊娠中、出産時、出産後の母体の経過・状態や、妊娠中の胎児、産後の児の健康状態までを網羅的に追跡できている症例が非常に少なく、出生率や児の健康状態に与える影響を調査するためには、より大規模で質の高い試験を行い調査を行う必要があるとしています。
妊娠の可能性を最大限に高めるために
肥満、または肥満のなりやすさについては、特定の遺伝子の発現や遺伝子の変異が関わっているということが多くの研究論文により指摘されていますが、家庭の経済的な理由や民族的な背景によっても肥満のリスクを抱えて生活する人が数多くいることが示されています。
妊娠する前の準備として、減量サポートプログラムを取り入れることは、自然妊娠の可能性や、不妊治療の妊娠率を向上させるだけでなく、妊娠・出産までの期間の短縮や、全体的なコストの削減につながる可能性があります。
妊娠にはタイムリミットがあるため、赤ちゃんの誕生を望まれるご夫婦にとっては、毎周期が時間との戦いでもあります。
安全で、衛生的で、健康的な妊娠を目指すためにも、自身の健康状態を把握し、体重をコントロールすることは、妊娠の期待値を最大限に高める極めて効率的で高いエビデンスに基づいた方法になり得る可能性があります。
まとめ
今回のコラムでは、実は夏は太りやすいということ、そして肥満と不妊の関係性について解説してきました。
これだけ毎日のように猛暑が続くと、外に出るのが億劫になってしまったり、運動や食事の習慣に偏りが出てしまったりすることも多いかもしれません。しかしながら、妊娠という目標を達成するためには、自身だけでなくご夫婦がともに健康であることがとても重要です。そして、この考え方は、ファミワンが推奨している“プレコンセプションケア(妊娠する前の健康管理)”にもつながります。
未来のパートナー・未来の自分のために|男性にも必要なプレコンセプションケアとは?
薬剤師に聞く!プレコンセプションケアとしてのワクチン|未来を守る予防の選択
将来的に、今回のコラムで取り上げた研究のような知見が積み重なっていくことで『妊娠のため、あるいは不妊治療を行うためには、まずは減量をしましょう!』というキャンペーンが、より身近なものになるのかもしれません。
安全で、衛生的で、健康的な妊娠のために、体重コントロールの重要性をしっかりと理解し、ご夫婦で一緒に生活習慣の改善に取り組むようにしましょう。
参考文献
- オックスフォード大学ニュース
- イギリス保健社会福祉省;イングランドにおけるNHS資金による体外受精
- The Effect of Weight Loss Before In Vitro Fertilization on Reproductive Outcomes in Women With Obesity: A Systematic Review and Meta-analysis, Annals of Internal Medicine,
Reviews 12 August 2025, Moscho Michalopoulou, Nerys Marie Astbury, et al. https://orcid.org/0000-0001-9301-7458
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/ANNALS-24-01025
- Overweight, obesity and assisted reproduction: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2022;271:117-127. Ribeiro LM, Sasaki LMP, Silva AA, et al.
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301211522000276