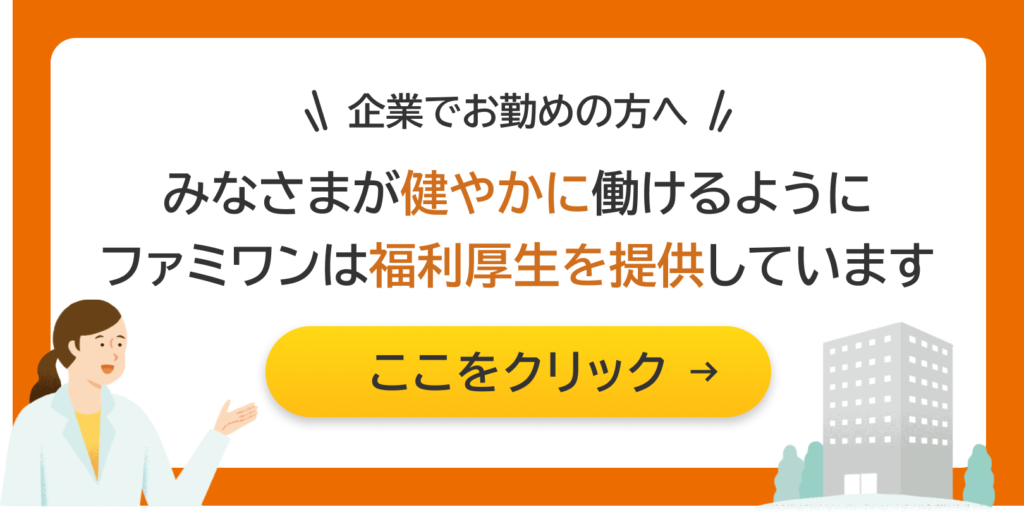みなさんは「死産」という言葉を聞いたことがありますか。
少し重たい印象を持つ方もいるかもしれません。けれど、妊娠や出産をめぐる現実の中で、実は決して珍しいことではありません。
医療の現場では、妊娠22週以降にお腹の中で赤ちゃんの心臓が止まってしまうことを「死産」といいます。
日本では、1,000件の出産のうち数件の割合で赤ちゃんの命が途中で途切れることがあります。定義の違いによって数値は変わりますが、世界的に見ても珍しいことではありません。
それでも、日常の中で「死産」について考える機会は多くありません。
話題にするのが難しく、どこか「触れてはいけないこと」のように扱われることもあります。
でも、誰にでも起こりうることだからこそ、「知っておく」「考えてみる」ことには意味があるのではないでしょうか。
死産を考えることは、「特別な誰かの話」ではなく、誰にとってもそばにある「いのちの話」を考えることかもしれません。
「誕生死」という言葉
2002年に出版された『誕生死』(三省堂)という本があります。
流産・死産・新生児死で子どもを亡くした親たちが、実名で体験をつづった書籍です。
そのタイトルに使われた「誕生死(たんじょうし)」という言葉は、医学用語ではありませんが、 本の制作時に考案された造語で、その後、産科医や助産師たちが現場で紹介し、広く知られるようになりました。
“誕生”と“死”という相反する言葉をつなげたこの言葉には、深い意味を感じます。
生まれることと死ぬことは、本来、遠く離れた出来事ではない。
いのちは始まりと終わりを行き来しながら、ひとつの流れの中に存在している。そんなことを考えさせられますね。
「生まれる」と「死ぬ」のあいだ
医療の発達によって、赤ちゃんが無事に生まれる確率はとても高くなりました。
だからこそ、命が途中で途切れることを「想定外」と感じる人も多いのかもしれません。
けれど、生まれることも死ぬことも、いのちの営みの一部です。
お腹の中で命を終えた赤ちゃんも、確かに“生まれた”存在です。
そのことを「誕生死」という言葉が、静かに教えてくれるような気がします。
死産を経験するということ
死産の知らせは、多くの場合、突然やってきます。
診察室で「心拍が確認できません」と告げられても、すぐには理解が追いつかない。
涙が止まらない人もいれば、ただ時間が止まったように感じる人もいます。
反応の仕方は人それぞれで、どれも自然なことです。
その後に行われる出産は、通常の出産と同じように陣痛を経て行われます。
赤ちゃんを抱く、写真を撮る、名前をつける、手形を残す、手紙を書く……。
「抱いてよかった」「つらくて抱けなかった」「想像のままの姿でいてほしかった」。
どれも、その人がそのとき精一杯に出した答えです。
どんな形であっても、それは確かに「誕生」ではないでしょうか。
体は出産を経ています。ホルモンの変化や母乳の分泌など、心と体のリズムが合わないこともあります。
そんなときは、我慢せず、医療者に頼ってください。体を整えることは、心を軽んじることではありません。
そして伝えたいのは、死産は誰かのせいではないということ。
お母さんのせいでも、家族のせいでも、誰かの行動の結果でもありません。多くの死産は、医学的にも原因を特定できず、防ぐことも難しいものです。
それでも、悲しみは確かにそこにあり、その痛みと共に生きていく時間が始まります。
そばにいるということ
死産を経験したご家族の悲しみは深く、その痛みは時間がたっても完全に消えることはありません。けれど、その悲しみと共に生きていくようになります。
まわりの人にできるのは、特別な言葉をかけることではなく、「そばにいること」。
ただ一緒にいて、話を聴くこと。沈黙の時間も、確かな支えになると思います。
そして、「そばにいる」というのは、人と人の関係だけを指す言葉ではないような気がします。
悲しみそのものが、これからの人生のそばにいる。
生きることと死ぬことは、まったく別の出来事のようでいて、どちらも同じいのちの流れの中にあります。私たちはその境い目のような場所で、日々を生きているのかもしれません。
また、社会の中で「死産」を話題にできる空気を少しずつ増やしていくことも大切です。
それは、経験した人を励ますだけでなく、「生まれる」「生きる」「死ぬ」といういのちの流れを、みんなで考えるきっかけになります。
いのちの存在を見つめてみる
死産という出来事は、悲しみの中にあるご家族だけでなく、妊娠や出産に関わるすべての人にとって、深い問いを投げかけます。
「生まれる」とは何か、「生きる」とは何か、そして「死ぬ」とはどういうことなのか。
どれも遠い話ではなく、私たちのすぐそばにあることを思い出させてくれます。
お腹の中で亡くなった赤ちゃんも、確かに“生まれた”存在です。そしてその小さないのちは、ご家族の心の中でこれからも生き続けていきます。
悲しみは時間とともに消えるものではありませんが、少しずつ形を変え、穏やかな思い出や祈りとなって寄り添ってくれるようになることもあるかもしれません。
死産について語ることは、いのちを語ることでもあります。
生きることと、失うこと ー その両方を抱えながら、私たちは日々を過ごしています。
この現実を悲しみだけで終わらせるのではなく、赤ちゃんが確かに存在したことを静かに見つめ続けていくこと。
それが、いのちを語る上で大切なことのひとつかもしれません。
参考
誕生死 流産死産新生児死で子をなくした親の会(著)2002年