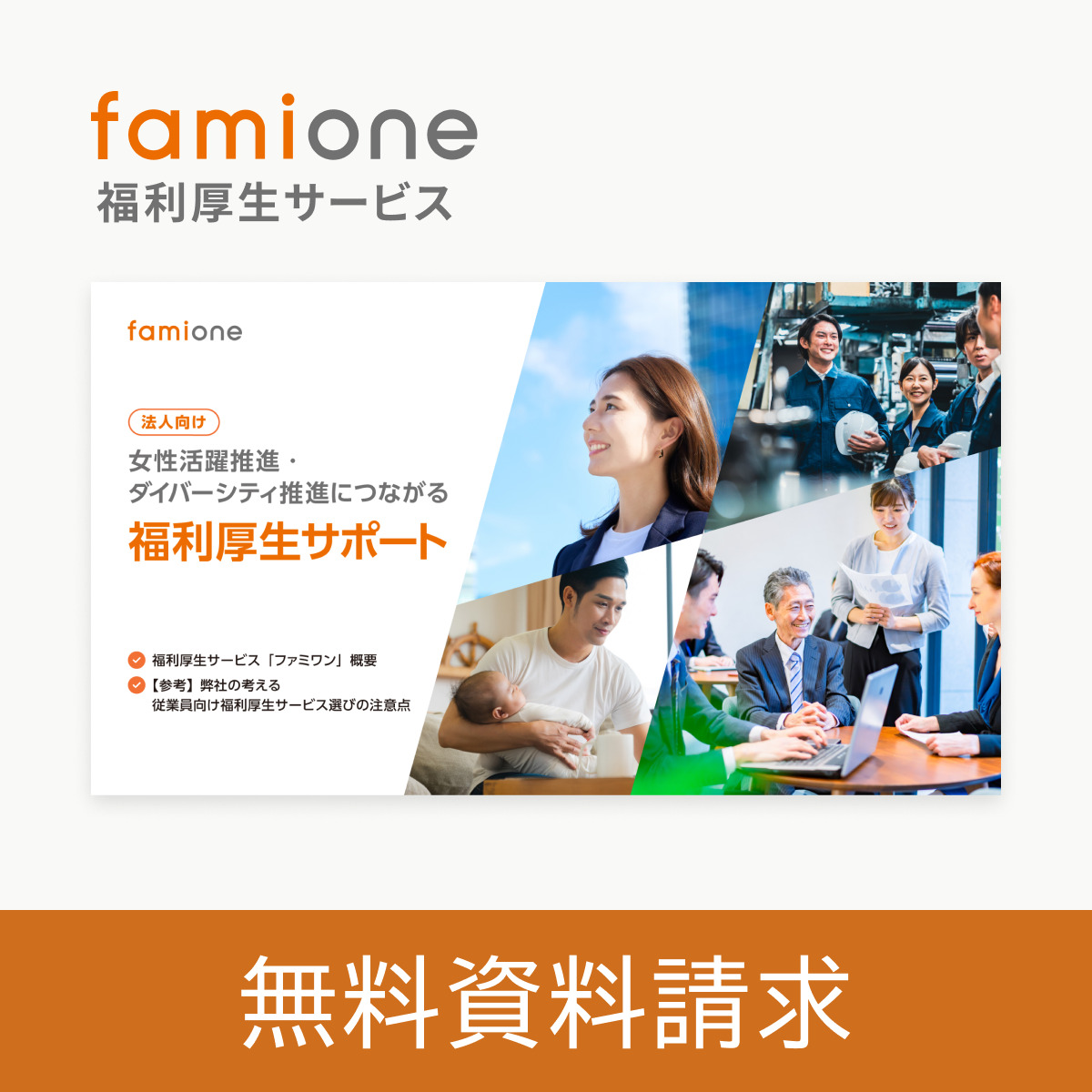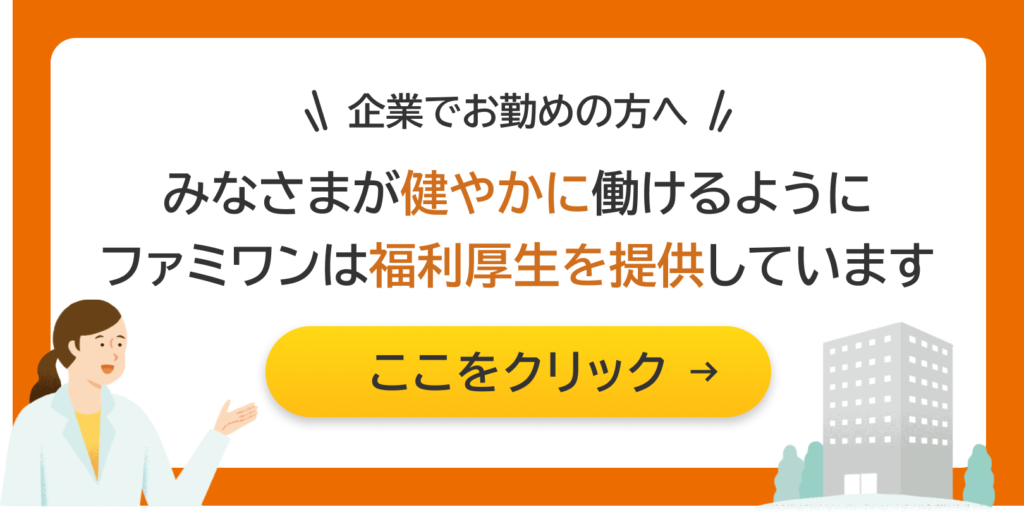管理栄養士の山本です。春になると、毎年お花見が楽しみという方が多いのではないでしょうか。美しい桜を眺めながら食べるお弁当は格別です。
今回は、お花見弁当のレシピや詰め方のポイントなどをご紹介いたします。満開の桜に似合う華やかなお弁当を作って、春のイベントを楽しみましょう
お花見弁当レシピ
お花見弁当には、春を思わせる彩りや春らしい食材がおすすめです。ふたを開けたときにワクワクするようなお花見弁当のレシピをご紹介いたします。
塩こうじ唐揚げ
冷めてもやわらかいので、お弁当にもおすすめです。

材料:
鶏もも肉:2枚
(A)塩麹:大さじ1と1/2
(A)酒:大さじ1
(A)しょうゆ:小さじ2
(A)にんにく、しょうが(すりおろし):各1片分
薄力粉:大さじ2
片栗粉:適量(目安大さじ6)
揚げ油:適量
【1】鶏もも肉は一口大に切り、(A)と合わせてジッパー付き保存袋にいれて揉み込み、30分以上(できれば一晩)おく。
【2】保存袋に薄力粉を加えて揉み込む。バットに片栗粉を入れ、鶏肉にまぶす。
【3】揚げ油を170度に熱し、5分揚げる。
鮮やか!三色卵焼き

材料:
卵2個
かにかま 6本
小葱 10g
砂糖 小さじ1
サラダ油 大さじ 1と1/2
作り方
【1】ボウルに卵を溶き、かにかまをほぐしていれ、小口きりにした小葱、砂糖を加える。
【2】卵焼き用フライパンに油をひき、フライパンが温まったら1/3量をいれ、奥から手前に巻いていく。残り2回も同様におこない形を整える。
【3】全体にふんわり焼き色がついたら火からおろす。
華やかいなり寿司

材料:
味付けいなりの皮(市販) 6枚
酢飯 180g(1個30g位)
卵 2個
砂糖 小さじ2
鮭フレーク 60g
大葉 3枚
作り方
【1】卵は砂糖を加え炒り卵にする。
【2】いなりの皮に酢飯を詰め、逆さまにし具材を飾る。
炒り卵、鮭フレーク、千切りにした大葉を飾る。
お花見弁当の詰めかたのポイント
お花見弁当は、詰め方にもこだわりましょう。きれいに詰めると華やかなお弁当になり、目でも楽しめます。みんなで食べやすいように、取りやすさも考えて詰めましょう。
色合いを考える
子どもに人気のおかずを詰めると、唐揚げやハンバーグなど茶色なものばかりになりがちです。春の華やかさが感じられる色合いになるよう、お花見弁当には3色以上使うようにしてはいかがでしょうか。春らしい色の食材には次のようなものがあります。
ピンク…桜の塩漬け、桜でんぶ、ハム
緑…菜の花、枝豆、グリーンピース、アスパラガス、ブロッコリー
黄…卵、パプリカ、さつまいも、かぼちゃ
お弁当箱に詰めるときは、同じ色が隣り合わないように工夫すると彩りがよくなります。
ピックを指しておく
一口サイズのおかずは、ピックをさしておくのもおすすめです。箸を使わずにそのまま片手で食べられるので、みんなでお弁当を囲むときも気軽につまみやすいでしょう。
おかずをカップに入れておく
取り分けにくいおかずは、1人分ずつカップに入れておくと扱いやすくなります。お弁当用のカップにはさまざまな大きさや深さのものがありますので、おかずに合わせて選びましょう。
お花見弁当の注意点
前日から下準備する
お花見弁当を作るのは時間がかかるため、できるだけ前日から下準備しておきましょう。下準備ができていれば、当日の朝は「焼くだけ」「揚げるだけ」で済むのでスムーズです。前日に用意できるおかずは作っておき、当日は温め直すだけにしておけば、お弁当作りにかかる時間をずいぶん短縮できます。
汁気のあるものは避ける
汁気のあるものは他のおかずに味が混ざったり、汁がもれ出たりする場合があります。加えて水分の多いものは細菌が増えて傷みやすいというデメリットもあるため、できるだけ避けた方がよいでしょう。入れる場合は、しっかりと汁気を切ってください。
トマトもヘタをとることで、雑菌の繁殖を防ぎます。
さいごに
お花見弁当は、おいしさだけでなく彩りの美しさまで考えて作ると華やかになります。みんなで取り分けて食べる場合は、食べやすさも考えて詰めるとよいでしょう。
桜の塩漬けや菜の花、たけのこなど、春を感じさせる食材を使うと、よりお花見を満喫できます。満開の桜が楽しめる時期には、ぜひお花見弁当を持って桜の季節を堪能してください。