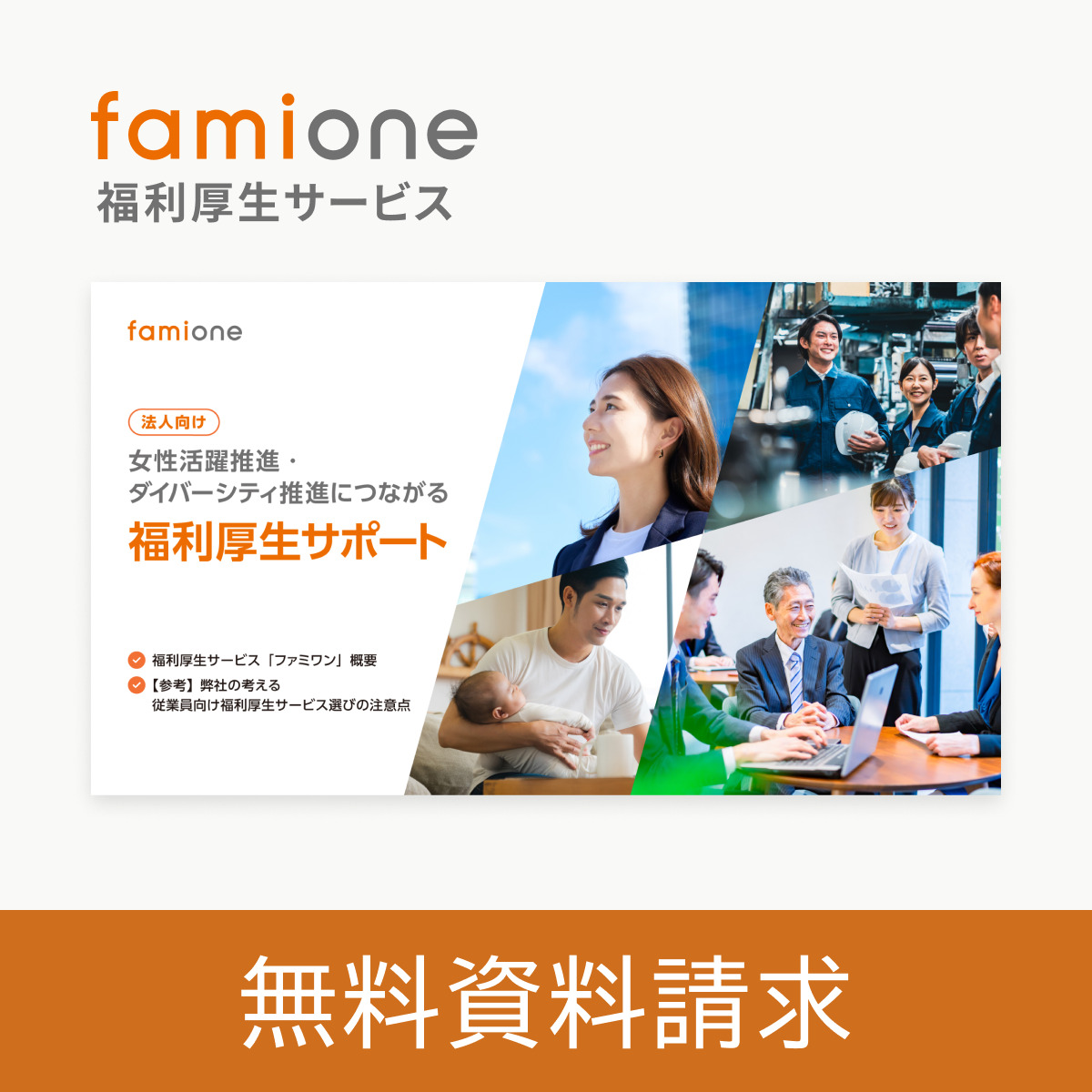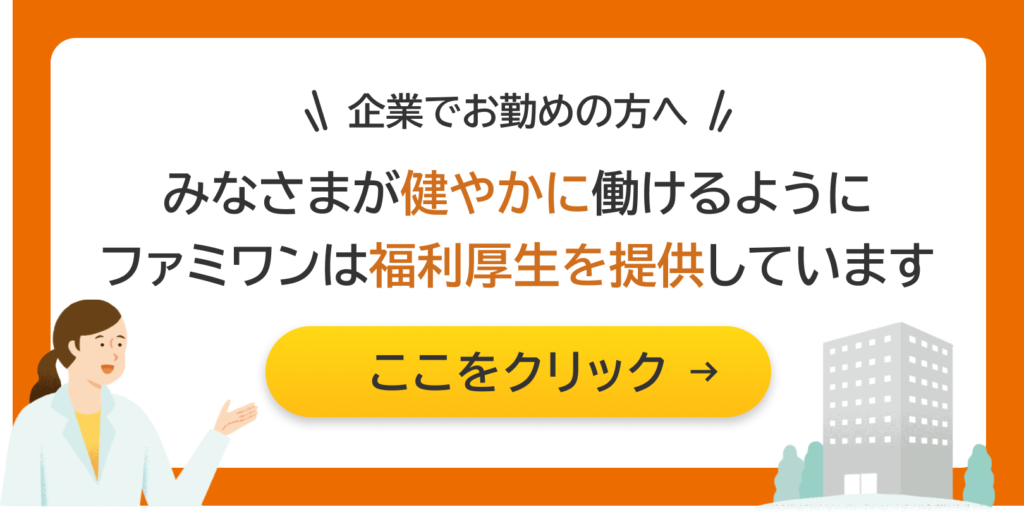はじめに
皆さんこんにちは。胚培養士の川口 優太郎です。
先日、【肥満と不妊は密接に関係している|生活習慣の改善と体重コントロールの重要性】というコラムを書かせていただきました。
このコラムは、主に女性の肥満と体重コントロールの重要性についての内容でしたが、実は不妊症と肥満の関連性は、男性においても同様の知見が数多くあることをご存知でしょうか?
今回は、男性の肥満と生殖能力に与える影響について、いくつかの研究論文を紹介し、詳しく解説をしていきたいと思います。
不妊原因の約半数は男性側が関わっている
妊活・不妊治療を続けていてもなかなか妊娠に至らない場合、女性側の要因ばかりが疑われるケースは臨床でもよくあります。しかしながら、実際のところ男性側が不妊症の要因となる症例も数多くあり、日本生殖医学会のデータでは、全体の約35~45%のケースに男性側が関わっていることが示されています。
男性不妊の主な要因としては、精子濃度(数)の異常、運動性の異常、精子の形態的な異常、テストステロン値の低下、性機能障害(勃起不全)などが挙げられます。
また、反復性流産症例や反復性ART不成功症例のケースでは、いわゆる精子の“質”を評価する項目である、精子DNA断片化が原因であるとする学術的にも信用性の高いエビデンスが多くあるにもかかわらず、依然として女性側に焦点を当てた検査や処置が優先的に選択される傾向があります。
男性の生殖能力は、生活習慣による影響を受けることが知られており、特に、今回のコラムで取り上げる“肥満”に関連する食事習慣・運動習慣・喫煙・飲酒といった習慣のほか、睡眠・ストレスなどのライフスタイルが精液データの低下と相関を示すといった学術的な研究報告は、年々増加しています。
肥満の男性では不妊症リスクが増加する
最初にご紹介する研究は、オーストラリア・アデレード大学のJared M Campbell博士のチームが発表している論文で、
(1) 男性側に肥満が認められる場合、不妊症のリスクが増加する
(2) 高度生殖医療における1周期当たりの生児出産率が有意に低下する
ことを明らかにしています。
この研究は、Reproductive BioMedicine Online | Journalに掲載された論文で、過去に行われた30件以上の論文、対象者総数は115,158名について不妊症のリスク、臨床的妊娠率、生児出産率、乳児の発育、精液データ、精子DNA断片化などを調査しました。
その結果、肥満男性では標準体重の男性と比較して不妊症リスクが10%以上高く、従来の精液検査項目(精子濃度や運動率など)には大きな差は認められなかったものの、精子DNA断片化、形態異常の割合、酸化ストレス値において有意に悪い影響を受けていることが示されました。
その原因の一つとして、Jared M Campbell博士は「精巣(陰嚢)付近の脂肪の増加は、精巣温度の上昇を引き起こし、造精機能と精液データに悪影響を及ぼす可能性が非常に高い」と述べ、「加えて、肥満はホルモン分泌とその結合タンパクに障害を起こし、正常な精子の生成を阻害する可能性もある」と指摘しています。
先述の通り、精子DNA断片化は妊娠継続率や流産とも深く関連しており、論文の中では、適切な減量治療の介入が行われた場合には、このような精液のパラメータに明確な改善が見られたことから、適正体重への減量によって妊娠の期待値も大きくなるのではないか、と考察しています。
肥満男性は体重を適正に近づけるほど妊娠の可能性が高くなる
次にご紹介するのは、カナダ・シャーブルック大学のJean-Patrice Baillargeon博士のチームが発表した研究で、
(1) 男性の肥満が不妊症の原因になること
(2) 肥満男性への減量支援プログラムが妊娠に寄与する可能性
について報告をしています。
国際内分泌学会年次総会で発表されたこの研究では、カナダ国内で不妊治療専門クリニックに紹介されたカップルのうち、男性パートナーが肥満と診断された65組のカップルを対象として、男性側の肥満と不妊との関連性についての検討が行われました。
男性パートナーは約1年間にわたって、栄養指導と運動療法の支援プログラムに参加し、その後の妊娠に与える影響を調査しました。
その結果、男性パートナーが適正体重へとコントロールできた場合に妊娠率は有意に上昇し、体重を減らした対象者ほど妊娠までの期間も短かったと報告しています。
肥満男性では、遺伝子の発現パターンに変化が認められる
3つ目に紹介するのは、デンマーク・コペンハーゲン大学のRomain Barres博士のチームが発表している論文で、
(1) BMI;Body Mass Indexが30以上の肥満男性では、特定の遺伝子に通常とは異なる発現パターンが生じている
(2) その遺伝子情報が精子を通じて子どもへと伝達され、将来的に子どもが肥満になりやすい体質になる可能性
を指摘しています。
この研究は、国際的な細胞生物学カテゴリーの学術誌の中で最も高い評価を受けている科学誌の一つであるCell Metabolismに発表された論文で、外科的な肥満手術(減量手術)を受けた6名の被験者の精子を解析しました。
肥満男性では、食欲制御や脳の発達に関わる遺伝子に、標準体重の男性とは異なる発現パターンがあることを発見し、減量手術を受ける前、受けた後、術後から1年後、まで定期的に解析を行った結果、その遺伝子の発現に“エピジェネティックな変化(※DNAの配列を変えずに、タンパク質等の化学修飾によって遺伝子の働きをコントロールする仕組み)”を認めたと報告しています。
Romain Barres博士は「これらのエピジェネティックな変化が、具体的にどのような影響を与えているのかについては決定的な結論には至っていない」と述べる一方で、減量手術によって正常な体重へと改善した場合、遺伝子の発現パターンは標準体重の男性に近づいたとしています。
また、「標準体重の男性と肥満男性で、特定の遺伝子の発現パターンにこれほど大きな違いが見られるのは非常に珍しく興味深く、このような変化が不妊症を引き起こしている可能性がある」とし、この研究を裏付けるものとして「マウスやラットを用いた研究でも同様の結果が得られた」と明らかにしています。
まずは自分の健康状態や生活習慣を理解し継続的に改善をはかる
ヒトの精子は、精巣内の『精細管』という組織の中で形成されますが、精子の“素”となる細胞から成熟した精子に発育していく過程には約74日かかると言われています。
そのため、直近の生活習慣が精液検査の結果にあらわれるのではなく、過去の長期的な行動・習慣や健康状態の結果がデータとして反映されると考えるのが一般的です。
これは裏を返せば、精液データの改善をはかるためには、短期的な取り組みではまったく効果が無く、データに反映されるためには生活習慣の改善・環境変化などに関して少なくとも3ヶ月程度の継続した取り組みが必要になるということです。
また、いわゆる精子の“質”は、より具体的に言えば精子内部の遺伝子情報であるDNAがいかに正常であるか、損傷を受けていないかであり、従来の精液検査項目である精子濃度や運動率では判断することは出来ません。
たとえ、精子の数や運動性に問題が無くても、精子DNAに損傷を受けている割合が多い男性患者様は数多くいらっしゃいます。そのような精子DNAに損傷を受けている精子が多ければ、当然ながら治療の顕著に成功率は低くなり、女性側の負担やコスト面での負担も著しく増加してしまいます。
ご夫婦が不妊症と診断されていて、男性側に少しでも思い当たる要因があるという場合には、積極的に改善に取り組んでいかなければなりません。
「不妊治療はチームで行うもの」という意識を持つ
不妊治療、特に体外受精などの高度生殖医療では、女性側が受ける負担はとても大きいです。
日々の通院や、ホルモン採血、経腟超音波、自己注射に加えて、採卵では長さ30cmほどの針をお腹の中に刺すわけですから、そのダメージは男性では容易に想像がつかないのではないでしょうか?
不妊治療はチームで行う治療であり、どちらか一方が欠けてしまっては成立しない治療です。
そのため、治療における女性側・男性側の負担がアンバランスな状態では、治療を継続することそのものが極めて難しくなってしまいます。
「精子がいるから大丈夫」といった安直で馬鹿げた思考ではなく、いかにして良好な精子を造るか?そのために何をしたらいいのか?を常に考えて行動し、妊活・不妊治療に臨む必要があります。
最後に
今回のコラムでは、男性の肥満と生殖能力に与える影響について解説をしてきました。
男性側がどんなに生活習慣の改善に取り組んでも、妊娠という事象は100%保証されるものではありません。しかしながら、カップルで共に同じ目標に向かって努力をするということは妊活・不妊治療においては最も重要なことであると考えます。
コラムの冒頭でも解説した通り、不妊症要因の約35~45%には男性側が関わっています。
不妊治療を自分事として認識し、自分たちがチームであり“対等なパートナーである”という意識を持つことが出来れば、生活習慣の改善が妊娠のためのノルマという義務的なものでは無く、当たり前のように取り組んでしかるべきのもの‥‥と捉えられるようになるのではないでしょうか?
参考文献
- Paternal obesity negatively affects male fertility and assisted reproduction outcomes: a systematic review and meta-analysis. Reprod Biomed Online. 2015 Nov;31(5):593-604. doi: 10.1016/j.rbmo.2015.07.012. Epub 2015 Aug 10. Jared M Campbell, et al.
- Trends of male factor infertility, an important cause of infertility: A review of literature. J Hum Reprod Sci. 2015 Oct-Dec;8(4):191-6. doi: 10.4103/0974-1208.170370. Naina Kumar, Amit Kant Singh.
- The Obesity-Fertility Protocol: a randomized controlled trial assessing clinical outcomes and costs of a transferable interdisciplinary lifestyle intervention, before and during pregnancy, in obese infertile women. BMC Obesity volume 2, Article number: 47 (2015). Karine Duval, et al.
- Obesity and Bariatric Surgery Drive Epigenetic Variation of Spermatozoa in Humans. Cell Metabolism. Volume 23, Issue 2p369-378February 09, 2016. Ida Donkin, et al.
- Boosting male fertility with diet and weight loss;CNN Health