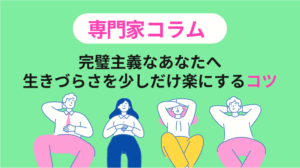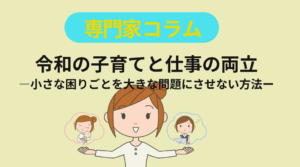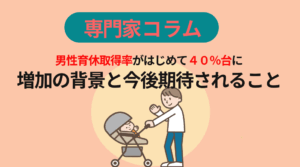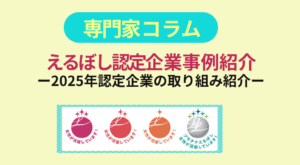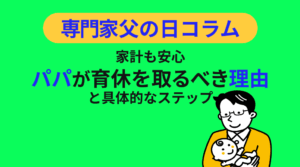「子育てだけでも大変なのに、親の介護まで同時に……?」
そんな状況が突然訪れることを、「ダブルケア」と呼びます。子育てと親の介護、あるいは子育てとパートナーの看護など、家族・親族への複数のケアが重なることを指します。
平成28年に公表された内閣府の調査(※1)によると、未就学児の育児と介護を同時に担う「ダブルケアラー」は全国で推計約25万人いると言われています。誰にとっても他人事ではなく、ある日突然、ダブルケアに直面する可能性があります。
このコラムでは、そんなダブルケアの実態や影響、そして事前にできる備えについて解説します。
ダブルケアとは?
ダブルケアとは、育児と介護など、複数のケアが同時に求められる状況のことを指します。代表的なケースとしては以下のようなものがあります。
・育児と親の介護(例:40代で子どもが幼稚園、親が要介護状態)
・育児とパートナーの看護(例:子育て中に配偶者が大病を患う)
・育児と祖父母の介護(例:共働きのため祖父母に子育てを頼っていたが、祖父母が介護状態になる)
特に、共働き家庭ではどちらの親もフルタイムで働いており、育児と介護の負担がのしかかることで、心身の疲弊が深刻化しやすいのが特徴です。
ダブルケアの実例
① 40代女性・フルタイム勤務のAさんのケース
Aさんは3歳の娘を保育園に預けながら、正社員として働いていました。そんな折、遠方に住む母が脳梗塞を発症し、要介護状態に。最初は兄弟で介護を分担していましたが、兄弟にも仕事と家庭があり、最終的にAさんが中心となって介護を担うことになりました。仕事、育児、介護のすべてをこなす中で精神的・身体的に追い詰められ、休職を余儀なくされました。
② 50代男性・フルタイム勤務のBさんのケース
Bさんは小学生の子ども2人を育てながら、家計を支えていました。妻は専業主婦で、家庭のことは妻中心に回っていました。ある日、妻が突然の病で入院し、長期の治療が必要になりました。Bさんは仕事をセーブしながら育児と妻の看護をこなす日々に。育児支援制度や訪問看護などを活用することで、なんとか生活のバランスを保つことができました。
ダブルケアがもたらす影響
① 身体的・精神的負担
育児と介護のどちらも24時間対応が必要なことが多く、休息の時間を確保しにくくなります。慢性的な睡眠不足や疲労により、心身の健康が損なわれるケースが少なくありません。
② 経済的な負担
育児にも介護にも費用がかかります。特に介護が加わると、介護サービスの利用料や通院費、医療費などの出費が増えるため、家計のやりくりが難しくなることも。
③ 仕事への影響
ダブルケアによって、仕事の時間を削らざるを得なくなったり、離職を選ばざるを得ないケースもあります。特に管理職や責任のあるポジションにいる人ほど、調整が難しくなることが多いです。
④ 子どもへの心身の負担
親が介護と仕事に追われることで、子どもとの時間が減少し、精神的な不安を感じやすくなります。また、親のストレスが子どもにも伝わり、情緒不安定になったり、成長に影響を及ぼすことがあります。
⑤ ダブルケアラーは孤立しやすい
ダブルケアに直面すると、自分自身の時間を確保しにくくなり、周囲と交流する機会が減ることが多いです。その結果、孤立感を深め、精神的に追い込まれるケースが増えます。
事前にできる備えとは?
① 介護の可能性を考えて情報収集を
介護はいつ始まるか分かりません。事前に情報を集めておくことは重要です。
・親の健康状態を把握する(持病やかかりつけ医の確認)
・介護サービスについて知る(地域の介護施設や訪問介護の情報収集)
・金銭面の準備(介護費用の試算や利用可能な公的支援の確認)
・親と介護について話し合う(親の希望を聞き、介護方針を共有する)
② 周囲とつながる
ダブルケアを一人で抱え込まないために、周囲のサポートを活用することが大切です。
・家族との話し合い(役割分担を明確にする)
・地域のサポート制度を利用(自治体の相談窓口や支援団体) ・同じ立場の人とのつながりを持つ(SNSやオンラインコミュニティ)
心の健康を守る方法
ダブルケアでは大きなストレスがかかります。その時になってストレスに柔軟に対応する力を身に着けようとするより、今から自分に合ったストレス解消法を発見しておく方が効率的です。特に、ストレスを軽減するための「レジリエンス(精神的回復力)」を高めることが重要です。
具体的には、次のようなことに今から取り組んでみましょう。
・ポジティブな思考を意識する(完璧を求めず「できることをやる」姿勢を持つ)
・小さな楽しみを見つける(好きな音楽や趣味の時間を確保する)
・サポートを求める(家族や友人、専門家に相談し、一人で抱え込まない)
・適度な運動をする(ストレッチや散歩などを取り入れ、心身のリフレッシュを図る)
ダブルケアは、ある日突然やってきます。しかし、事前に情報を集め、心の準備をしておくことで、負担を軽減することができます。
もしあなたが「我が家にダブルケアが必要になったらどうしよう」と感じたら、まずは家族と話し合い、職場の制度を確認し、地域の支援策を調べてみてください。
そして何よりも、自分自身の心と体を大切にしながら、無理のない形で乗り越えていきましょう。
※1 内閣府男女共同参画局 平成28年4月「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。