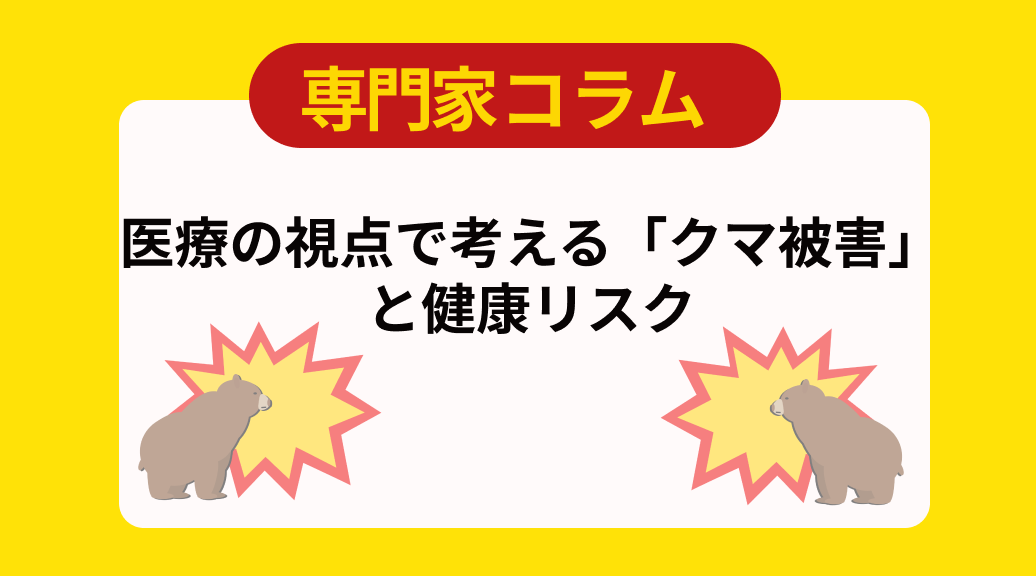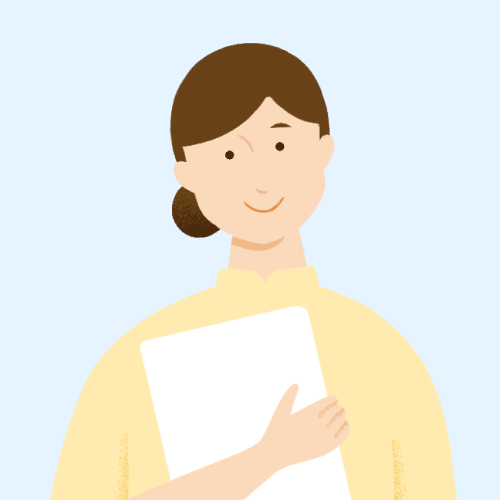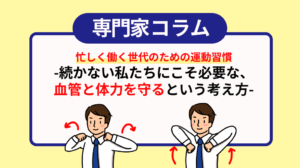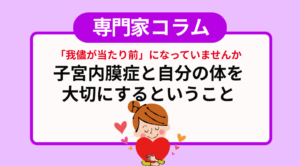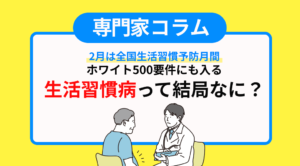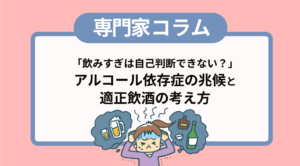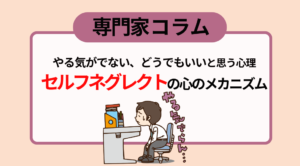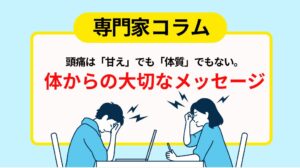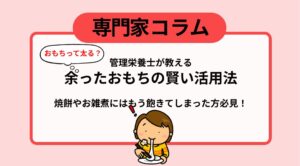最近、日本各地で「クマが出た!」というニュースを見ない日はないほど、クマの出没が増えていますね。
「また!?」「まさか自分の町にも!?」と驚かれた方も多いのではないでしょうか。
実際、ここ数年でクマによる人的被害は急増しており、環境省の速報値(2024年)によると、2023年度の被害件数は過去最多の198件。特に東北地方や北陸、北海道では深刻な状況が続いています。
クマというと山の奥に住む生き物と思いがちですが、最近では畑や民家の裏庭、通学路など、私たちの生活圏にも姿を見せるようになりました。実際に朝の犬の散歩中に遭遇した、通勤途中に見かけたなど、身近な場所での出没報告が相次いでいます。
こうしたニュースを聞くと、怖さや不安が先に立ちますが、医療の視点から見ると、クマ被害=噛まれる、引っかかれるだけではない、さまざまな健康リスクが潜んでいることがわかります。
今回は、医療的な観点を交えながらクマ被害の現状、遭遇したときのリスク、健康被害の種類、そして身を守るための具体策についてお話しします。
クマ被害の現状:なぜこんなに増えているの?
2024〜2025年にかけて、クマによる人的被害が特に多い地域は東北地方・北陸・北海道。
なぜ、ここまで出没が増えているのでしょうか?
主な理由は次の3つです。
- 餌不足と環境の変化
クマの主食であるドングリやブナの実が不作の年には、食料を求めて山を下りてきます。
また温暖化の影響で植物の実り方や虫の発生時期が変化し、生態系のバランスが崩れているとも指摘されています。 - 人慣れしたクマの増加
一度、人の住むエリアで食べ物を得たクマは、その記憶を頼りに何度も同じ場所に現れるようになります。特に、生ゴミや果樹、畑の作物が放置されている場所は格好のターゲットです。 - 人の生活圏の拡大
山間部の住宅地開発や、レジャー・登山の人気により、人間がクマの生息域に近づいているという現実もあります。
つまり、クマが人の世界に入ってきたというよりも、人がクマの世界に近づいている構図が背景にあるのです。
クマ被害=外傷だけではない! 医療者が注目する見えない健康リスク
クマの前足の力は想像以上に強く、成獣であれば一撃で骨折や深い裂傷を負わせるほどの破壊力があります。しかし、医療の現場では、外傷以外の健康被害も見逃せません。
① 出血性ショック
クマの攻撃で大腿動脈や頸動脈といった太い血管を損傷すると、数分で出血性ショック死に至る危険があります。特に山中などで救助が遅れると、止血の成否が命を左右します。もし出血がある場合はできるだけ清潔な布などで圧迫止血を行います。
② 感染症リスク
クマの歯や爪には多くの雑菌が付着しており、破傷風や蜂窩織炎(ほうかしきえん)などの感染症を引き起こすおそれがあります。
見た目に浅い傷でも、内部に細菌が入り込むと数日後に腫れや発熱が起こります。
そのため、必ず医療機関で破傷風ワクチン接種と抗生剤投与を受ける必要があります。
③ 精神的ショック・PTSD
実はクマ被害の中で、心のケアも重要な課題です。
突然の襲撃や目の前での遭遇体験は強いトラウマとなり、不眠・動悸・フラッシュバックなど、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症する人も少なくありません。
これは地震や交通事故と同じように命の危機にさらされた体験として脳が記憶してしまうためです。
心理的支援を受けることは決して弱さではなく、回復のためのケアとして必要な医療行為の一つです。
④ 二次的な健康被害
逃げようとして転倒・骨折した、心臓がドキッとして胸が痛くなったというケースも報告されています。
突然の恐怖により交感神経が急激に高まり、血圧上昇や不整脈、狭心症・心筋梗塞の誘発につながる場合もあります。特に高血圧や心疾患を持つ方は要注意です。
クマに出会わないための「3つの基本対策」
- 音を出して自分の存在を知らせる
クマは本来、人間を避ける臆病な動物です。鈴・ラジオ・会話などで音を出すことが最もシンプルで効果的です。 - 食べ物・生ゴミを残さない
畑の作物や果樹の実、キャンプ後のゴミなどはクマを呼び寄せます。一度味を覚えると再び来る学習性があります。 - 早朝・夕方の山道を避ける
クマの活動が最も活発になるのは朝と夕方。特に秋の実りの季節は注意が必要です。
万が一クマに出会ってしまったら
- 走って逃げない(背中を見せると追いかける習性があります)
- 大声を出さず、ゆっくり後ずさりする
- クマが立ち上がっても威嚇と判断し、動揺しない
- 木や岩などの障害物を間に置く
- 襲われたら首の後ろを守り、うつ伏せで丸まる(致命傷を避ける)
クマ撃退スプレーを使うときの注意
最近ではベアスプレー(クマ撃退スプレー)を持ち歩く人も増えました。しかしながら正しい使い方を知らないと使用できません。スプレーはお守りではなく、最後の防御手段として使用するものです。持ち歩かれる際はぜひ正しい使い方を知っておいてください。
- 風向きを確認する(逆風だと自分にかかります)
- 2〜3秒間、クマの顔面をめがけて噴射
- 練習用のスプレーで事前に扱い方を確認
もしケガをしたら:現場での応急処置
- 清潔な布で圧迫止血
- 骨折の疑いがあれば動かさず固定
- 意識がある場合は安静と少量の水分補給
- すぐに119番通報
その後は医療機関で、創傷洗浄・縫合・破傷風ワクチン・抗生剤投与・輸血・手術などの治療が行われます。また、心理的ショックが強い場合は精神科・心療内科での支援を受けましょう。
クマ被害から考える人と自然の関係
クマはもともと、人を襲うために生きている動物ではありません。食料不足や環境の変化が、彼らを人里に追いやっているのです。つまり、怖い存在として遠ざけるだけでなく、なぜ彼らが山を下りてきたのかを理解することも、人と自然が共に生きる第一歩です。
クマが出没しやすい地域では、地域ぐるみの対策も進められています。
地域放送での出没情報共有、山菜採りシーズンのパトロール、餌となる果実の処理など、日常のちょっとした意識が被害を防ぎます。
最後に
まさか自分がという状況でも、備えが命を守るのは医療の現場も野外も同じです。
クマとの遭遇時、落ち着いて正しく行動できるかどうかが生死を分けることもあります。
そして何より、恐れるだけでなく、知ることが最大の防御になります。
自然を理解し、共に生きる知恵を持つこと——それが、現代を生きる私たちに求められている新しい共存のかたちなのかもしれません。
【参考・出典】
- 環境省「クマ類による人身被害について(速報値)」2024年
https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/injury-qe.pdf - 環境省「クマ類による被害防止に向けた対策方針」2024年
https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-prevention-all.pdf - 環境省「クマ類の生態・行動特性に関する資料」
https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-situation.pdf - 厚生労働省「破傷風に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161955.html
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。