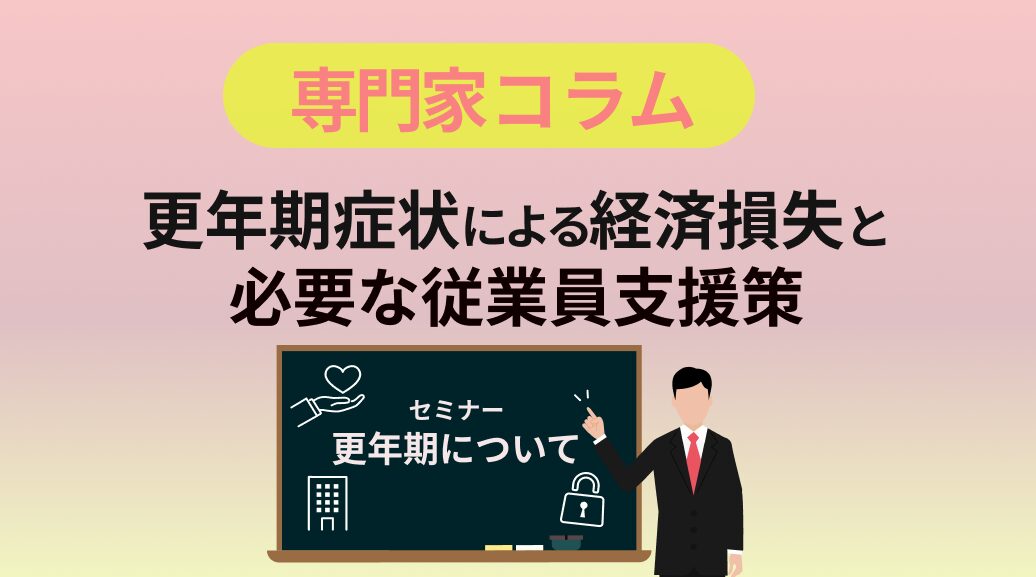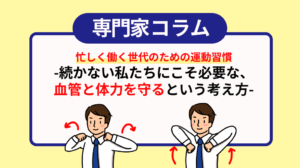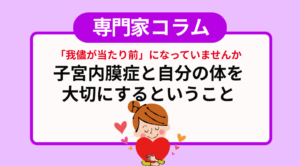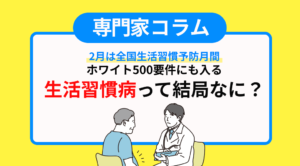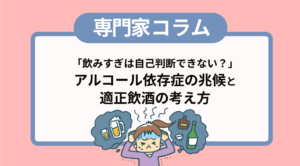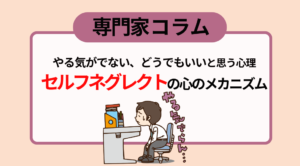男女の更年期と仕事の両立支援とは
ここ3年間ほど、男女の更年期と仕事の両立支援が注目されるようになってきました。健康課題やライフステージによる変化で仕事を諦めなければならない。そんな状況を打破するために、子育て、妊娠、不妊治療、月経・PMSといったテーマが順々に取り上げられたのち、やっと更年期の課題や支援にスポットライトが向けられたのです。
長らく、更年期に起きる健康課題は、主に女性のものとされてきました。同時に、からかいや悪口の文脈で利用されることも多くありました。女性がカッとなると「更年期じゃない?」と言ってなじるなど、「更年期」という言葉にはネガティブな意味を割り当てられてきました。
しかし今では、更年期は思春期や青年期のように誰もが通るライフステージのひとつで、更年期の症状は女性にも男性にも現れることが知られています。そして、加齢によって性ホルモンが減少するために起きる様々な症状を、からかいや悪口として利用するのは誤ったコミュニケーションである、という認識も広がってきたように思われます。
データで見る更年期の実態
2021年、NHKは全国の40代と50代の男女およそ4万5千人を対象に調査を行いました。更年期特有の症状を「現在、経験している」または「過去3年以内に経験した」という人は女性で36.9%、男性で約8.8%でした。
年代別に見てみると、女性は40代後半で34.9%、50代前半で52.3%、50代後半で42.8%が症状を経験しています。40代から50代前半にかけてをピークに、50代後半になると症状を経験する人の割合が減る、山なりの形になっていることがわかります。
一方、男性は40代前半から50代後半にかけて、わずかですが徐々に症状を経験する人の割合が高くなっていることがわかります。

更年期症状によるマイナスー更年期ロスの実態
同調査では、過去3年以内に更年期症状を経験した人で、更年期症状によって仕事に何らかのマイナスの影響があった人を「更年期ロス」として集計しました。そのうち、
・「仕事を辞めた」
・「雇用形態が変わった(正社員から非正社員になった など)」
・「労働時間や業務量が減った」
・「降格した」
・「昇進を辞退した」
など、雇用や収入に影響があった人が女性で15.3%、男性で20.5%いました。日本女子大学の周燕飛(しゅう・えんび)教授の推計では、女性で75.3万人、男性で29.2万人が「更年期ロス」に陥っているのではないかとの計算がされています。
仕事にマイナスの影響があった「更年期ロス」の内訳を見ると、女性では「仕事を辞めた」という人の割合が最も多く、9.4%。男性では「人事評価が下がった・降格した」人の割合が7.8%と最も多くなっています。実際に影響は出ていなくても、仕事を辞めることを検討している男性は15.3%、女性は10.2%でした。

更年期離職の経済的損失
「改正高年齢者雇用安定法」が2021年4月1日に施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となっている時代に、更年期症状を理由に労働力が減ってしまうというのは、企業にとって大きな損失であると言えるでしょう。また、長く健康に働き続けたい当事者にとって、更年期障害のためにキャリアが分断されるのは納得しがたい、非常に心残りのある決断となるでしょう。
令和6年2月、経済産業省が「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」を発表しました。これによれば、更年期離職による経済損失は女性で年間およそ1.9兆円、男性で年間およそ1.2兆円、合わせて3.1兆円にも上ると推計されています。

従業員支援策の重要性
同調査では、当事者の支援ニーズが大きい一方、企業側が ”ニーズを把握しづらく、何をすべきか分からない” というミスマッチが生じていると指摘されています。では、どのようなことから取り組めば、ニーズと支援のミスマッチを解消し、適切なサポート体制を作ることができるのでしょうか。
先述のNHK「更年期と仕事に関する調査2021」では、男女ともに40%近くが「職場の全員への研修」を望んでいました。一方で、「職場の人には知られたくない・自分ひとりの問題にしておきたい」という人も、女性で9.5%、男性では16.8%いました。つまり、個人の症状について周囲に詳しく知られたくないが、更年期という時期や症状について職場全体が知る機会は必要だと言えるのではないでしょうか。
知る機会を作るために、具体的には下記のような方法が考えられます。
セミナーや研修による啓発
プロジェクトチームを作り、組織的に取り組む
全社で認識を共有する
積極的なヒアリングを行う
従業員が要望を伝えやすい仕組みづくりをする
メルマガやイントラでの情報発信を行う
相談窓口の設置
これらの取り組みは、組織から社員に対する「困ったことがあったら相談してくださいね」というメッセージにもなります。
逆に従業員側は、
当事者同士のネットワークを作る
工夫していることや困っていることを共有する
複数名で組織に要望を伝える
月経やPMS、メンタルヘルスについてリテラシーを高める
かかりつけ医を見つけて医療の力を積極的に活用する
といった行動を取ることができるでしょう。組織の変化スピードを待つのではなく、自分達で働き続けやすい環境を作っていくことも大切ですね。 更年期は誰にでもやってきます。個人差はありますが、一定数が更年期特有の症状で悩み、働き方や収入を不本意に変えざるを得ない状況になるのです。働き続けたい人が健康に働き続けられる組織づくりのために、このコラムがお役に立てば幸いです。
※ファミワンでは更年期に関するセミナー等行っております。お気軽にお問い合わせください。
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。