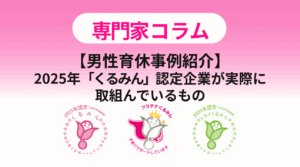くるみんは聞いたことあるけど、えるぼしって・・・?と思われる方、意外と多いのではないでしょうか。どちらも認定制度ということもあり、混乱しやすいと思いますので改めて整理していきたいと思います。
【ファミワン公式】「くるみん認定チェックシート」でくるみん認定をチェックしてみませんか?ダウンロードは無料です。
えるぼしって何?
「えるぼし」とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定制度で、一定の基準を満たし、女性活躍推進に関する状況などが優良な企業に発行される認定マークです。くるみんは次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度となるため、そもそもの土台となる法律が違います。しかし、共働き率も高くなり、結婚、出産後も働き続ける女性が増えているため、この2つの制度を意識して各種人事施策を行っていくことが、現在の経営者や人事担当者には求められていると考えています。
くるみんについてはこちら
【ファミワン公式】「くるみん認定チェックシート」でくるみん認定をチェックしてみませんか?ダウンロードは無料です。
女性活躍推進法とは
正式名称は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律と言い、平成27年に成立しました。この女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、つまり女性活躍推進法は働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられたものです。また、令和4年7月に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられました。
【ファミワン公式】「くるみん認定チェックシート」でくるみん認定をチェックしてみませんか?ダウンロードは無料です。
情報の公表について
各種の情報公表にあたっては、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の 「女性の活躍推進企業データベース」にて公表されているため、気になる企業の情報はこちらで確認が可能です。なお、「男女の賃金の差異」の情報を有価証券報告書のみにおいて公表しても、女性活躍推進法の義務を果たしたことにはならないため担当者は注意が必要です。一般の求職者等から見て、男女の賃金の差異の情報がどこに掲載されているのかがわかるように前述の「女性の活躍推進企業データベース」や自社の採用ページ等で情報公表をすることが求められています。また、情報公表の期限についても注意が必要です。
男女の賃金の差異については、改正省令の施行日(令和4年7月8日)以後に終了する事業年度について、当該事業年度が終了し、新たな事業年度が開始してからおおむね3か月以内に公表することとされています。つまり、令和5年3月末にて事業年度が終了し、同年4月から新しい事業年度が開始している場合は同年6月末までがおおむねの公表期限となります。本コラムは令和5年7月に作成しているため、3月決算の企業における男女の賃金差異については既に公表されている、ということになります。
【ファミワン公式】「くるみん認定チェックシート」でくるみん認定をチェックしてみませんか?ダウンロードは無料です。
まとめ
くるみん認定制度においては、男女の育児休業取得率や、子育てと仕事を両立していくために必要とされる施策の有無等について主な認定要件となってきています。その背景としては、将来の労働力不足への問題に対して出産後も働き続ける女性を増やしていきたい、そのためには男性の育児参画が重要だという国の意思が見てとれます。しかし、それだけではなく、女性が「ただ働く」ことだけを支援するのではなく、公平な処遇のもと、正当に評価され、長く働き続けることができる社会を作っていくことも日本社会における重要な課題であり、くるみん制度とえるぼし制度は切っても切れない関係と言えるのではないでしょうか。
【ファミワン公式】「くるみん認定チェックシート」でくるみん認定をチェックしてみませんか?ダウンロードは無料です。
参考:
厚生労働省女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
男女共同参画局 女性活躍推進法 「見える化」サイト
無料「くるみん認定チェックシート」ダウンロード
「くるみん認定」「くるみんプラス認定」取得に向けた取り組みをご相談いただけます。
不妊治療と仕事の両立支援や育児支援制度の整備をはじめ、認定取得を後押しする多様なサポートをご提供します。

1. 「まずは自社のくるみん対応度を可視化」
あなたの会社は、くるみん取得に向けてどの段階にありますか?
このくるみんチェックシートで現状ギャップを把握し、改善の優先ポイントを明確にできます。
2. 「不妊治療と仕事の両立支援もカバー」
「くるみんプラス認定」では、不妊治療支援も評価対象。
関連資料とあわせて、制度設計や支援施策のヒントが得られます。
3. 「無料で資料を入手・取り組みをスタート」
くるみんチェックシートのダウンロードは無料。
資料をもとに、社内で議論を始めたり、外部支援の相談も可能です。