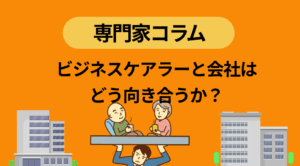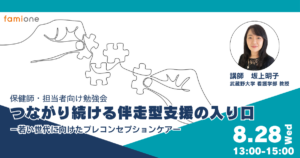はじめに
皆さんこんにちは。胚培養士の川口 優太郎です。
2025年7月27日にファミワン主催で開催されました『夏休みスペシャル!こども性教育 ボクらのカラダ大冒険!~思春期のヒミツ~』にて講師として登壇をさせていただきました。
“男の子向けの性教育講義を、男性の講師から話す”という、他ではなかなか無いイベントということもあって、300名を超えるたくさんの子どもたちにお申し込みをいただきました。
性教育というと、どうしても普段の生活の中では、触れにくい・話しにくい・聞きにくい、といった内容も多くありますので、今回のイベントでは貴重な機会を提供出来たのではないかなと思います。
さて、このこども性教育イベントでは、男の子向けの思春期の変化にフォーカスしてお話しをしましたが、性教育、特に男性のカラダの変化についてさらに掘り下げていくと、「そもそも、なぜヒト(男性)が現在の形態に進化したのか?」「進化の過程にはどのような根拠があるのか?」といった進化生物学や生命科学に辿り着きます。
数十億年という長い年月をかけて小さな細胞から断続的に組み立てられてきたヒトとその成り立ちについては、多くの科学者たちが現在も研究を続けていますが、実は解明されていないこともまだまだ数多くあります。
今回のコラムでは、男性の身体のヒミツについて掘り下げ、生物学・生命科学的な視点から解説をしていきたいと思います。
Tree of Life;生命の樹について
ヒトを始めとする生物の進化は、それぞれどのように分類され、どのように構築され、どのような要素がその生物を成すための設計図に加わったのか、を読み解くことからスタートしていきます。
生物は、分類階級と呼ばれる階層的なレベルによって分類されていきます。
基本的には、まず「界」という最も上位のグループに分けられ、その後「門」「綱」「目」「科」「属」「種」というより詳細なグループに分類されます。このような分類は、スポーツのトーナメント表や、樹木の枝葉に例えられることもあり、生命の樹(Tree of Life)とも呼ばれます。
われわれヒトであれば「動物界」「脊索動物門」「哺乳綱」「霊長目」「ヒト科」「ホモ属」「サピエンス種」と分類されます。それぞれの分類階級は、生物学的な進化の過程や特徴に基づいて定められており、下位の階級になるほど、より近い種類の生物となります。
“種”を構築、あるいは区別する上で最も重要となる要素のひとつに『生殖的隔離』があります。
生殖的隔離を極めて簡単に説明すると、
「同じ“種”に属している生物個体どうしは、生殖・繁殖行動によって生殖能力を持った子孫を残すことが可能だが、異なる“種”どうしでは、生殖能力のある子孫ができないか、またはそもそも交配自体が成立しない」
という理論です。例えば、私たちヒトとチンパンジーは、生物学的には非常に近縁で遺伝子情報の約98%以上が共通していますが、異なる“種”に属しているためヒトとチンパンジーでは交配が成立しません。
収斂進化(Convergent Evolution)と適応放散(Adaptive Radiation)
生物学的な進化の過程や特徴、そして生物がどのようにして現在の姿・形になったのか。今回のコラムの主役である『なぜ男性が今の形態に進化したのか?』を知るためには、「収斂進化(しゅうれんしんか)」と「適応放散(てきおうほうさん)」という考え方を知っておく必要があります。
収斂進化とは、系統的に異なる生物が、似たような環境下、あるいは似たような生態的地位に順応することで類似した形質を獲得する現象で、生物が生存のために環境に最適化された結果として姿や機能が似てくることを指します。
例えば、コウモリとトリはどちらも空を飛ぶ能力を持っていますが、コウモリは哺乳類、トリは鳥類です。コウモリの翼は皮膚の一部であるのに対し、トリは羽毛で構成されています。
一方の、適応放散とは、共通の祖先を持つ生物が多様な環境に進出してそれぞれの環境に適応していくことで、形態的、生理的、生態的に分かれていく現象です。
例えば、オーストラリアに棲息するコアラやカンガルーは同じ有袋類ですがまったく異なる生態を持ちます。コアラはユーカリの葉しか食べず生涯のほとんどを樹の上で過ごしますが、カンガルーは雑食性で、地上を時速60~70kmで跳躍し移動します。
“サイズ”から読み解く男性の進化
収斂進化や適応放散による形態・形質は、特に個体そのものや身体の特定の部位の大きさ(サイズ)に特徴として表れることがあります。
例えば、イルカとサメは哺乳類と魚類という異なる系統のグループに属しますが、どちらも水中での生活環境に適応し、同じような個体の大きさ、同じような体型(背びれ、胸びれ、尾びれなど)といった共通の特徴を持つように進化しました。対して、スズメの仲間であるフウキンチョウの一種であるダーウィンフィンチという鳥は、同じ“種”の中に、硬い豆類・種子を食べるもの、昆虫を食べるもの、果実を食べるものなど、異なる食性を持つ個体が存在し、大きさや形状などがそれぞれの食性に適応したクチバシへと進化する多様化が見られています。
このような、特定の身体の部位の進化は、われわれヒトにも見られます。
今回のコラムのテーマである「男性のカラダ」、そして不妊治療・生殖医療というところにフォーカスをしてみると、ヒトの男性の睾丸(精巣)は、他の生物や霊長類動物と比較して相対的にサイズが小さいということが知られています。
生物学的に近縁で、約98%以上遺伝子情報が共通していると解説したチンパンジーでは睾丸の体重比(※個体の体重のうち、特定の部位が占める重さの割合)で見るとヒトの約5倍も大きいサイズの睾丸を持っています。
一方で、同じくヒトと共通の祖先を持つゴリラは、体重比で見るとヒトの1/3程度ほどの大きさしかありません。
ではなぜ、同じ霊長類であるにも関わらず、このようなサイズの差があらわれたのでしょうか?収斂進化や適応放散の原理を理解していれば、その答えに辿り着きます。
生きるための戦略・選択や環境への適応が“形”にあらわれる
先述した通り、収斂進化でも適応放散でも、原理・原則としては、生息している環境や生態的地位に沿った合理的な形質に進化していきます。つまり、それぞれの生物のサイズは、その大きさが生息環境や生態的地位、習慣、食性、活動時間など、生きていくため(あるいは子孫を残すため)の戦略として最も適している形態に進化したのだと言えます。
例えば、コロブスザルとマカクザルという、同じオナガザル科のサルがいます。成体の身体の大きさはいずれも約13~15kgとほとんど同じです。また、ヒトとチンパンジーと同様に、コロブスザルとマカクザルも遺伝子の系統がかなり近縁です。しかしながら、睾丸の大きさはまったく異なります。
コロブスザルの睾丸はおおよそ3グラム(体重比でおよそ0.02%)程度であるのに対し、マカクザルの睾丸はなんと48グラム(体重比およそ0.3%)もあります。
では、なぜこのような大きさの差があらわれるのか?考えられている理由は大きく2つあり、
1)生物学的に、睾丸の大きさが“種”によってはクジャクが羽を広げるのと同様で求愛行動やメスへのアピールになる
2)それぞれのサルの生息環境や生態的地位、習慣、繁殖様式などから適したサイズへと進化した
とされています。
後者について少し詳しく解説していくと、コロブスザルとマカクザルでは、生態様式や繁殖様式が大きく異なります。
まず、コロブスザルは一夫多妻制で、オスがハーレムを形成します。食糧や縄張り、交尾するためのメスを巡ってオス同士が熾烈な競争を行います。より強いオスが繁殖の機会を得ることが出来るようになり、メスも強いオスとの繁殖を有利に進めることができます。
一方で、マカクザルは乱婚制で、雌雄混成の群れで比較的平和な環境下に生息しており、繁殖期になるとオスもメスも複数の相手と交尾をします。
コロブスザルの場合、繁殖よりも前の段階で、力によるオス同士の競争があるため、その競争に勝つことこそが自分の遺伝子を残すこととなり、ここには生物学的淘汰があります。そのため、勝負に勝つことで特定のメスとのみ繁殖を行うコロブスザルは睾丸がそれほど発達していません。
それ対してマカクザルは、乱婚制のため、自分自身の遺伝子とそれ以前またはそれ以降に交尾した他のオスの遺伝子(精子)の争いになります。メスの体内でどの精子が受精できるかは、より多くの精子を作れる個体にこそ遺伝子を残せる可能性が高くなるため、進化の結果、睾丸の機能が発達=サイズが大きくなるという形質にあらわれたのではないかと考えられているわけです。
ちなみに、ゴリラは睾丸の小さく、チンパンジーは大きいというお話しをしましたが、それぞれの繁殖様式を見てみると、ゴリラはコロブスザルに近い生態を持ち、群れのリーダーのオスはシルバーバック(背中の毛の色が銀白色になることから)と呼ばれ、特定のメスとのみ繁殖を行います。
一方のチンパンジーは、マカクザルと同様に乱婚制で、複数の相手と繫殖行動を行います。
ヒトの進化は多様な選択肢の結果
では、ヒトの男性の睾丸のサイズはどうなのか?ということですが、ヒトは一夫一婦制が基本ではあるものの、国・地域や民族、宗教などによって非常に多様な配偶戦略を持ちます。
ゴリラのように群れを形成するわけでも、チンパンジーのように乱婚制でも無く、霊長類の中では、極めて中間的で多様な繁殖システムがあります。
生物全体で見ると、ヒトの睾丸のサイズは体重比では小さい部類に入るものの、ゴリラよりも大きく、チンパンジーより小さいのは、このような多様な生態と繁殖システムを持った結果なのではないかというのが現在最も有力な説とされています。
さて、今回のコラムでは「なぜヒト(男性)が現在の形態に進化したのか?」を掘り下げ、詳しく解説をしてきましたが、ヒトの進化は決して直線的に進んで来たわけではなく、人種、民族、文化、政治、宗教などの様々な要因によって形作られたということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
多様性が進む現代においては、近い将来、さらなる進化を遂げた新しいヒトの“種”が誕生するのかもしれませんね。
参考文献
- Sexual ornaments but not weapons trade off against testes size in primates, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, April 10, 2019 Volume 286, Stefan Lüpold, Leigh W. Simmons and Cyril C. Grueter
- Mating system and brain size in bats, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, March 22, 2006 Volume 273, Scott Pitnick, Kate E Jones, Gerald S Wilkinson
- University of Oxford, Museum of Natural History, “Reading the Tree of Life”
- The Tree of Life, Solving Science’s Greatest Puzzle, Prof, Max Telford
- 面白くて眠れなくなる生物学, 著者;長谷川英祐 出版;PHP研究所 ほか
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。


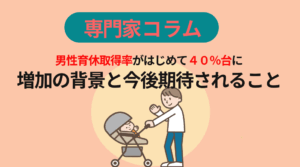
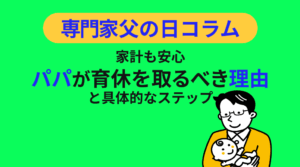

について助産師が解説します-300x167.jpg)