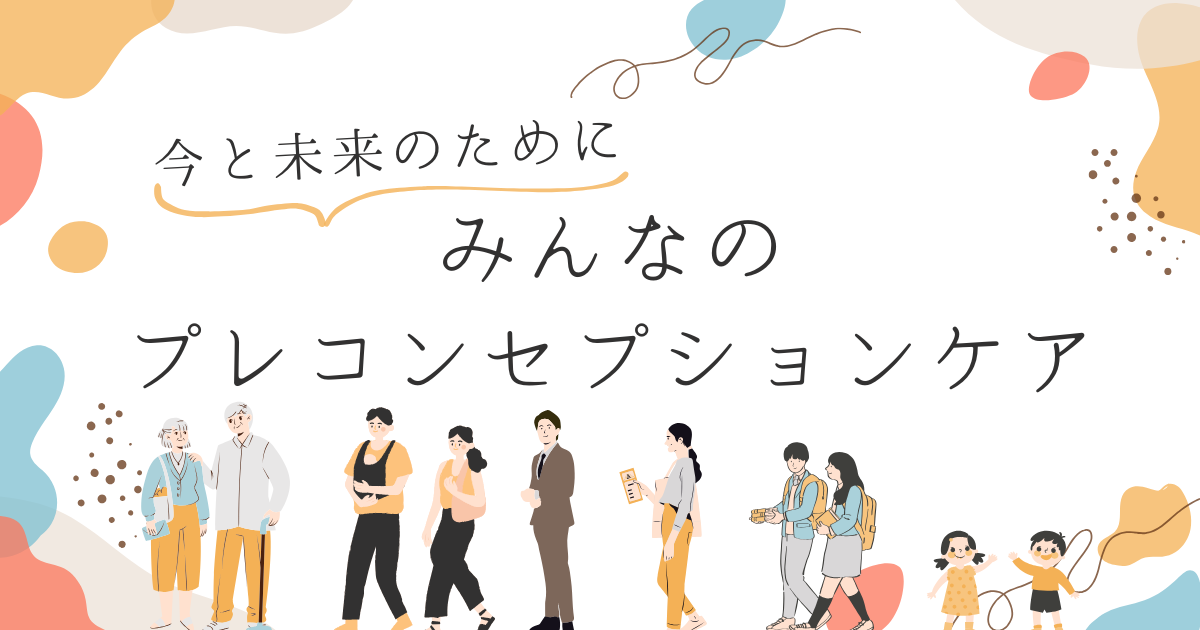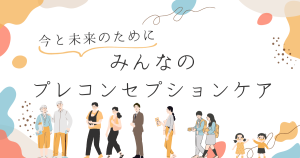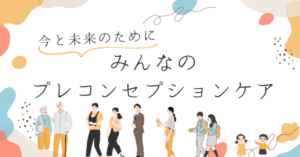赤ちゃんを授かる前も、妊娠がわかった後も、母体と未来の命を守るために今できるケアのひとつがワクチン接種です。感染症によっては妊娠中にかかると、流産や早産、赤ちゃんの発育に大きな影響を及ぼすことがあります。だからこそ妊娠前から接種歴や抗体の有無を確認し、必要なワクチンを受けておくことが大切です。このコラムでは薬剤師の視点から、妊娠前後に知っておきたいワクチンについてわかりやすく解説します。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
妊娠を考える前に確認しておきたいワクチン
妊娠前に特に気をつけたいのは、風疹や麻疹、おたふくかぜ、水痘、B型肝炎の予防です。これらの感染症は妊娠中に初めてかかると、母体の重症化や、赤ちゃんに先天異常や障害が残るリスクが高くなります。
たとえば風疹は、妊娠初期に感染すると「先天性風疹症候群」という心臓疾患や難聴、白内障などの障害を赤ちゃんに引き起こす恐れがあります。男女問わず接種歴を確認し、抗体が不十分ならワクチン接種を検討しましょう。自治体によっては抗体検査や接種に助成がある場合もあります。
麻疹(はしか)は直接の先天異常は少ないとされていますが、妊婦が感染すると高熱や肺炎を起こしやすく、流産や早産のリスクが高まります。麻疹も風疹と合わせて抗体検査を行うことが多く、接種歴の確認が大切です。
おたふくかぜは妊娠中に感染すると重症化しやすく、胎児の難聴など後遺症が残ることがあります。水痘(水ぼうそう)は妊婦が初めて感染した場合、重症化のリスクが高く、赤ちゃんに先天性水痘症候群が起こることもあります。
B型肝炎は母子感染すると、将来的に慢性肝炎や肝がんに進展する恐れがあります。妊娠前に抗体検査をして感染リスクを確認し、必要であればワクチンを接種しましょう。
これらのワクチンのうち、風疹・麻疹・おたふくかぜ・水痘は生ワクチンで、接種後は原則2か月間の避妊が必要です。一方、B型肝炎ワクチンは不活化ワクチンであり、妊娠中も接種可能で避妊は不要です。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
妊娠中に接種を考えられるワクチン
妊娠中生ワクチンは原則接種できませんが、不活化ワクチンは安全性が確認されているものに限り、接種が推奨されることがあります。
2024年6月から接種が始まったRSウイルスワクチン「アブリスボ」は、生後3か月以内の赤ちゃんの重症化を約81.8%防ぐ効果が報告されています。RSウイルスは生後1歳までに半数以上、2歳までにほぼ100%の子どもが少なくとも一度は感染するありふれたウイルスで、発熱・くしゃみ・咳などの「風邪」の症状を引き起こします。特に生後半年以内の乳児は重症化リスクが高く、効果的な抗ウイルス薬やワクチンはこれまで存在しなかったため、妊娠中のワクチン接種は非常に重要です。日本産婦人科学会は妊娠28~36週の接種を推奨しており、費用は自費で約3万円です。
また、インフルエンザワクチンは妊娠中いつでも接種可能で、母体の重症化を防ぐだけでなく、赤ちゃんにも抗体が移行します。費用は3,000~5,000円程度で、自治体の助成がある場合もあります。
新型コロナワクチンは妊娠中の重症化リスクを軽減するため推奨されており、接種により赤ちゃんへの抗体移行も期待できます。現在、妊娠可能年齢の女性への公費接種は終了しているため自費での接種となり、費用は約15,000円です
百日咳ワクチンは、生後2か月未満の赤ちゃんを守るために、妊娠27~36週の早めの時期に接種すること、また妊娠ごとに接種することが推奨されています。成人用三種混合ワクチン(百日咳、ジフテリア、破傷風)は自費で約1~1.5万円、子ども用の三種混合ワクチンで代用すると約5,000円前後です。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
思春期からの予防にHPVワクチン
ヒトパピローマウイルス(HPV)は性交渉で感染し、子宮頸がんや性器のイボ(尖圭コンジローマ)の原因となります。出産時に母体から赤ちゃんに感染することもあるため、早めの予防が大切です。
HPVワクチンは現在小学校高学年から高校1年生の女児が定期接種の対象で、複数回の接種が必要です。女児は定期接種になっているため原則公費ですが、男児は任意接種のため助成については自治体によって異なり、公費対象外の場合は接種完了までに自費で約5万〜9万円程度かかります。また、ワクチンだけで子宮頸がんを完全に防げるわけではないため、定期検診も欠かせません。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
まとめ:未来の命を守るために
ワクチン接種は、母体と赤ちゃんの健康を守るための大切な準備です。妊娠前から抗体検査や接種計画を立て、必要な予防接種を受けておくことで、安心して妊娠を迎えられます。わからないことや不安があれば、かかりつけ医や薬剤師に気軽に相談してくださいね。
※ファミワンではプレコンセプションケアについてのセミナー、チェックシートのカスタマイズ作成など行っております。ぜひお問い合わせください。
「プレコンセプションケア」を推進したい方へ
妊娠前から始める健康管理「プレコンセプションケア」取り組みのご相談が可能です。プレコンセプションケアの実践をサポートする多様なサービスを提供し、個人向けにはオンライン相談や卵巣年齢チェック、性教育授業を、自治体・企業・教育機関向けには理解促進と行動変容を後押しする効果的な情報発信支援をご提案します。

1. 個人向け多様なサービス提供
オンライン相談、卵巣年齢チェック、動画配信、性教育授業など、お一人おひとりのニーズに合わせた幅広いサービスを展開しています。
2. 組織向け理解促進・行動変容支援
自治体・企業・教育機関に向けて、プレコンセプションケアの普及啓発と実践的な行動変容をサポートします。
3. 効果的な情報発信・啓発活動
オンラインセミナー開催支援、SNS運用サポート、リーフレット等の啓発ツール活用で効果的な情報発信をご提案します。