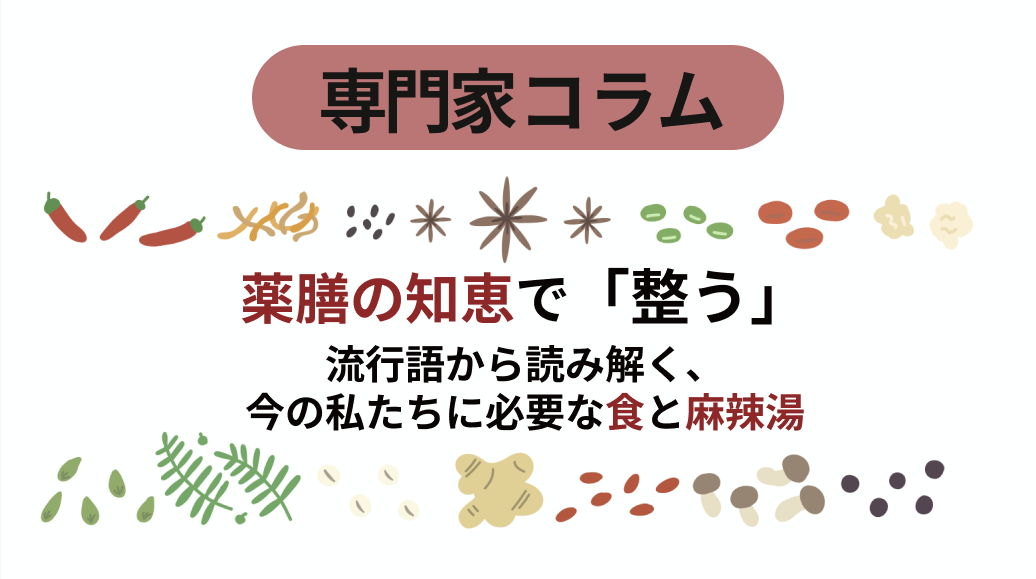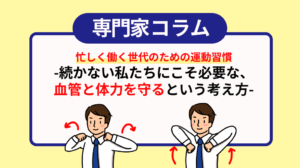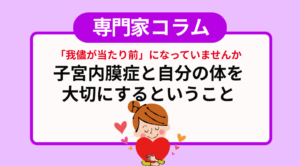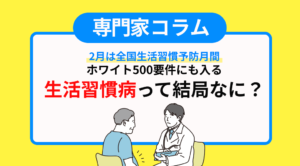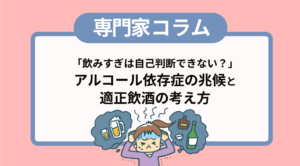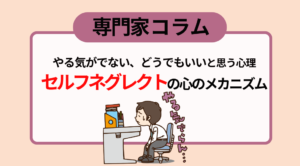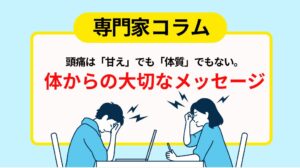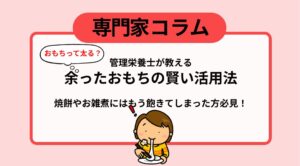近年、食や健康に関する価値観が大きく変化しています。今年の流行語大賞にノミネートされた言葉を見ても、「整う」「メンタルケア」「自己肯定感」など、心と身体を自分自身で調律することを大切にする空気が色濃く反映されています。忙しさや不安がつきまとう現代の生活の中で、「自分を立て直すための行動」を求める人が増えていることを感じます。
管理栄養士として多くの方と接する中でも、「無理なく続けられる健康習慣」や「食で心身を整えたい」というニーズが年々高まっていると実感しています。こうした時代の流れの中で、静かに広がりつつあるのが、薬膳の考え方を取り入れた麻辣湯(マーラータン)という食の楽しみ方です。
今なぜ、麻辣湯が求められているのか
麻辣湯は、中国の四川地方を代表する「麻(しびれ)」と「辣(辛味)」を掛け合わせたスープ料理であり、好みの具材を選んで煮込むシンプルさが魅力です。外食として選びやすく、家庭でも作りやすい。そして薬膳素材との相性が良いことから、現代のライフスタイルに寄り添う“整えの料理”として人気が高まっています。
薬膳では、心と身体のバランスは「気・血・水」という概念で捉えられます。これらの巡りが滞ると、疲労、冷え、むくみ、メンタルの不調などにつながるとされます。麻辣湯のベースとなる食材は、まさにこの巡りを整えてくれるものばかりです。
麻辣湯に込められた「巡らせる力」
まず注目したいのが花椒の働きです。独特のしびれる香りを持ち、薬膳では「気を巡らせる」食材とされています。ストレスでこわばった心身をゆるめ、滞りがちな気を動かすと考えられています。栄養学の観点から見ても、辛味成分による交感神経の調整や、血流の改善作用が期待できます。
次に唐辛子には、代謝を高めて身体を温める働きがあります。冷えやすい体質の方、冬場に疲れが重くなりやすい方に非常に相性の良い食材です。また、生姜やにんにくは胃腸を温め、消化吸収を助ける働きがあります。季節の変わり目で胃腸が弱りやすい時、ストレスで食欲が落ちている時にも心強い存在です。
さらに、麻辣湯の具材として選ばれることの多い豚肉、豆腐、卵などは、たんぱく質やビタミンB群が豊富です。これらは代謝の材料となり、疲労回復や免疫力の維持にも役立ちます。きのこ類や黒きくらげなどの食物繊維源を組み合わせることで腸内環境も整えやすく、心身全体の調子に良い影響をもたらします。
選ぶ行為そのものが「セルフケア」
麻辣湯の大きな魅力は、具材を自分で選べる点にあります。薬膳では、食材を選ぶという行為そのものが「自分の体調と向き合う最初の一歩」とされています。今日は冷えている、今日は疲れが抜けない、今日は気持ちが落ち着かない。そうした小さな変化に気づき、必要な食材を選んで組み合わせていくことは、日常の中でできるセルフケアの一つです。
例えば、冷えが強い日は生姜やラム肉、にらを選び、疲れが抜けない日は豚肉ときのこ、小松菜を組み合わせる。気持ちがざわつく日は、豆腐や白菜、黒ごまを加えて滋養を高める。このように、麻辣湯は“選ぶ楽しさ”と“整えるための食材選択”が自然に融合している料理です。
冬の養生と麻辣湯の相性の良さ
冬は薬膳で「腎」をいたわる季節とされています。腎は生命力や体力の基礎を司るといわれ、冷えや乾燥が強い季節には特に補いたい臓器です。黒きくらげ、わかめ、黒ごま、きのこ類、根菜、豚肉などは、冬の養生に最適とされています。
これらは日本の栄養学においても、鉄分、ミネラル、食物繊維、抗酸化成分が豊富で、免疫力が下がりやすい冬場にこそ積極的に取り入れたい食材ばかりです。麻辣湯は、こうした季節の食薬を取り入れやすく、冬の身体をじんわりと支える一皿として非常に相性が良いといえます。
管理栄養士がすすめる、家庭で作りやすい薬膳麻辣湯
麻辣湯は専門的な調味料が必要に感じられるかもしれませんが、家庭でも気軽に再現することができます。ここでは、忙しい方でも作りやすいレシピをご紹介します。

材料(一人分)
- 鶏ガラスープ 300ml
- 豆乳 100ml
- にんにくと生姜 各1片(すりおろし)
- 豆板醤 小さじ1
- 花椒 小さじ1/2
- 醤油 小さじ1
- ごま油 小さじ1
- お好みの具材 200〜250g (例:豚肉、鶏肉、豆腐、チンゲン菜、白菜、きのこ、黒きくらげ、春雨)
作り方
- ごま油でにんにくと生姜を炒める。
- 具材を食べやすい大きさ切って炒める。
- 豆板醤を炒め、鶏ガラスープと豆乳を加える
- 花椒や調味料を加えて味を調える
- 春雨を入れて煮たら完成
豆乳を加えることで辛味がまろやかになり、胃腸が弱りやすい時期にも食べやすくなります。また、きのこ類を多めに入れると腸内環境が整えやすく、春雨を加えればエネルギー補給にもつながります。沸騰させると豆乳が分離しやすいので、ご注意ください。
食の力で「整う」暮らしへ
麻辣湯は、ただ辛いだけのスープではありません。選ぶ楽しさ、巡りを整える食材、身体を温める作用、そして薬膳に通じる“季節を慈しむ知恵”が詰まった一皿です。流行語に象徴されるように、自分の心と身体の状態を見つめ、丁寧に整えていくことは、これからの時代ますます必要とされる習慣になっていくでしょう。
忙しい日々の中でも、食事は自分を取り戻すための大切な時間になります。湯気の立つスープに身を委ねるひとときが、身体だけでなく心も温め、明日への活力を生み出してくれるはずです。薬膳の知恵を日常の食に取り入れながら、自分自身を大切にできる“整う暮らし”を、ぜひ楽しんでみてください。
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。