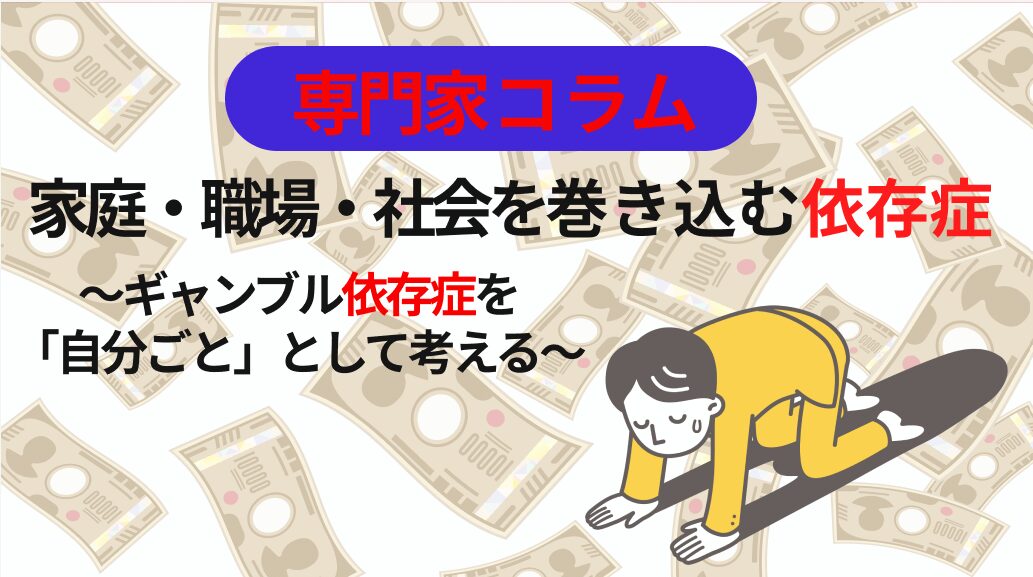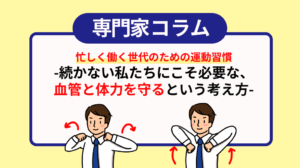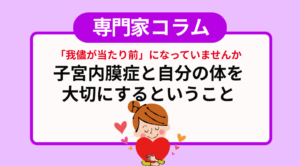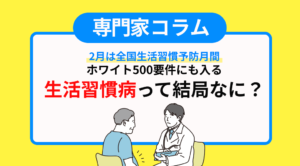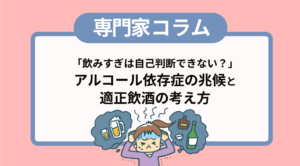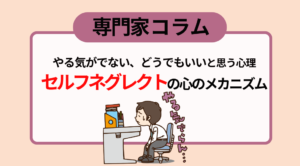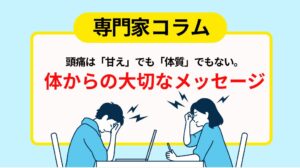なぜ“自分事”として考えるべきなのか
最近ニュースをにぎわせることが多くなったギャンブルについてのトラブルですが、皆さんはギャンブルと自分は関係ないと思っている人が多いのではないでしょうか。
しかし果たして本当にそうなのでしょうか。ギャンブル依存症には自分は関係がないのでしょうか?
ギャンブル依存症の例をいくつか見ていきましょう。
エピソード例①
・ある大学生。スロットで大勝ちをしたのをきっかけにギャンブルにのめり込んでいった。「自分には才能がある」と思い込み、親からもらった学費も賭けてしまった。大学は中退。家族関係も崩れ、ようやく自助グループに通い始めたことで回復していっています。
エピソード例②
・社会人3年目の男性。週末に競馬をストレス解消として楽しんでいました。ある日、大勝ちしたことをきっかけに、「自分は勝てる」と思い込み、仕事よりもギャンブルが生活の中心になってきました。最終的に借金が膨らみ、相談もできず孤立。「バレる前に返さないと」という焦りが事態を悪化させてしまいました。
エピソード例③
・若い頃からパチンコ依存症になった男性。闇金に手を出したことで家族にも迷惑がかかる事態になりました。「やめたくてもやめれない」辛さに10年以上の月日を費やしました。今は回復し、同じ悩みを持つ人たちの支援を始めています。
いくつかのエピソード例のように、思ってもみないうちにはまってしまったり、簡単に抜け出せると思っていても、なかなか難しかったり、また家族に迷惑が掛かって関係性が壊れてしまうということも起こっています。自分が依存症にならなくても、家族が依存症になる場合もあるでしょう。ギャンブル依存症は対岸の火事ではなく、誰にでも起こりうることなのです。

家族に起こる影響・・・なぜ「家族の病」と言われるのか
ギャンブル依存症は周りへの影響が甚大です。はまり始めた頃は、皆、自分の問題で家族は関係ないと思い、事態を軽視していることが多いです。しかしお金の問題だけでなく、関係性が壊れる、心に傷を負う、育児や介護の放棄などの問題に繋がっていくことが考えられます。自分だけの問題ではないのだと理解しておくことが大切です。
ここでは依存症が「家族の病」と言われるゆえんを見ていきましょう。
①共依存が生まれやすい
家族は依存者を助けたい一心で、お金を貸してしまったり、かばったり、隠したりなどの行動を取ることがある。そのことで依存のシステムが家族内に出来上がる。
②感情が揺さぶられることで関係性に影響を及ぼす
怒り、悲しみ、不信感、無力感、罪悪感などの強い感情を抱えるようになる。それによって家族間コミュニケーションに影響が出る。親が依存症になっている場合は、子どもが親に対して親でなくてはならないような逆転も起きやすくなる
③ひどくなると家庭内問題に発展する
離婚、別居、家庭内暴力、DV、経済困窮などの深刻な問題となりケースもある。故人の問題だったものが、家族問題に発展してしまう
④回復期についても家族支援が必要
依存症は当事者だけで回復するのは難しい問題です。家族の支えが必要でしょう。ケースによっては、依存者のみならず家族も治療やカウンセリングが必要な場合もあります。
上記のように、家族は「見えない当事者」になります。「共に生きる者」として、自分事と捉えて考えていきましょう。
職場への影響
仕事先にももちろん影響はあるでしょう。遅刻、欠勤、無断欠勤、態度の変化など、依存が進めば進むほど、周りからの信頼が無くなっていくような行動を取るようになっていきます。ギャンブルに依存しているなどと上司に相談できるはずもなく、気づかれないまま信頼が失われ、チーム力に影響を与え生産性が落ちることも予想されます。
上司は部下の変化にどうすればいち早く気づくことができるでしょうか。見えないSOSへの対応法を考えていきましょう。
【普段から部下をよく観察しておき、小さな変化に気づくことが大切です】
一番の問題は無関心です。周りや部下に関心を持ち、しっかりと見守るようにしていきましょう。
最近表情が良くないな、とか、イライラしていることが増えたな、最近周りと距離を取り孤立しているな、などに気づいたら、早めに1on1面談を行い、部下の話を聴いてみましょう。同じく、遅刻、早退、欠勤が増えるなどの勤務に変化が出ることもサインの一つでしょう。まずは話を聴くところから支援していきましょう。
職場でできる回復支援のステップ
①信頼関係を築く 批判ではなく、理解から始めよう
②柔軟な勤務体制の検討 通院や自助グループに参加するための時間調整がしやすいように整えていく
③社内相談窓口の設置や、外部支援団体との連携 産業医やEAP(従業員支援プログラム)、精神保健福祉センターや依存症専門医療機関の情報などを提供する
④職場全体の理解促進と予防としても大切な風土づくり 偏見をなくすように啓蒙運動していく 「問題を抱えても相談できる職場」という安心感を醸成していく
⑤再発防止の為の方針の作成 本人・上司・人事・産業医などで支援チームを組む
ギャンブル依存症は他人事ではありません。たとえ自分が当事者とならなくても、家族や職場に抱える問題になりえることを知り、日頃から関係性を育み、かかわる人を温かい目で観察して、いち早く異変に気付くことが大切です。
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。