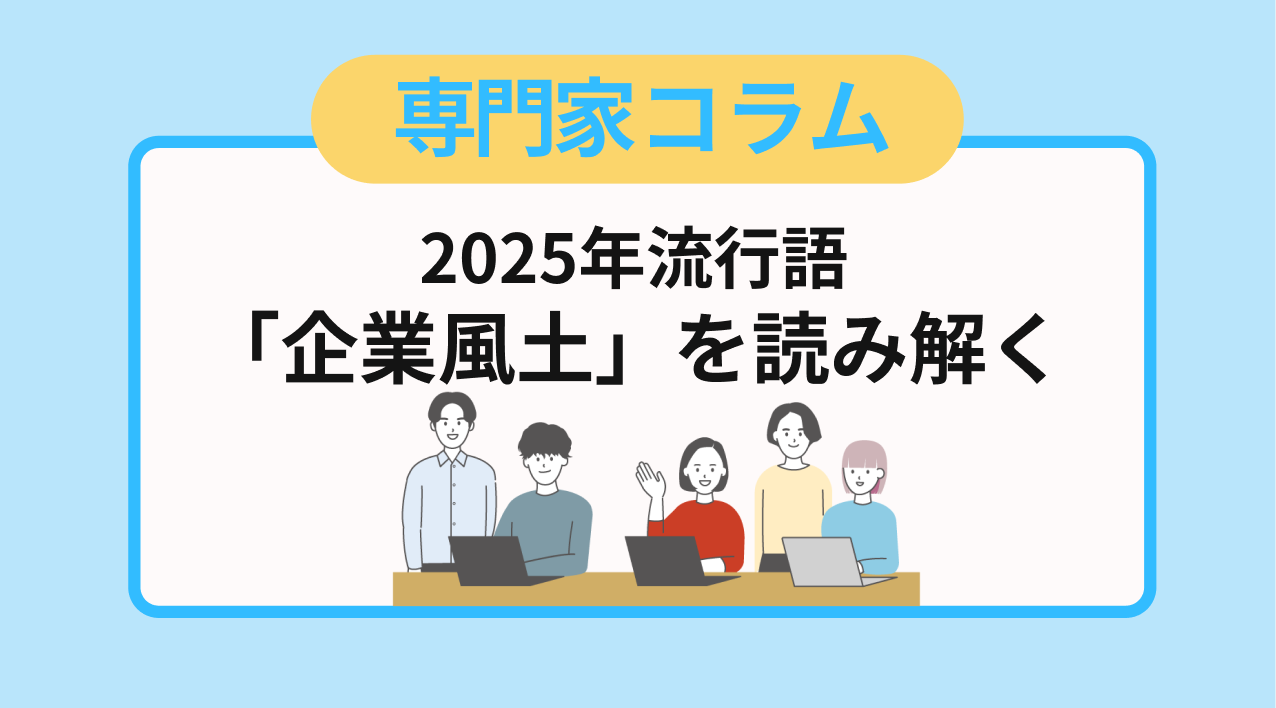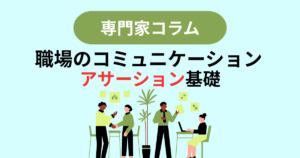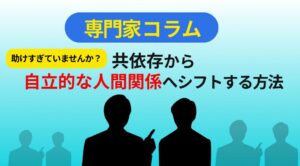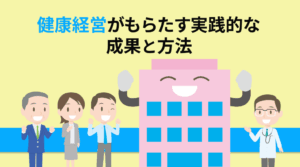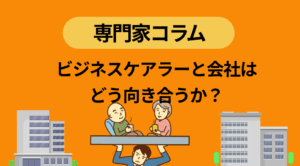はじめに
2025年の流行語「企業風土」は、組織の価値観や習慣、行動様式を映すキーワードとして注目されました。今回はこの「企業風土」をテーマに考えていこうと思います。
最初は職場に漂ういわゆる「空気」から始まります。なんとなくその場に漂っているものを感じている人も多いのではないでしょうか。単なる「職場の空気」と侮るなかれ、「空気」は固まると「風土」に成長し、「風土」がさらに固くなり「文化」になっていくと私は捉えています。どんどん固くなってしまうとなかなか変えることが難しいものです。「空気」→「風土」→「文化」となっていく職場に漂う目に見えないものについて、まずはこの「空気」とは何かを考えていくところから始めていきましょう。
「空気」の正体
コミュニケーションは、言語と非言語で構成されています。言語とは会話、非言語とは言葉以外のやり取りのことです。非言語の例としては、目を合わす、笑顔、などの表情や身振り手振りなどのジェスチャー、デスクから給湯室に移動するなども非言語コミュニケーションになります。つまり表情なども含めた行動を代表とするコミュニケーションです。
「空気」とは、非言語的な合意を指します。それは、誰も明示的に言わないけれど「こう振る舞うべきだ」という暗黙のルールということです。「~すべき」ということは、最初は程度の低いものでしょうけれど、大げさに言うと空気が固まってくると、従わなければ罰せられるということを意味するようになっていきます。そうなるともはや「空気」ではなく「風土」化したと言えるでしょう。つまり「空気」はルールなのです。
例えば「悪い空気」の例を挙げてみましょう。「会議で発言すると浮く」とか、「上司に逆らっても良いことはない」とか、「新しいアイデアが出ても『前例がない』と切り捨てられるものだ」とか、「誰も本音を言わないから自分も言わない」とか、「あきらめムードが漂っている」とか、「情報共有はあまりしない方がいい」とか、「知らない方がいいという空気がある」などがあるでしょう。「悪い空気」の具体例を整理すると、職場で何が人を萎縮させたり、やる気を削いだりするのかが見えてきますね。
この状態を放っておくと、「企業風土」になっていきます。「上司の言うことは絶対」「意見は出さず言われたことをこなすだけ」「何か起こってもここだけの話にする」「ミスはもみ消す」「会議は報告会」などが挙げられます。
つまり、「空気」とは人の想いが入り混じり作られた、形が見えないルールと言えるでしょう。それは誰かが意図的に作り出したというよりは、人々がやり取りを重ねる中で培われてきたちょっとした経験値から思いこまれた事柄の伝染なのではないかと私は思っています。つまり、誰も悪くないのに勝手にできてしまった良くない空気が「悪い空気」ということでしょう。自然発生的にできていったものと捉えます。
なぜ今『企業風土』が流行語なのか?
「企業風土」とは、企業が長年培ってきた価値観・習慣・行動様式の総体と定義されます。そして、その自然発生的に形成されたルールが、従業員の思考や行動に影響を与えているということを指します。
では次に、なぜ今年になって「企業風土」が取り出さされているのでしょうか。今までも自然発生的に「企業風土」はできていたはずです。なぜ今年になって注目を集めているのでしょうか。それは働き方改革の見直しや、人材確保の競争激化、ダイバーシティや心理的安全性の潮流、そして企業の経営課題としての「風土改革」に焦点が当たり始めていることが見受けられます。
働くモチベーションについて
モチベーションは、二要因理論から考えてみるとわかりやすいでしょう。人のモチベーションには、衛生要因と動機付け要因が大きく影響していることがわかっています。衛生要因は働くインフラのようなもので、無いと不満足を起こすものです。給料が思ったより少ないとか、ボーナスが出ないとか、サービス残業になったとか、職場の人間関係が基本的にスムーズにいかないとか、普通あるべきものが無い状態になると不満足を起こします。働き方改革はこの部分をしっかりと整えようとしてきました。
一方で動機付け要因というのは、本人の目標が達成されるとか、高い信頼関係で結ばれたチームに所属しているなど、あると増えるモチベーションです。こちらは持続力も高く、あると離職率も下がることがわかっています。
衛生要因についての制度を整えていくだけでは、昨今の少子化や人材不足の中で人を引き付けておくことができなくなってきていることを受けて、採用でも「企業風土」に注目する人が増えていることを背景に注目されていると言えるでしょう。給与や福利厚生の見直しだけでは人材を獲得する競争に勝てなくなっているというわけです。
求職者が「この会社の風土は自分に合うか」を重視するようになり、採用広報でも「企業風土」がキーワード化しています。働く人たちは、自分が長く働けるかどうかを考えるときに、働きやすさだけではなく、働きがいもほしいと考えるでしょう。両側面から「企業風土」への関心が高まっていると思います。
風土改革という視点
経営課題として向き合わざるを得ないこともあるでしょう。ハラスメントや不祥事の問題は後を絶たず、そのたびに「企業風土の問題」と報じられるケースも増加しています。経営層が「風土改革」を掲げることで、社会的に注目される言葉となっていきました。法の整備も整ってきているため、ハラスメント対策として企業には「事業主が講じる土曜管理上の措置」なども定められたことも背景としてあるでしょう。
悪い企業風土のリスク
・発言しづらい雰囲気 → 若手の成長阻害
・失敗を許容しない → 挑戦意欲の低下
・協力関係の無さ → 生産性の低下 など
まとめると、「企業風土」が流行語になったのは、制度や仕組みよりも“職場の空気”が人材定着や組織の持続可能性を決める時代に入ったからです。つまり、企業の競争力は「風土」によって左右されるという認識が社会全体に浸透したことが背景にあると言えるでしょう。
「企業風土」を変えるには
まずは「良い空気」を作っていくことを考えてみましょう。「良い空気」とはどのようなものでしょうか。安心して発言できる、協力しあえ助け合える、挑戦することを歓迎される、そのような空気が「良い空気」なのかと思います。ちなみに「悪い空気」を対比で考えてみると、沈黙が支配する、失敗を恐れる、表面的な同調ばかり…などが挙げられるでしょう。
実務的なヒント
職場の「空気」を変えるには、
・上司から率先して見えないルール(空気)を破る
・会議で意見を引き出すファシリテーションを行う(全員の意見を汲み取ることが大事)
・感謝や承認の言葉を日常的に使う
・朝礼の見直しをし、2人1組でお互いに感謝を伝えるワークを5分盛り込む など
こうした積み重ねが「空気」を少しずつ変えていきます。継続的であることも重要です。一時的に改善しても続けなければ風土が変化することはないでしょう。固まっていればいるほど、変わらなさは強いと言えます。
良い企業風土がもたらすもの
・従業員のモチベーション向上
・離職率の低下と人材定着
・部署を超えた協力やイノベーションの促進
・社会的評価やブランド力の強化(企業イメージ向上)
まとめ
「企業風土」は2025年の流行語として、単なる経営用語を超え、社会全体が“働く環境の質”を問う時代に入った象徴です。企業の持続可能性や人材戦略を考える上で、風土の改革は避けて通れないテーマとなっています。組織文化への関心の高まりと社会的な価値観の転換があります。
今まで個人の問題だとされてきたことが、組織の問題と捉えられるようになってきたのでしょう。個人を守り、組織を調整するといった考えは、私は肯定的に受け止めています。今までの努力至上主義や長時間労働文化が明確に終わったと感じます。
「企業文化」を見直すということは、個人個人が働くことの意味を見出す必要があることを教えてくれます。そして企業は自分の会社の「風土」を育てていく必要があるという認識を持つことがこれからの組織の鍵となっていくことでしょう。
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。