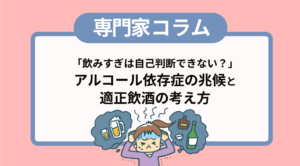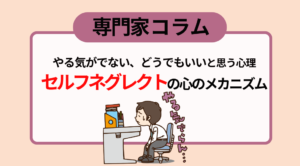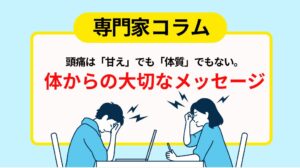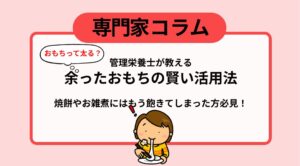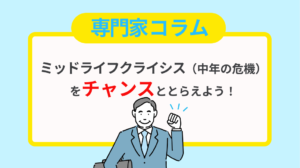朝晩はぐっと冷えるのに、日中は汗ばむような陽気。そんな「寒暖差の激しい季節」に疲れがたまって体調を崩す人も多いのではないでしょうか。気温の変化にうまく対応できず、「なんとなくだるい」「頭が重い」「肩がこる」「寝つきが悪い」といった不調が出るのは、体温調節を担う自律神経の乱れが主な原因です。そして、その自律神経の働きを支える鍵となるのが腸内環境と栄養バランスです。
今回は、寒暖差にゆるがないからだを内側からつくるための「食事のととのえ方」を、腸と自律神経の視点から詳しく見ていきましょう。
寒暖差で自律神経が乱れるメカニズム
私たちの体は体温を一定に保つようにできています。この体温調節を司っているのが自律神経です。自律神経には「交感神経(活動モード)」と「副交感神経(リラックスモード)」があり、寒いときには交感神経が優位になり血管を収縮させ、熱を逃がさないように働きます。逆に、暑いときには副交感神経が働いて血管を広げ、汗をかいて体温を下げます。
ですが、朝晩の気温差が激しいと、この自律神経の切り替えが何度も繰り返され、神経が疲れてしまいます。例えると、冷暖房を何度もオンオフするようなものなので、体は次第に対応しづらくなり、結果として倦怠感や風邪を引いてしまうなど体に不調が現れるのです。
腸と自律神経はお互い影響しあう
自律神経の働きを安定させるために重要なのが腸内環境です。腸は「第2の脳」と呼ばれるほど、神経ネットワークが発達しており、脳と密接に情報交換をしています。この関係は「脳腸相関」とも呼ばれ、腸の状態が自律神経やメンタルに大きく影響することが分かっています。
セロトニンというホルモンを聞いたことはあるでしょうか。このセロトニンは「幸せホルモン」ともよばれ腸から約90%作られます。
善玉菌が優勢で腸内環境が良いと、セロトニンの分泌がスムーズになり、自律神経や心の状態も安定しやすくなります。逆に、悪玉菌が優勢になり腸内環境が乱れるとセロトニンの分泌も滞り、気分が優れず、また体の不調が現れやすくなってしまいます。
寒暖差にゆるがない体をつくる栄養素と食材
ここからは寒暖差にからだが順応できるようカギとなる「腸内環境」と「自律神経」をサポートする栄養素と食材についてご紹介していきます。
ポイント①腸内環境を整える「発酵食品」と「食物繊維」
善玉菌を増やす発酵食品
→ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなど
善玉菌のエサになる水溶性食物繊維
→果物・こんにゃく・わかめ・里芋など
以前は生きたまま届く菌が良いと言われていましたが、最近の研究では、「生きた菌」だけではなく、「死んだ菌」でも腸内環境に良い影響を示すものが出てきています。生きた菌にこだわらず食事に取り入れやすいものを食べるようにしてみてください。
ポイント②セロトニンの材料となる「トリプトファン」
セロトニンはトリプトファンというアミノ酸からつくられます。このトリプトファンは体の中で作ることができないので食事からとる必要があり「必須アミノ酸」と呼ばれています。
トリプトファンを多く含む食品
→鶏肉・鮭・大豆・卵・乳製品・ナッツなど
効果的に摂るコツ!
朝食で摂るのがおすすめ!
朝にトリプトファンを多く含む食品を食べると、日中にセロトニンが活性化し、夜に自然な眠気を促すメラトニン生成につながります。夜なかなか寝付けず翌朝に疲れが残っているといった方に効果的なとり方です。朝にヨーグルトを食べる習慣をつけるのが毎日取り入れやすく続けやすいですね。
ポイント③ストレスをやわらげる「マグネシウム」と「カルシウム」
寒暖差は体にとってストレスです。その影響を和らげるためには、神経の興奮を抑える働きのあるミネラル類が大切です。
マグネシウム
→ほうれんそう、大豆製品、ごま、バナナなど
カルシウム
→小魚、牛乳、チーズ、ヨーグルト、小松菜など
「腸と自律神経をととのえる」こんだて例
寒暖差にゆるがないからだを作るには、特別な食材よりも自分が取り入れやすい食材を使った食事を食べるという「日々の継続」が大切です。
ここからは簡単に作れる献立例をご紹介いたします。
ある1日のこんだて
- 朝食:納豆ごはん+味噌汁+バナナヨーグルト
おみそ汁は晩の残りもので朝の時短に - 昼食:玄米+鶏の照り焼き+ほうれん草のごま和え+ひじきと大豆の煮つけ
副菜は多めに作ってお弁当用にストックしておくと楽
- 夕食:鮭のソテー+厚揚げのチーズトースト焼き+きのこのポタージュ
スープでお腹の内側からじんわり温める
おすすめレシピ
かぶとさけのほっこりスープ

おすすめポイント!
消化を助ける秋食材のかぶとトリプトファン・カルシウムも取れるこの季節におすすめの温かいスープ。きのこのビタミンDはカルシウムの吸収を促進してくれます。
1人前
<材料>
- かぶ・・・1/2株
- 生鮭・・・1切れ
- しめじ・・・1/12株程度
- 固形コンソメ・・・1/2個
- オリーブオイル・・・大さじ1
- 水・・・200cc
- 牛乳・・・100cc
- しお・こしょう・・・少々
<作り方>
- 生鮭に軽く塩をふり10分置いて、出てきた水分はキッチンペーパーで拭く。
- しめじの軸を切り、かぶを8等分のくし切りに。
- 鍋にオリーブオイルをいれ、①の生鮭を皮目から焼く。
- 両面色付いたらいったん取り出す。
- 同じ鍋に②を入れ炒める。
- 水・固形コンソメ、焼いた鮭を戻しいれる。
- ふたをして中火で10分煮込む。(かぶが柔らかくなるくらいまで)
- 牛乳を入れ、しおこしょうをふる。(牛乳を入れたら弱火で沸騰させないように)
生活習慣にプラスα
寒暖差にゆるがない体をつくるには、食事だけでなく生活リズムを見直すことでさらに相乗効果を発揮します。
- 朝はカーテンを開けて自然光を浴びる
→ 体内時計がリセットされ、セロトニンの分泌が促されます。 - 夜は湯船に浸かる
→ 副交感神経が優位になり、深い睡眠がとりやすくなります。 - 通勤時に一駅分歩く・階段を使う
→ 適度な運動は腸の動きを活発にします。
まとめ
寒暖差によるからだの不調は、体温調節を担う自律神経の疲れから生じます。
そして、自律神経を安定させるカギは「腸と栄養バランス」。
- 発酵食品と食物繊維で腸をととのえる
- セロトニンの材料とミネラルで神経の働きをサポートする
- 生活のリズムをととのえる
この3つを意識するだけで、寒暖差にゆるがないからだへと整っていきます。
まずは寒い朝の時間帯に温かいおみそ汁を一品朝食にプラスするなど取り入れやすいところから始めてみませんか。
忙しい毎日の中でもゆっくり深呼吸することも大事な時間にしたいですね。
<参考文献>
「きちんとわかる栄養学」飯田薫子、寺本あい、西東社出版2022年
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。