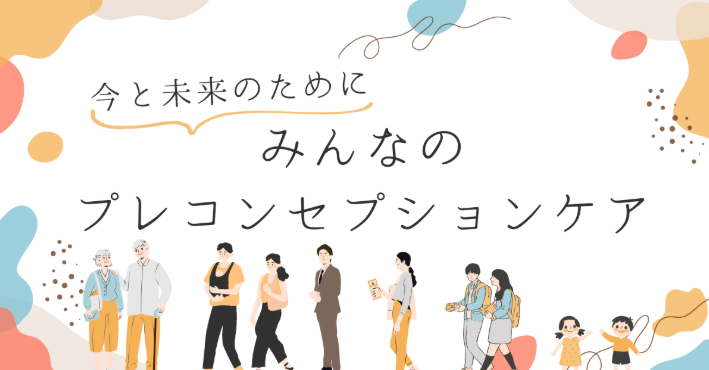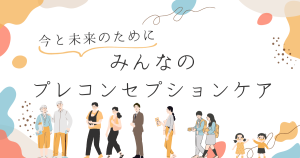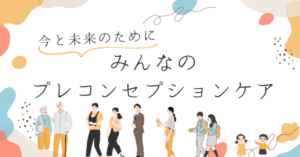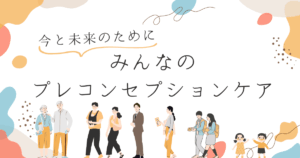皆さんは『インターコンセプションケア』という言葉をご存じでしょうか?このインターコンセプションケアは、『女性およびその次のお子さんの健康転帰を改善するために、妊娠と妊娠の間に母親に提供されるケア』として、産後ケアと次の妊娠に向けてのプレコンセプションケアを含む連続したケアを指します。
産後、ご自身の体調の回復やお子さんのお世話で忙しい日々を過ごしている方にとっては『もう次の妊娠に向けて考えなきゃいけないの?』と思うかもしれません。寝不足が続き、不安や戸惑いを抱えながらの育児は本当に大変で、自分のことどころではない状況かもしれません。しかし、妊娠・出産・産後の経験を経て、ご自身やお子さんの健康管理のために何ができるのか、今後のライフフプランも含めて少しずつ考えていくことは、あなたやご家族の健康への投資とも言えます。
また、今後妊娠を希望しているかどうかに関わらず、産後ケアをどのように進めていくかは、健康維持にも役立ちますので、ぜひ一緒にプレコンセプションケアとインターコンセプションケアについて考えてみましょう!
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
お母さんの心身の回復と育児
さまざまな理由から最近では里帰り分娩ではなく、カップルお二人で産前産後を過ごすことも少なくありません。しかし、パートナーのサポートがあったとしても出産で負担のかかった身体で赤ちゃんのお世話をすることは、大変なものです。現在、各自治体が中心となり出産後1年以内のお母さんと赤ちゃんに対して心身のケアや育児サポートなどを行い、産後も安心して過ごせるよう産後ケア事業が行われています。日帰りもしくは宿泊の産後ケアを受けられたり、産後ヘルパーサービスなどもありますので、お二人だけで頑張り過ぎず、これらを活用するのも良いと思います。
また、産後の回復状況は人それぞれ違いますし、育児ではわからないことや不安に思われることも多いと思います。産婦人科や小児科、地域の子育て支援の保健師などお二人の子育てを応援している窓口はいろいろありますので、「相談しても大丈夫かな?」と思わず、遠慮なく相談してみてくださいね!
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
妊活・妊娠・出産・産後の経過を振り返る
産後の心身の回復を図りながら次にとりかかるのは、ご自身の妊活・妊娠・出産・産後の経過を振り返ることです。この約10ヶ月間の中で、妊活をされていた方はその期間も含め、痩せや肥満、糖代謝異常、排卵障害や黄体機能不全、抗リン脂質抗体症候群などの不妊症や不育症の原因と考えられるもの、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群、早産や胎児発育不全など妊娠中の合併症、常位胎盤早期剝離や帝王切開など経腟分娩以外の出産など、症状の程度を別として何らかの問題はなかったでしょうか?これらの問題があった場合には、次の妊娠に至った場合にも同様の経過を辿る可能性があります。つまり、何が原因であったのかを知り、予防に向けて妊娠する前から心とからだを整えていくことは、次の妊娠を安全に過ごすことにつながっていくのです。ご自身の今回の経験を振り返り、診察や助産指導の中で受けたアドバイスを親子手帳などの記録を元にぜひ振り返ってみてください。また、何らかの既往疾患をお持ちの方は、今回の妊娠経過や産後の急激なホルモンバランスの変化の中で疾患の増悪がなかったのかも含め、定期的なフォロー受診を継続しながら、次の妊娠のタイミングも確認していきましょう。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
原因から考えるリスク
今回の妊活・妊娠・出産・産後の経過を振り返り、何らかの問題があった場合は、原因から考えられるリスクを知り、そのリスク毎の改善策をできる範囲で取り入れていきましょう。
<やせ>
日本ではBMI(体重/(身長)2×10000)が18未満を『やせ』と定義しています。やせの場合、排卵障害など月経不順の原因になるため妊娠しにくく、また早産や赤ちゃんが小さく生まれてしまうリスクが高まることがわかっています。そして骨量や筋肉量が低いまま経過すると骨粗鬆症やフレイルのリスクが高まります。妊娠で増えた体重は、産後6~12ヶ月頃を目安として元に戻していきますが、最終的な目標には適切な体重(BMI:18.5~24.9)を目指しましょう。
<肥満>
日本ではBMI(体重/(身長)2×10000)が25以上を『肥満』と定義しています。肥満の場合、排卵がうまくいかず妊娠しにくい場合があり、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群の原因となる場合があります。また、赤ちゃんがお腹の中で大きく成長し、将来的に肥満や糖尿病になりやすいことがわかっています。また赤ちゃんが大きすぎると、産道を赤ちゃんが通れず帝王切開になったり、経腟分娩になった場合も産後の出血が多くなるリスクが高まります。そしてお母さんが将来、糖尿病や高血圧症、脂質異常症になりやすく、脳心血管病のリスクや、関節・脊椎の変形のリスクが高まるという報告もあります。
産後の急激な減量は危険ですが、まずは産後6~12ヶ月頃を目安として元に戻していき、次の妊娠前に適切な体重(BMI:18.5~24.9)を目指しましょう。
<妊娠糖尿病・糖代謝異常>
妊娠中や妊活中に診断された方は、その際にかかっていた病院で産後3ヶ月以内に糖負荷検査もしくは血糖などの糖代謝に関する検査を受けてみましょう。
妊娠糖尿病の場合は出産すると血糖が正常に戻ることが多いですが、産後5年時の2型糖尿病進展率(糖尿病になっている確率)は、妊娠糖尿病ではなかった群が1%に対して、妊娠糖尿病であった群は20%という報告もあり、将来の糖尿病や脳心血管病のリスクが高まることがわかっています。
また産後の75g糖負荷試験で境界型と診断された方や妊娠前もしくは産後の現在でBMIが25以上の方、妊娠中にインスリンを打つ必要があった方、ご兄弟やご両親のいずれかに糖尿病の方がいらっしゃる方は、糖尿病のリスクが高いため注意が必要です。
産後も定期的な血糖などの検査を受けながら、適切な体重(BMI:18.5~24.9)が維持することを目指しましょう。
<妊娠高血圧症候群>
高血圧症とは、診察室で繰り返し測った血圧が140/90mmHg以上の場合を指します。妊娠高血圧症候群になった女性群は、産後5年時ですでに6人に1人の割合で高血圧症を発症しており、その頻度は妊娠高血圧症候群にならなかった女性群に比較すると約6.4倍だったという報告もあります。
高血圧症になると、将来の脳や心臓、血管の病気のリスクが高くなることがわかっています。高血圧にならないよう食事の塩分や栄養バランス、飲酒や喫煙など生活習慣を見直しながら、ご家庭でも血圧を測定し記録していきましょう。病院よりもご家庭で測定する場合の方が血圧は低くなっていることが多いので、135/85mmHg以上が数日続く場合は、かかっていた産婦人科や内科を受診し相談なさってください。
<早産・胎児発育不全・常位胎盤早期剥離・妊娠10週未満の流産を繰り返す・妊娠10週以降の流産>
妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群と診断されていなくても、早産や赤ちゃんの成長が一定の基準よりも低かった(胎児発育不全)場合や、お産よりも先に胎盤が剥がれ出血し緊急帝王切開となった場合、妊娠10週未満の流産を繰り返したり、妊娠10週以降の流産やお腹の中で赤ちゃんが亡くなってしまった経験のある不育症の方(疑いも含めて)は、お母さんが将来的に脳心血管病のリスクが高まることがわかっています。
妊娠中や出産時に何らかの検査異常を指摘された場合は、産後3か月以内に状態を確認してもらいましょう。
また繰り返す流産や死産を経験された方の中には、通常よりも血液が固まりやすかったり、抗リン脂質抗体症候群などの病気を持たれている方もいらっしゃいますので、1度習慣性流産や不育症の専門医にご相談ください。
いずれの場合も生活習慣病の予防とされる規則正しい生活と栄養バランスのとれた食生活、適度な運動が基本となります。大変な時はお店のお惣菜を取り入れたり、産後ヘルパーを活用して家事を手伝ってもらったり、全部お二人でやろうとせず、サポートを得ながら無理のない範囲で進めてくださいね。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
今後のライフプランを考える
女性の場合、年齢の上昇に伴い妊娠しにくくなり、妊娠しても流産する確率が高まり、また妊娠中やお産の時のリスクも増加することがわかっています。また、35歳以上をさす高年妊娠では21トリソミー(ダウン症)を含む染色体の問題による先天性疾患児の出生率も増加することから、早めに次の妊娠を考えるカップルもおられると思います。
しかし、妊娠・出産・産後で疲れたお母さんの心身を回復し、次の妊娠に向けて準備していくために、WHOでは産後18~24ヶ月あけてから次の妊娠をすることが理想としており、日本でも12ヶ月、少なくとも6ヶ月以上はあけることが推奨されています。またお産が帝王切開となった場合は、1年以上あけることが推奨されています。
産後から次の妊娠までの期間が6ヶ月よりも短い場合には、お母さんの年齢に関わらず、早産・赤ちゃんの低出生体重・お腹の中の赤ちゃんや生まれた赤ちゃんの異常・母体異常のリスクが高くなるという報告もあり、早すぎる次の妊娠は、お母さんにとっても次に迎える赤ちゃんにとっても、そして見守るご家族にとっても望ましいものではありません。
妊活を乗り越えてのご出産だったり、ご自身の年齢から次の妊娠を焦る気持ちもあるかもしれませんが、ご自身と大切なお子様の健康や安全のために、産後12ヶ月(少なくとも6ヶ月)はしっかりと心身を休ませ、赤ちゃんとの時間を楽しんでください。
そして、産後の悪露が落ち着いた後も、ホルモンバランスの変化や母乳分泌の影響から月経が回復するまでの期間は人それぞれ違います。また、月経が来ないからといって、排卵していないとは限らず(排卵後に月経はくるので)、産後健診で性交渉の許可が下りた場合、避妊しないまま性交渉を行うと予期せぬ妊娠に至る場合があります。その場合は望まない選択をせざるを得ない可能性もありますので、お二人でしっかりと次の妊娠のタイミングを考え、それまでは必ず避妊をしてください。
お二人の中で、お子さんは何人欲しいのか、一番下のお子さんが生まれた時にご自分たちは何歳ぐらいまでなら大丈夫なのか、その時のお二人の年齢や健康状態、仕事・保育などを含めた環境、経済力など色々な面から一緒に今後のライフプランを考えてみてくださいね。
そして、次の妊娠を望まれる際に、何らかの不妊治療が必要だと思われる場合や、凍結胚の移植を考えている方、不育症治療が必要な方は、妊娠に向けてスケジュールを組んだり、何らかの処方が必要な場合があります。妊娠を希望されるタイミングよりも前にかかりつけの病院へ事前にご相談ください。母乳をあげている方は早めの断乳を考えるかもしれませんが、必ずしも断乳しないといけないわけではありませんので、お子さんの状況も含め、断乳すべきかもご相談ください。
妊娠・出産・産後の経験を経て、お母さんや次のお子さんを希望される際に必要なことなど多くの情報が得られたと思います。その情報を活用し、今後に活かしながら健康管理を進めることがインターコンセプション/プレコンセプションケアです。今回のお話がお二人で今後についてお話されるきっかけになれば嬉しいです。
<引用・参考文献>
・「妊娠を起点とした将来の女性および次世代の糖尿病・メタボリック症候群予防のための研究」、厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業、平成24年~26年度 総合研究報告書(研究代表者 荒田尚子)
・「女性における生活習慣病戦略の確率―妊娠中のイベントにより生活習慣ハイリスク群をいかに効果的に選定し予防するか」、平成21~23年度厚生労働科学研究費補助金循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業
・産後ケア事業について 第4回こども家庭審議会成育医療等分科会 資料2-1
こども家庭庁成育局母子保健課
・インターコンセプションケアプログラム開発のためのパイロットスタディ 令和4年度厚生労働科学研究費補助金「生涯を通じた健康の実現に向けた「人生最初の1000日」のための、妊娠前から出産後の女性に対する栄養・健康に関する知識の普及と行動変容のための研究」 研究報告書
・Laura Schummers, Jennifer A. Hutcheon, Sonia Hernandez-Diaz, Association of Short Interpregnancy Interval With Pregnancy Outcomes According to Maternal Age. AMA Intern Med, 2018;178;(12):1661-1670.
「プレコンセプションケア」を推進したい方へ
妊娠前から始める健康管理「プレコンセプションケア」取り組みのご相談が可能です。プレコンセプションケアの実践をサポートする多様なサービスを提供し、個人向けにはオンライン相談や卵巣年齢チェック、性教育授業を、自治体・企業・教育機関向けには理解促進と行動変容を後押しする効果的な情報発信支援をご提案します。

1. 個人向け多様なサービス提供
オンライン相談、卵巣年齢チェック、動画配信、性教育授業など、お一人おひとりのニーズに合わせた幅広いサービスを展開しています。
2. 組織向け理解促進・行動変容支援
自治体・企業・教育機関に向けて、プレコンセプションケアの普及啓発と実践的な行動変容をサポートします。
3. 効果的な情報発信・啓発活動
オンラインセミナー開催支援、SNS運用サポート、リーフレット等の啓発ツール活用で効果的な情報発信をご提案します。