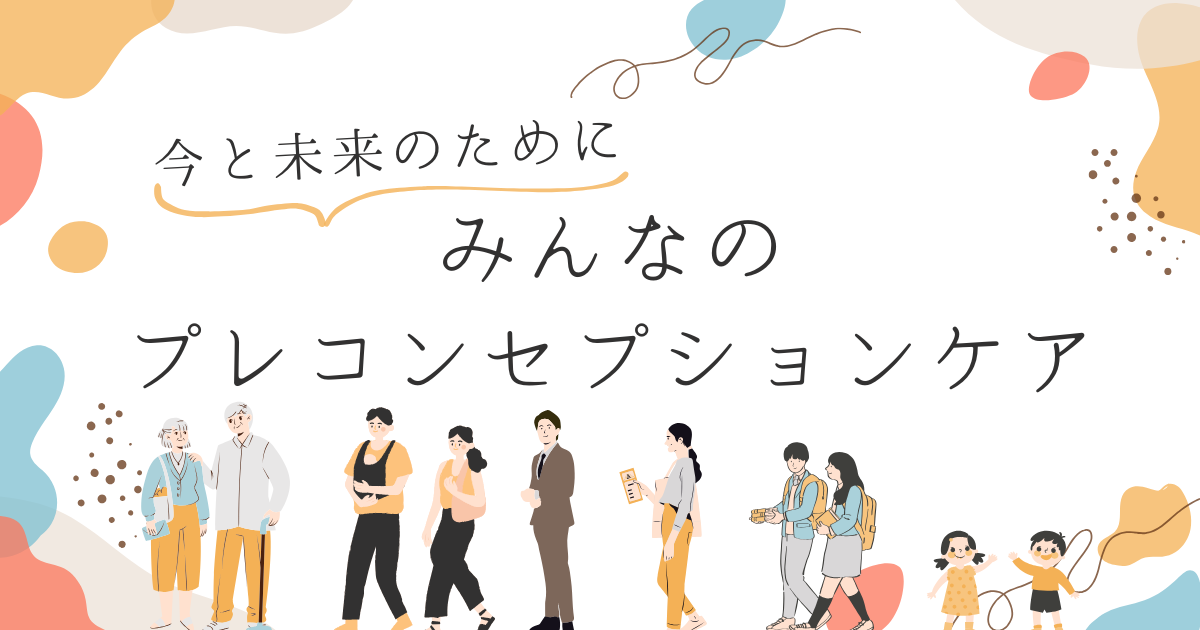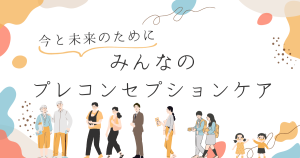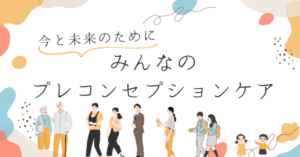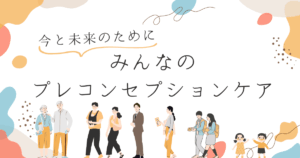はじめに
皆さんこんにちは。胚培養士の川口 優太郎です。
今回は、近年話題の『プレコンセプションケア;Preconception Care』についてのお話しです。
赤ちゃんを授かる前・妊娠する前の健康管理のことをプレコンセプションケアといいますが、このプレコンセプションケアというワードを聞くと「女性のためだけのものなのではないか?」と考える方が多いのではないかなと思います。
実際に私のクリニックでも、ブライダルチェックや妊活に向けた初期スクリーニング検査を目的として、女性だけがおひとりで来院されるというケースも非常に多いです。
確かに、女性向けのキャンペーンが多く、メディアやSNSなどで取り上げられる機会も増えてきてはいるのですが、しかしながらプレコンセプションケアという意味の中には、女性のことだけではなく、
・男女ともに安全で衛生的な妊娠のために健康管理や準備を行うこと
・パートナーや家族の健康状態の向上をサポートすること
・将来的に親としてパートナーや子どもを保護するための準備を行うこと
も含まれています。つまり、本来プレコンセプションケアは、女性だけのものではなく男性にとっても非常に重要なものであるわけです。
近年の研究では、女性だけでは無く男性側の健康状態も、産まれてくる児のリスク(早産、低体重出生児、先天性疾患)に影響を与えることが数多くの学術研究から報告されているため、将来、安全で健康で衛生的な妊娠を迎えるためには、男性も積極的に行動を起こしていかなければなりません。
今回のコラムでは、男性側のプレコンセプションケアに焦点をあてて詳しく解説をしていきたいと思います。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
ライフプランニングを行うことの重要性
まず、将来的に子どもを持つことを望んでいる場合には、男女ともに妊娠・出産を意識したライフプランニングを行うことが極めて重要です。理由は実に明確で、妊娠・出産には適齢期(タイムリミット)があるためです。
女性の妊娠率は年齢とともに顕著に低下していきます。より詳しく数字で示すと、
◆20代~34歳では、一周期あたりの妊娠率は約25~35%以上
◆35~39歳では、一周期あたりの妊娠率は約15~20%
◆40~42歳では、一周期あたりの妊娠率は5~10%未満
◆43歳を超えると、一周期あたりの妊娠率は5%未満
となります。
この数字は“妊娠率”であるため、実際に出産まで辿り着く確率はこれよりもさらに低くなります。そのため、自身だけではなくパートナーの年齢も考慮しながら妊娠・出産を意識し、“いつまでに”、“どのように”、“どのくらい”、といったライフプランニングを行う必要があります。
また、このような人生設計は自身のキャリアを形成する上でも同様です。
例えば、「△△のポジションに就きたい」「〇〇のプロジェクトをやりたい」「□□の資格を取りたい」と考えた時に、
①いつまでに(30歳までに。入社後●●年以内に。など)
②どのように(外国語のスキルを上げる。■■の資格を修得する。など)
③どのくらい(1年間勉強する。▲▲万円までかける。など)
といった具体的な目標を立て、そのスケジュールに沿って計画を進めていくことは非常に大事です。
プレコンセプションケアでは、自分自身のキャリアや、目標や、価値観だけではなく、パートナーの年齢や、意思や、理念も一緒に共有しながらライフプランニングを行うことが不可欠であり、漠然と「いつかは子どもが欲しいなぁ‥‥」と考えているだけでは、結果的に適齢期を逃してしまい、赤ちゃんを授かることが難しくなってしまう可能性も十分にあります。
私自身、生殖医療の現場で胚培養士として15年以上のキャリアの中で不妊症に悩む数多くの患者様を受け持ってきましたが、「もっと早く妊活に取り組んでおけばよかった」と後悔される患者様や、年齢面や費用面での理由から、結果的に子どもを持つことあきらめざるを得なくなった患者様も決して少なくありません。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
プレコンセプションケア:3つのカテゴリーより
では、男性のプレコンセプションケアについて、具体的にはどのようなことに気を付けていけばいいのでしょうか?
アメリカ疾病予防管理センター(CDC)とアメリカ家庭医学会(AAFP)では、プレコンセプションケア;Preconception Careに関する取り組みとして、後述の通りチェックリストを公表しています。
男女ともにライフプランニングを行う上では、このようなチェックリストを参考にして計画を立てていくことも強く推奨されています。
このチェックリストで公表されている項目は大きく、
1.健康状態の確認と健康の最適化
2.ライフスタイル・生活習慣の最適化
3.精神的な健康と社会・環境の最適化
という3つのカテゴリーに分けられており、各カテゴリーからさらに差分化されたチェック項目がリスト化されています。
健康状態の確認と健康の最適化
(1)医療従事者への相談:
安全で、衛生的で、健康的な妊娠に向けて、ご自身だけでなくパートナーとともに、現在の健康状態、過去の病歴、投薬(服用歴)、予防接種などについて話し合える医療従事者を確保しましょう。勤務先で産業医に相談が出来るような制度が整えられている場合には、このような制度を積極的に活用していきましょう。
(2)生活習慣病、慢性疾患等の評価:
心臓、脳、血管、肥満などの他、甲状腺やアレルギー性疾患などの慢性疾患、生活習慣病は、妊娠に直接的な影響を及ぼす可能性があり、妊娠中、産後、胎児へのリスクが増加します。また、男性では造精機能に影響を与え、精子の数や運動性、質の低下につながる恐れがあります。
(3)常用薬とサプリメント:
常用薬やサプリメント、過去の服用歴には、造精機能や精子の質に影響を与え、妊娠を阻害する可能性や妊娠中の児のリスクを増加させる可能性がある薬剤も数多く存在します。かかりつけの医師や薬剤師と相談しながら、妊娠前に調整する、または中止する必要がある薬やサプリメントを特定しておきましょう。
(4)適切なワクチンの接種:
風疹や麻疹、おたふくかぜなどは、妊娠中の流産・死産などのリスクを増加させるほか、妊娠中に風疹ウイルスに感染すると胎児に難聴、白内障、心疾患などを引き起こす可能性が著しく高くなります。また水痘(水疱瘡)は、妊娠中に予防接種を受けることができないため、過去に罹患歴が無い場合には妊娠の前に摂取するようにしておくようにしましょう。
(5)感染症の検査:
梅毒は、早産・流産・死産の原因となるほか、クラミジアは、妊娠初期に感染すると流産・死産につながる危険性があります。また淋病は、新生児結膜炎を起こして失明する可能性があります。いずれも、自覚症状がなく知らずに感染しているケースも臨床では多くみられます。自身が感染しないことはもちろん、パートナーを感染させないことが重要です。
(6)遺伝カウンセリングの検討:
自身に染色体または遺伝子の異常による疾患や、家族に遺伝病歴がある場合には、専門の医療従事者による遺伝カウンセリングを受けることが推奨されています。特に、Y染色体微小欠失は、重度の男性不妊を引き起こす要因の一つですが、子ども(男児の場合)に遺伝する可能性があるためリスク等をあらかじめ十分に把握しておく必要があります。
ライフスタイル・生活習慣の最適化
(1)適正体重の把握・評価・維持:
過度な痩せ型や肥満は、生殖能力に影響を及ぼし、不妊症の直接的な要因となるほか、妊娠経過におけるリスクを増加させます。パートナーとともに、BMIに基づいた適正体重を把握し、現在の体重の評価ならびに維持を行いましょう。 BMIが18.5未満、または25以上ある場合には、適切な医療機関で栄養指導や健康指導を受ける必要があるとされています。
(2)必要な栄養素、サプリメントの摂取:
特定の栄養素の過不足は、造精機能や精子の質に影響を与え、不妊症の直接的な原因となるほか、胎児の発育にも大きな影響を与えます。特に女性では、胎児の神経管閉鎖障害の予防に重要な葉酸はサプリメントによる摂取が推奨されています。
(3)バランスの取れた食事:
偏りのある食事は、卵子・精子などの生殖細胞に影響を与えるほか、男性では造精機能を障害させる可能性があります。野菜や果物、穀物を中心に、魚介類や脂肪の少ない赤身肉のタンパク質、脂肪分の少ない乳製品を中心に摂取するようにしましょう。
(4)カフェイン摂取の制限:
過剰なカフェイン摂取は生殖細胞に影響を及ぼす可能性が指摘されているため、適度な摂取(※1日あたりの摂取上限目安;200mg以下(≒コーヒー2杯程度))を心がけましょう。エナジードリンクなどの成分表示には100mlあたりの濃度が記載されているため、缶1本だけでカフェイン濃度が200mg近くなるものも多いため特に注意が必要です。
(5)アルコール摂取の制限:
アルコールの過度な摂取や、少ない量であっても長期的な摂取によって、精子の運動性の低下やDNA損傷を引き起こし、不妊症の原因となる可能性が報告されています。
(6)喫煙(タバコ)の制限:
喫煙は、健康状態そのものに極めて大きな影響を及ぼし、また副流煙は、様々な疾病の直接的な原因となることが指摘されています。副流煙に暴露された妊婦は、流産、早産、低出生体重児となる確率が20~30%以上高くなることが示されています。
(※飲酒・喫煙が止められない場合には、医師や専門の医療機関、あるいは地域の保健センターなどに早い段階で相談することが推奨されています。)
(7)定期的な運動習慣:
適度な運動は生活習慣病の予防と改善に効果的であるとされており、健康で衛生的な妊娠のためにも非常に有益です。一方で、精子は熱に弱い性質があり、精巣の温度が高くなると造精機能が障害されてしまうため、座った姿勢で長時間行うサイクリング、筋力トレーニングのほか、高温環境で行うホットヨガ、また長時間のサウナや入浴などは避けるようにしましょう。
(8)口腔の健康改善:
妊活中・妊娠中は、ホルモンバランスの変化などにより口腔内の環境が悪化しやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まります。妊娠する前の口腔ケアは、妊娠中のトラブルを予防し、健康で衛生的な出産を迎えるために非常に重要です。また、キスや食器を共有することでも虫歯の原因となる菌がカップル間で感染することがあるため、妊活を始めたら、パートナーとともに揃って歯科検診を受け、必要であれば治療を済ませておくことが推奨されます。
(9)化学物質・環境毒素への曝露の制限:
いわゆる環境ホルモンである内分泌かく乱化学物質や、工業用化学品、農薬、PCBなどの有機塩素系化合物、フタル酸類などは、精子形成を阻害する可能性や精子DNAの損傷、精子の運動性低下などを引き起こし、男性不妊の原因となる可能性が報告されています。
精神的な健康と社会・環境の最適化
(1)家族計画について話し合う:
「妊娠したい」「子どもが欲しい」という目標について、カップル間で相違が無いかどうか。本当に子どもが欲しいならば、いつまでに欲しいのか、それを達成するためには何をしたらよいか、どのような準備が必要なのか、を具体的に話し合い、“個人”ではなく“2人(または家族)”の意思が一致していることがとても重要です。また、計画通りに進まなかった場合に起こりうる課題についても考慮しておくことが望ましいでしょう。
(2)ストレスコントロール:
安全で、衛生的で、健康的な妊娠のためには、精神面での健康も非常に重要な項目になります。家庭環境、職場環境など日常生活の中でどんなことにストレスを感じやすいかを認識し、趣味の時間を持つ。家族と過ごす。運動をする。ヨガや瞑想などを実践してみる。など、ストレスを軽減させるための自分なりの対処方法を見つけることが必要です。
(3)社会的支援の評価:
お住まいの都道府県あるいは市区町村で、妊活や妊娠、出産、育児などについてどのような支援サービスがあるのか、また相談が出来る保健センターや子育てサロン、公民館などの環境があるのかを調べておきましょう。家族が生活する環境、地域の情報・状況を知ることで、出産、育児、教育における選択肢を増やしておくことが家族のQOL向上につながります。
(4)DV、モラルハラスメント、ネグレクトの可能性と評価:
自身またはパートナーによる暴力やハラスメントに関連するあらゆる問題をスクリーニングします。暴力的な行動やハラスメントを、受けてしまう場合でも与えてしまう場合でも、その背景にはストレスや心理的な問題、あるいは精神疾患や発達障害が関連しているケースも多いため、必要に応じて精神科や心療内科を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
(5)財政状況の見直し:
妊活、妊娠、出産、子育てに関わる具体的な費用をあらかじめ考慮した上でライフプランニングを行うようにしましょう。また、利用できる制度や助成金についても詳細に調べておくことで、精神的あるいは経済的な負担を減らすことにつながります。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
アンコンシャス・バイアスを失くすことの必要性
アンコンシャス・バイアスとは?
さて、上記のリストを参考にして、プレコンセプションケアに取り組んでいく上で、一つの大きな概念として重要となるのが、『アンコンシャス・バイアス(Unconscious Bias)を失くす』ということです。
アンコンシャス・バイアスとは、日本語では「無意識の思い込み・偏見」などと訳されますが、過去の経験や受けてきた教育、周囲の環境などから、無意識のうちに形成された、自分だけでは気付きにくい偏りのあるものの見方や考え方のことを指します。
例えば、プレコンセプションケアにおいては、「女性は〇〇するべきだ!」、「男性は□□であるべきだ!」といった固定観念や決めつけが挙げられます。代表的なもので言えば、日本には未だに『男は仕事、女は家庭』という意識が根深く残っていますが、このような古びた考え方もアンコンシャス・バイアスによるものです。
偏った思い込みが妊活・妊娠を困難にする
アンコンシャス・バイアスは、職場や家庭など、日常生活のありとあらゆるシーンで直面することがあり、これに気がつかないと、知らず知らずのうちにパートナー傷つけてしまったり、ライフプランニングが本来持っているはずの選択肢や可能性の範囲を極端に狭めてしまったりすることがあります。
実際に、私がこれまで臨床で接してきた患者様を例に挙げると、「子どもが出来ないのは女性の問題!」、「俺は病院に行かなくても大丈夫!」という偏った思い込みや主張から来院を拒否し、ようやく先生が説得して検査を受けてもらったら、男性側に不妊の原因があった‥‥というケースが数多くあります。
またよくあるのが、「友人はタバコを吸っていても子どもが出来たからタバコは関係無い!」、「俺はやめるつもりは一切ない!」、「禁煙なんて無理!」とおっしゃる患者様です。
先述した通り、喫煙は、喫煙者の健康状態そのものを害するだけでなく、副流煙に暴露されるパートナーの健康も著しく害します。加えて、パートナーが妊娠中の場合は胎児の健康も害し、流産、早産、低出生体重児となる確率が顕著に高くなることが示されているため、プレコンセプションケアにおいて禁煙は必須の項目でもあります。
現に、このような偏見を持ってしまったがばかりに、自分たちの思い通りに計画を進められなくなってしまった患者様は実のところ数えきれないほど多いです。
将来、“親”になる準備のために
このように、アンコンシャス・バイアスに気づき、意識をすること、そして多様な考え方や価値観を受け入れることがプレコンセプションケアにおいては非常に重要なのですが、ただし一方で、時にはパートナーの意見を尊重するだけではなく、ざっくばらんに率直に話し合うということも必要です。
特に「子どもが欲しい」という希望が、カップル間で本当に共通しているものなのか?同じ価値観を持っているかどうか?は、将来生まれてくる児の保健衛生(※生きていく上での健康の維持・増進、病気の予防・治療、生活環境の保護など。人間が健康で安全な生活を送るための活動全般)に非常に大きく関わってくるため、噓偽り無く本音で話し合う必要があります。
冒頭でも解説した通り、プレコンセプションケアには、妊娠する前の健康管理だけではなく、生まれてくる子どもの人生について、親としてやるべきことは何か?それを達成するために必要なことは何か?を考えることも含まれています。
近年では、メディアやSNSなどで『親ガチャ』(※子どもは親を選べない)という言葉も散見されますが、当然ながら親という存在が子どもの人生に与える影響は計り知れません。
>子どもの人生に責任を持つこと
>子どもやパートナーのために、適切な環境を整えて保護すること
>愛情深く接すること、そのための準備を行うこと
も、プレコンセプションケアに取り組む上ではとても重要です。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
子どもを持たない選択の受容
最後に、もしも「子どもは望んでいない」という場合には、その気持ちをしっかりとパートナーに伝えましょう。
噓偽り無く本音で話し合うという意味の中には、子どもを持たない選択をパートナーに伝えることも含まれており、プレコンセプションケア自体は、子どもを持たない選択をするカップルにも非常に有益です。
子どもを持つことが決して人生のすべてではなく、子どもを持たないという選択や家族のあり方も、当然ながら多様な生き方や価値観として尊重されるべきです。
実際に、子どもを持たない選択は、日本をはじめとする多くの国々で増加傾向にあり、社会的にも広く受け入れられるようになってきたライフスタイルであると言えます。
また、これもある種のアンコンシャス・バイアスの一つであると言えますが、日本では『名前』『血筋』『家系』という考え方や、男系・家父長制といった考え方が今もなお根強く残っており、社会通念上は“男女平等”などと謳ってはいるものの、実際には、女性が結婚することや子どもを産むことについて、男性と比較した場合に明確なハンディキャップが存在します。
現代社会においては、「少子高齢化が社会問題だ!」「異次元の少子化対策が必要だ!」「女性が子どもを産み育てやすい社会に!」という政治的あるいは社会的な圧力が、結果的に「女性は子どもを産むべき」というアンコンシャス・バイアスを生む要因にもなっています。
しかしながら、本来は『子どもを持たない選択や生き方を認める』というのが本当の多様性であり、社会のあり方であるべきはずです。そして、子どもを持つ選択・持たない選択を考えることこそがプレコンセプションケアの本質であると言えます。
もしもあなたが、「子どもをつくることは人生の意味になる」という考えを持っているなら、その考えを一度根本から疑ってみる、自分が女性なら/男性ならと考えてみる、ということもプレコンセプションケアに取り組む上では重要なのかもしれません。
【ファミワン公式】今すぐ始められるプレコンセプションケアの具体的なプログラムをチェックしてみませんか?
まとめ
今回のコラムでは、男性側のプレコンセプションケアについて解説をしてきました。
妊娠する前の健康管理とひと口に言っても、実際にチェックリストを見てみると、これまでまったく意識したことが無かったような項目がいくつもあったのではないでしょうか?
また、プレコンセプションケアは、女性だけのものではなく男性側にも取り組むべき項目が非常に多くあるということがお分かりいただけたのではないかと思います。
解説してきた通り、妊娠前の男性の健康状態も、胎児に与える直接的なリスク因子になるため、生活習慣など積極的に改善を図っていきましょう。
そして、プレコンセプションケアは健康を管理することだけでなく、パートナーとともに親になる準備を行うこと、家族の形・家族あり方を考えることでもあるということも理解をしていただけたのではないかなと思います。
安全で、衛生的で、健康的な妊娠を迎えること、そして元気な赤ちゃんを授かるためには、まずはご自身とパートナーが身体的・精神的に健康であることがなによりも重要です。
これまで、妊娠・出産に向けて特に何もしてこなかった方、あるいは何をしたらいいのか分からなかったという方、この記事を読んだ今この瞬間こそが、自分やパートナーの生活習慣の改善、健康増進に取り組みはじめる“きっかけ”なのかもしれませんよ!
参考文献
- 『不妊治療のプレコン 患者さんにはこう伝える!プレコンセプションケアQ&A』
出版:診断と治療社 編集:森本 義晴、古賀 文敏、川井 清考、太田 邦明 - 『The Art of Waiting: On Fertility, Medicine, and Motherhood』
出版:Graywolf Press 編集:Belle Boggs
CDC(アメリカ疾病予防管理センター);Planning for Pregnancy
日本産科婦人科学会;女性の健康支援 プレコンセプションケアとは
英国公衆衛生サービス(Public Health England)
英国国民保健サービス(NHS);Planning Your Pregnancy
「プレコンセプションケア」を推進したい方へ
妊娠前から始める健康管理「プレコンセプションケア」取り組みのご相談が可能です。プレコンセプションケアの実践をサポートする多様なサービスを提供し、個人向けにはオンライン相談や卵巣年齢チェック、性教育授業を、自治体・企業・教育機関向けには理解促進と行動変容を後押しする効果的な情報発信支援をご提案します。

1. 個人向け多様なサービス提供
オンライン相談、卵巣年齢チェック、動画配信、性教育授業など、お一人おひとりのニーズに合わせた幅広いサービスを展開しています。
2. 組織向け理解促進・行動変容支援
自治体・企業・教育機関に向けて、プレコンセプションケアの普及啓発と実践的な行動変容をサポートします。
3. 効果的な情報発信・啓発活動
オンラインセミナー開催支援、SNS運用サポート、リーフレット等の啓発ツール活用で効果的な情報発信をご提案します。