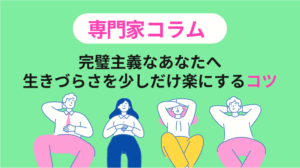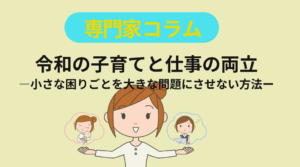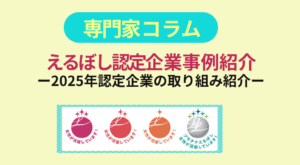はじめに
2025年7月30日、厚生労働省が発表した「雇用均等基本調査」により、日本における男性の育児休業取得率が初めて40%を超えたことが明らかになり、話題を呼んでいます。
「父親が育休をとるの?」といった時代はもう終わり、男性の育児参加が当たり前になってきていることがうかがえます。
今回のコラムでは、男性育休取得が増えた理由や今後期待されることについてまとめていきます。
当初の目標を上回る結果に。
政府はこれまで「2025年度までに男性の育児休業取得率30%」という目標を掲げていましたが、2025年7月30日に発表された令和6年度雇用均等基本調査では、取得率40.5%と目標値を大きく上回る結果となりました。

産後パパ育休制度が背中を後押し
とはいえ、2022年頃までは男性の育児休業取得率は10%台で推移していました。数年で40%とまで急増した理由として考えられるのが、2022年10月にスタートした「産後パパ育休」制度です。
この制度は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間の育休を分割して取得可能で取得中に一部就労することも可能としています。従来の制度よりも使いやすくなったことに加え、企業側の制度周知も進んだことで、取得のハードルが下がったと考えられます。
「育休取得意向確認の義務化」
また、育児・介護休業法の改正に伴い、 2022年4月から、「本人または配偶者の妊娠・ 出産等を申し出た従業員に対し、 育児休業制度等に関する周知と休業の取得 意向の確認を個別に行うこと」が義務となりました。
これまで「言い出しにくい」という課題を抱えていた男性育休が、企業側から声をかけることで取得への第一歩を踏み出しやすくなったことも取得率増加の後押しになったと考えられます。
男性育休の実態
男性育休の取得日数
さて、ここで気になるのが男性の育休取得期間だと思います。
令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査では平均46.5日*という結果も出ています。
産後パパ育休により、分割して取得可能になっているので各家庭の都合に合わせて取得期間や日数を決められることも今後の取得率上昇の後押しとなりそうです。
*回答企業(全国の従業員1,000人超のすべての企業・団体、約1400件)のうち、前事業年度に育児休業を終了し、復職した男性労働者がおり、同労働者の育 児休業平均取得日数を集計している企業(610社)における以下の計算値。
男性の育休取得は企業にもいい影響が
「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」に協力した企業に「男性育休取得率向上にに向けた取り組みによる効果」を聞くと「職場風土の改善」、「従業員満 足度・ワークエンゲージメントの向上」、「コミュニケーションの活性化」の順で回答が多い結果に。

男性育休取得は従業員だけでなく企業へも好影響を与えていることがわかります。
男性が育休を取る意味とは?
男性育休には、社会的意義だけでなく、家庭・子ども・夫婦関係にとっても多くのメリットがあります。ここでは男性も育休を取るべき理由について3つ紹介していきます。
母親の負担軽減と産後うつの予防
出産直後の母親は、ホルモンバランスの変化、寝不足、慣れない育児などで心身ともに不安定になりやすい時期です。父親が育児や家事に積極的に関わることで、母親の負担を軽減し、産後うつの予防にもつながります。
子どもとの愛着形成
出生直後から父親が育児に関わることで、子どもとの間に強い信頼関係や愛着が築かれやすくなります。特に0〜1歳の時期は、親子関係の土台をつくる大切な時期です。
夫婦間のパートナーシップ向上
育児という共通の経験を通して、夫婦のコミュニケーションが増え、チームとして協力する意識が強まります。長期的に見ても、家事・育児の分担がスムーズにいく家庭では、夫婦関係の満足度が高い傾向があります。
「パパが育休を取るべき理由と具体的なステップ」については以下のコラムでお伝えしています。
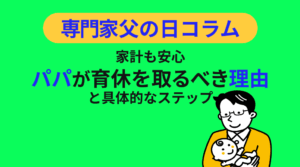
男性育休取得率以外にも期待
今後は単なる「取得率」ではなく、育休取得日数を増やせるような取り組みも必要があると考えられます。
・1週間未満ではなく、1か月・3か月といった中長期の取得を促す
・取得しやすさだけでなく、「取得後も安心して働ける」職場環境をつくる
・リモートワークやフレックス制度など、育休を取りやすく、復帰しやすい働き方の柔軟性
など企業がさらに男性育休を後押ししていくことで育児支援体制が整っていくことと思います。
おわりに
2022年からは政府も積極的に男性育休取得に向けて動いていたことによって、今回目標値を超える結果に。
取得率が40%を超えた結果は「男性も育休を取っていい」から「男性が育休を取るのは普通」へと社会がシフトしつつある兆しと見ることができます。これからの動きにも引き続き目を向けていきたいところですね。
参考文献
「2024年(令和6年)国民健康・栄養調査結果の概要」.PDF資料.2025年2月25日公表.(参照 2025‑07‑05)
厚生労働省イクメンプロジェクト. (2024). 令和5年度 男性の育児休業等取得率の公表状況調査(速報値) [PDF].(参照 2025‑07‑05)
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。