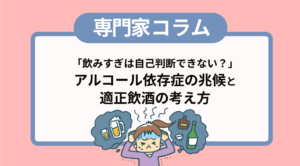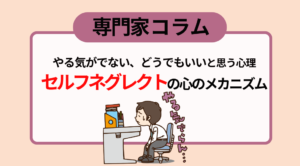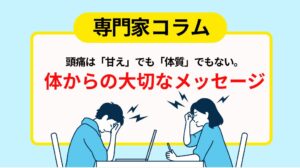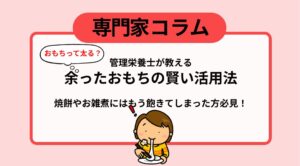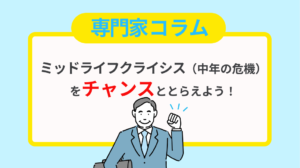はじめに
職場や家庭で完璧を目指そうとしていませんか?自分ではあまり自覚が無いとしても、本人なりに完璧でなければならないと思ってしまう人は多いのではないでしょうか。
周りからの期待に応えたい、ちゃんとやらないと落ち着かない、完璧でないと評価されないだろうと思ってしまう、でも完璧にしようしようと思えば思うほどにきちんとできないでいる、それがとてもしんどくてストレスだ、など感じていることはないでしょうか。
今回はそんな完璧主義なあなたへ、少し楽に生きる方法を見つけていくヒントを記していきたいと思っています。
なぜ?完璧にやらなければならないと思ってしまうのでしょう
職場や家庭で「完璧にやらなきゃ」と思ってしまう背景には、自己評価の低さ・失敗への恐れ・他者からの承認欲求が複雑に絡み合っています。
一つは心理的な問題として、自己評価の低さとそれに伴って自分の価値を証明したいという気持ちがある場合があるでしょう。「他人に認められたい」「期待には応えたい」など承認欲求を求めてしまう。だから頑張ってしまうというのも多くの人が抱える心情でしょう。また幼少期に「できて当り前」「失敗は許されない」という環境にいた人にとっても、完璧でないことは罪に感じてしまうようです。
また会社の風土的に「仕事でミスは許されない」「手を抜いてはいけない」という空気が流れていると、完璧に仕上げなくてはいけないというプレッシャーもあるでしょう。
もちろんちゃんと手を抜かずに仕事をすることは良いことですし、うまくいっている場合は問題ないですが、完璧でいることに疲れた人や、もう少し楽にやっていきたい人は少ししんどさを抱えているかもしれません。完璧さは固さでもあるでしょう。柔軟に対応しなくてはいけない時に固すぎることで逆に対応がうまくいかなくなっても困りますね。自分が少し楽になって、柔軟さを持った対応ができるようにするにはどうすればよいのでしょうか?考えていきましょう。
心を少し楽にするヒント
「完璧」の定義を見直す。
まずは自己理解を深めて、自分自身の「完璧」を定義しなおすと良いでしょう。
自分は何を持って完璧としているのか、いったい誰がその基準を決めたのか考えてみましょう。
「Good enough(ほどよい)」で十分だと心理学者ウィニコット氏の「ほどよい母」概念は、完璧よりも“修復できる関係”の方が大切だと説いています。「ほどよい」ことは家庭でも仕事でもちょうどよさを示しています。数値化するとしたら、完璧な状態を100点とすると、80点を目指すようにすることが大切です。80点でも価値を感じられるようになると楽になるでしょう。心の余白を作っていきましょう。そうすると柔軟な対応力も備えていけるのではないでしょうか。
余白を持つことは、実は完璧ではないが「完璧な準備」をしていることになると私は思います。
「できたこと」に目を向ける習慣をつけましょう。
完璧を目指すということは何ができていないかを探すことになっているかもしれません。
「できていないこと」を集めていくことは心にとって負担感が高いことです。「できていないこと」をチェックしていくよりも、「できたこと」に視点を置き、日々の小さな達成に気づくことが自己肯定感を育てます。「今日できたこと」を書きだすのもいいでしょう。夜寝る前に反省して寝てはいけません。睡眠の質が落ちてしまいます。睡眠はメンタルにとってとても重要な時間です。
寝る前は一日の反省をするのではなく、今日一日頑張った自分を褒め、愛で、労いましょう。夜に満足感を得ると、次の朝が充実します。気持ちの良いメンタルルーティンを作っていきましょう。
マイペース宣言をする。
人はそれぞれ違っています。自分のペースがあり、自分の達成へのプロセスがあります。
自分のペースを守り、大事に扱うことで自然に完璧すぎるところから離れていくことでしょう。自分のペースを大事にすることは、他者の基準から離れることです。自分基準を大切にすることは、自分を大切にすることです。見直していきましょう。
失敗をチャンスと捉えましょう。
失敗を恐れるのではなくて、学びの機会だと捉えると、失敗も意味が変わってきます。
よく仕事はPDCAを回すと表現されます。Pはプランを立てる、Dはやってみる、Cは検証し見直す、Aは見直して次のアクションを取ることです。このPDCAの流れは、実は失敗などないと言っているのに等しいと思います。実行してうまくいかなかったら見直してまた実行する、その繰り返しということです。失敗ではなく、次に進むためのデータが失敗によって得られたと捉えることが肝要です。そうやって失敗してもやり直すことが前提になれば、完璧主義から少し解放されていくでしょう。
間違っても見直してやり直せばいいわけですから。
「~すべき」から「~したい」へ言い換える
使う言葉を少し緩めるだけで意味が変わってきます。例えば、「〜すべき」から「〜したい」への言い換えなどです。
「ミスしてはいけない」→「丁寧に取り組みたい」言葉の使い方ひとつで、義務感から自発性へと気持ちが変わっていくことでしょう。自分の気持ちにフォーカスした言葉に整えると、メンタルは少し落ち着くと思います。自分の気持ちを受けとめるだけでも、気持ちが楽になるでしょう。
職場での完璧主義
「成果を出すために完璧を目指す」つもりが、かえって効率や人間関係を損なってしまう状態です。具体例・困りごとを以下にまとめましたので参考にしてください。
具体例
• 資料作成に異常な時間をかける。「100点でなければ提出できない」と思い、細部の修正を延々と続ける。
→80点を目指すことをルールにしましょう。
• 失敗を恐れて新しい挑戦を避ける。「ミスしたら評価が下がる」と考え、行動できなくなる。
→PDCAには失敗という概念はありません。チャンスと捉えましょう。
• 他人に任せられない。「自分でやった方が確実」と思い、業務を抱え込みチームの機能が低下。
→マネジメントは他人に任せることが仕事です。マネジメント力向上を目指しましょう。
• フィードバックを避ける。「未完成のものを見せるのは恥」と思い、改善の機会を逃す。
→報連相は仕事では重要項目です。未完であっても報告や相談をしていくことは大事です。
困りごと
• 生産性の低下。完璧を目指すあまり、スピードが落ちて機会損失が起きる。
• チームとの摩擦。細かすぎる指示や修正が、メンバーの自律性を奪い、信頼関係が崩れる可能性が出てくる。
• 孤立感と疲弊。自分だけが頑張っている感覚に陥り、心身ともに疲弊する。チームから孤立していく。 • キャリアの停滞。協調性や柔軟性が欠けていると見なされ、昇進に響く可能性が出てくる
職場では自分だけでなく、上司も同僚も「80%ルール」を共有していくことが大事です。みんながそれぞれを縛らずに余白を大事にしていければ、職場の風土も過ごしやすいものに整っていくことでしょう。
まとめ
完璧主義は悪いことではありません。できればいつも完璧でいたいものです。
ただ完璧を望むあまり周りと連携できなくなっていったり、抱えすぎてストレスとなりメンタル不調に陥ることになると本末転倒です。余白を作り、余裕を持つことも大事です。それは柔軟性に繋がり、協調性が表れることにも繋がってくるでしょう。
無理なく楽に仕事も家事も子育てもしていくことは長く楽しくライフキャリアバランスを整えることにも繋がります。マイペースに気持ちのいい状態を大事にしていきましょう。
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。