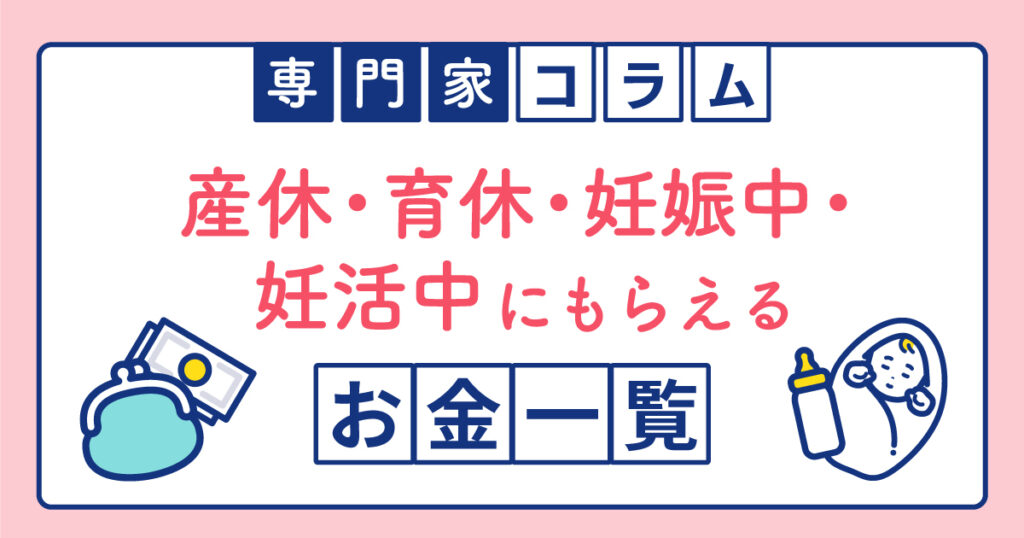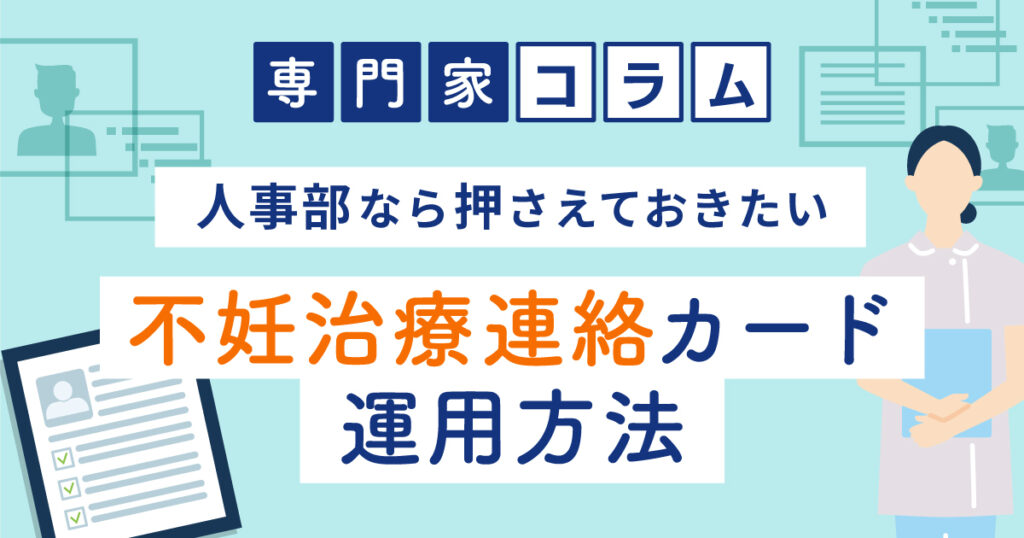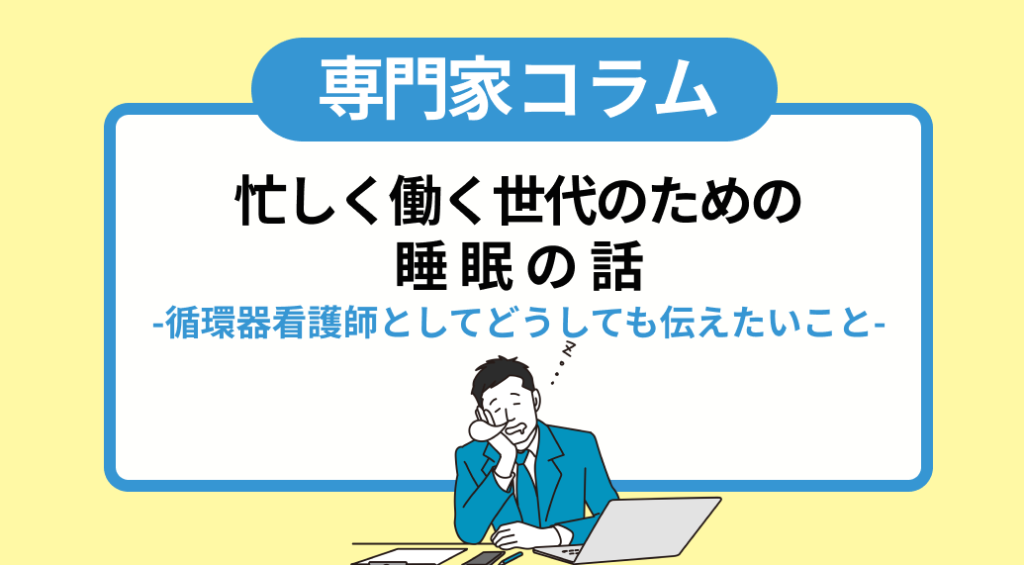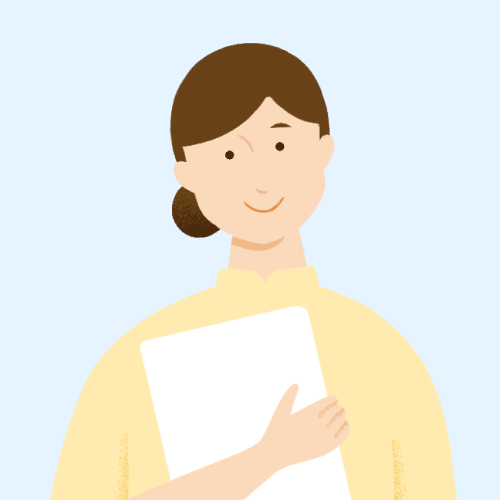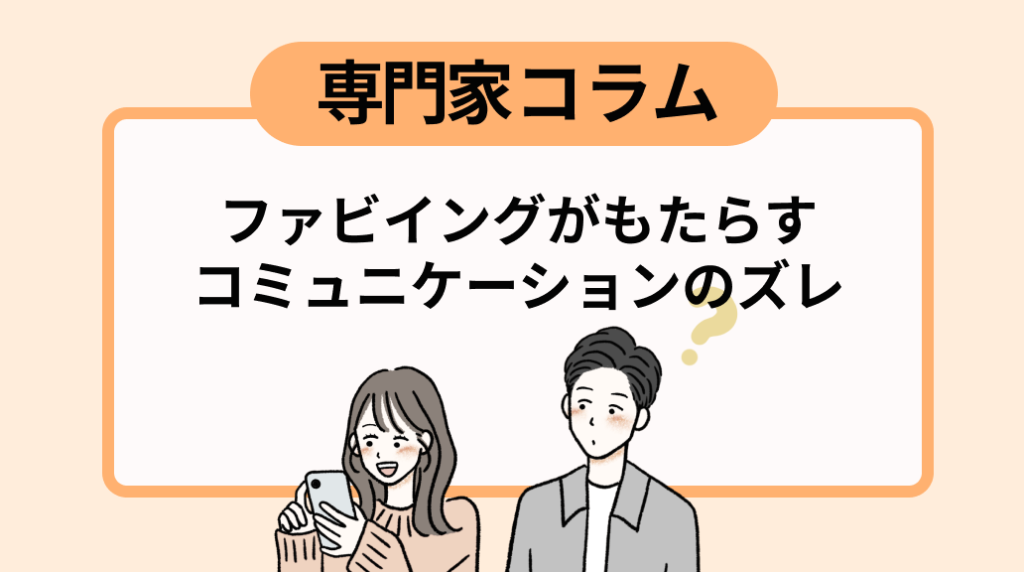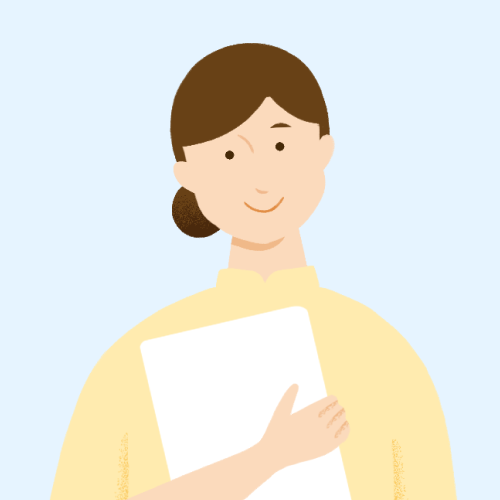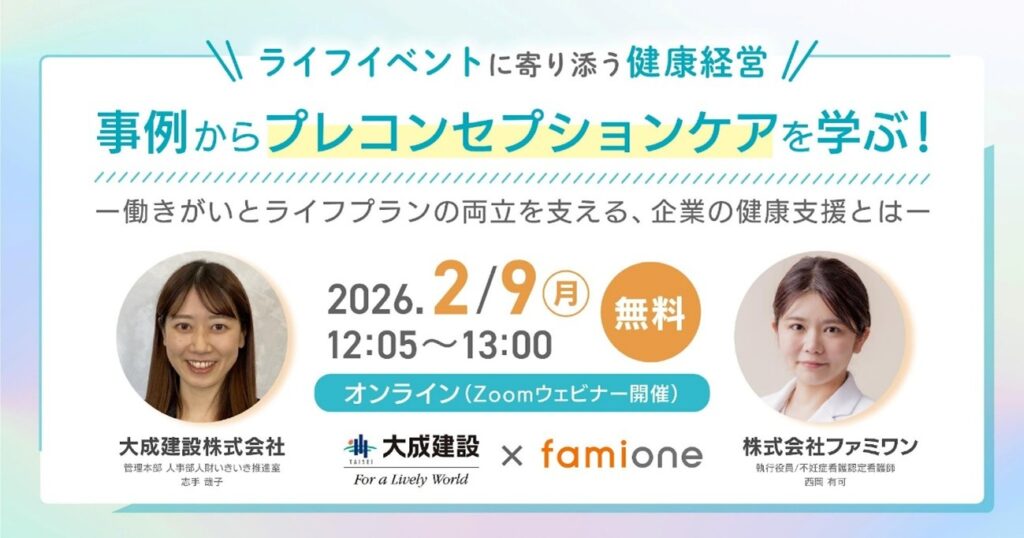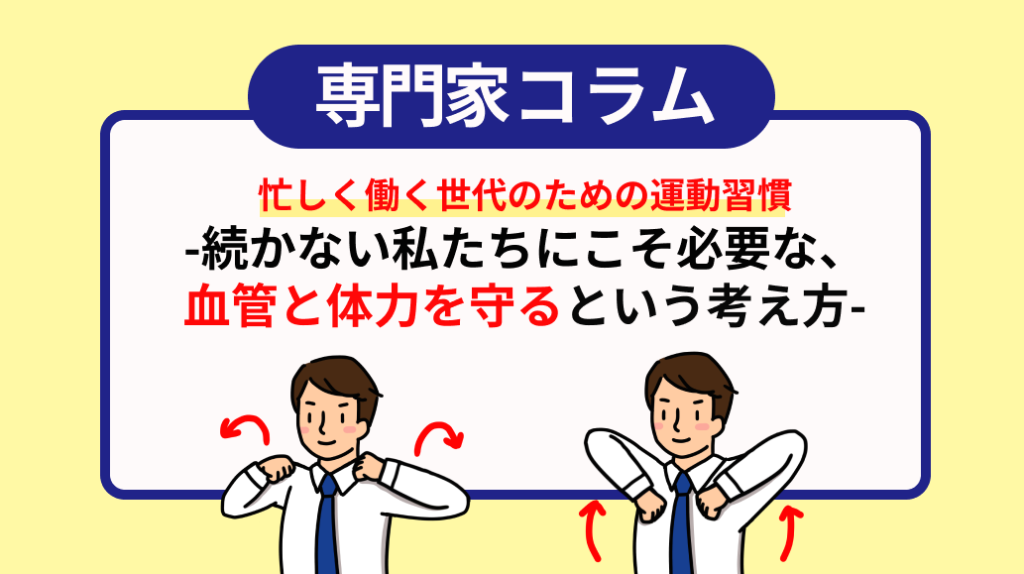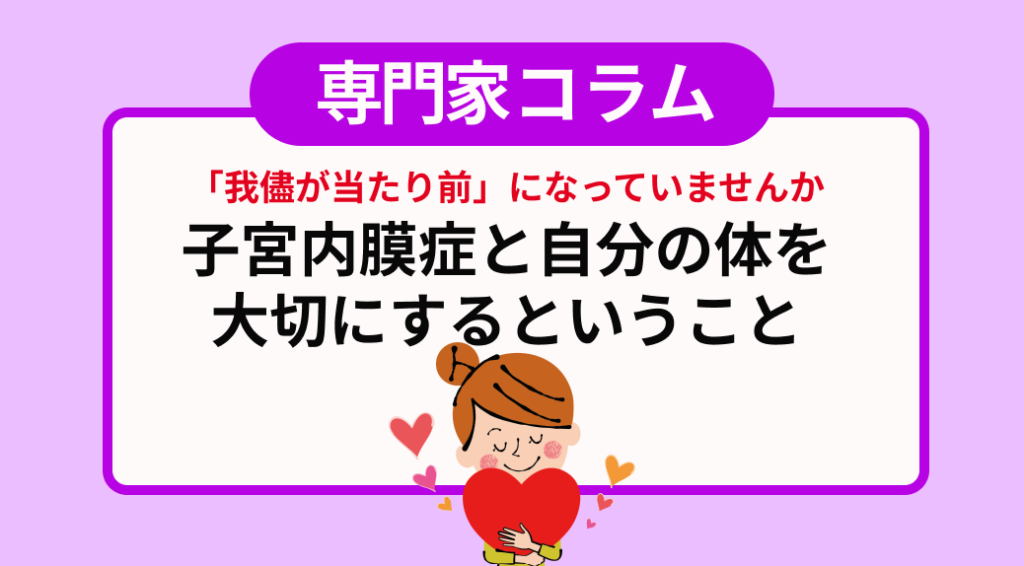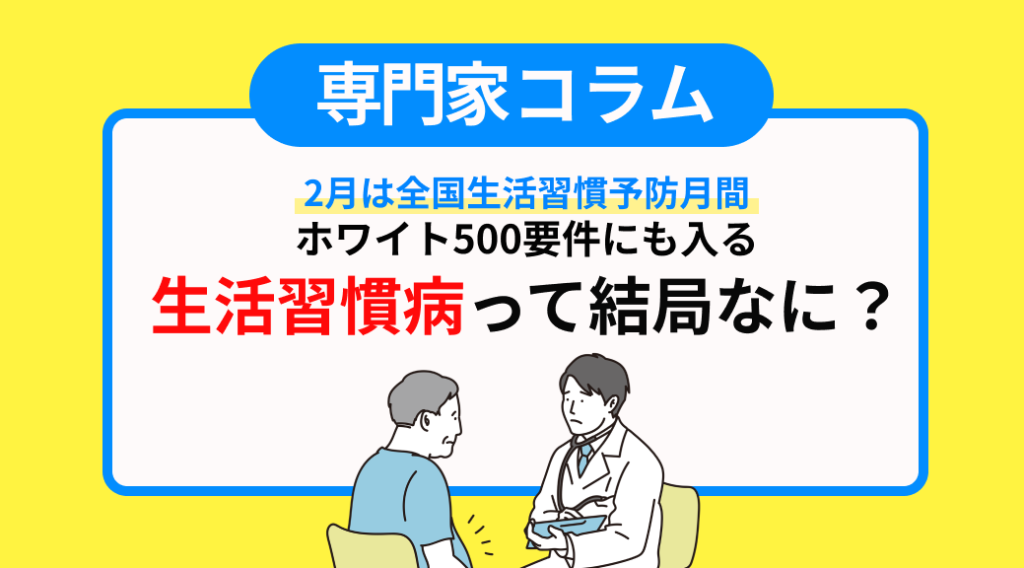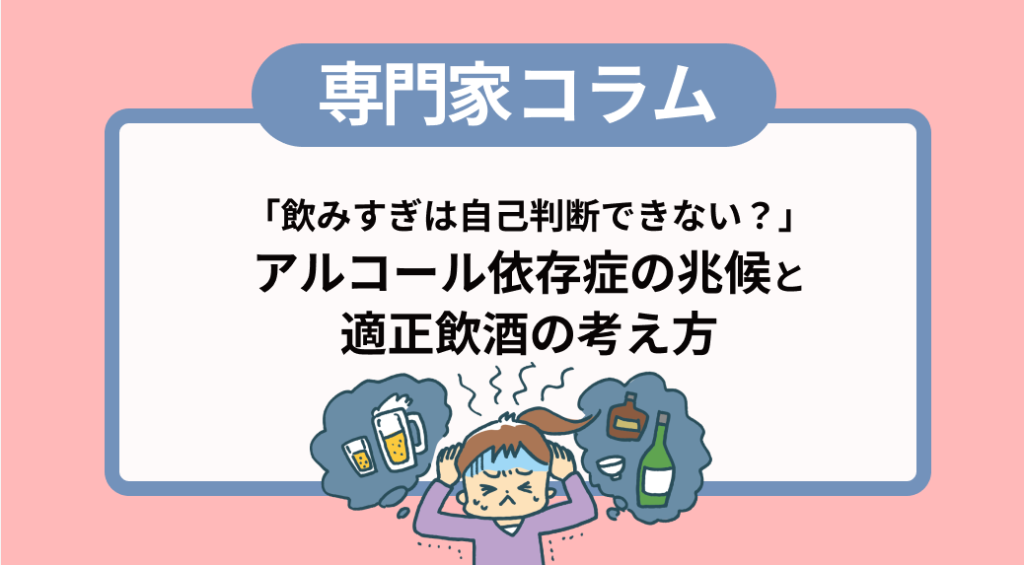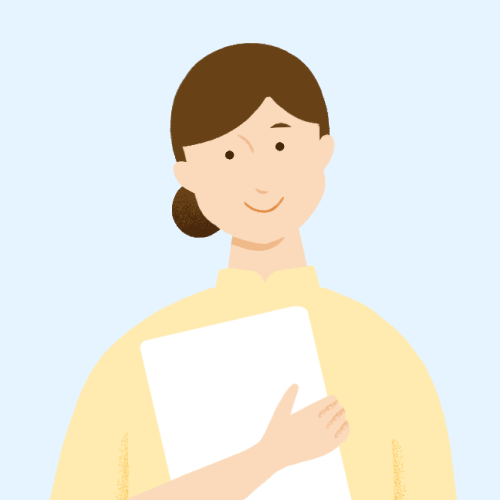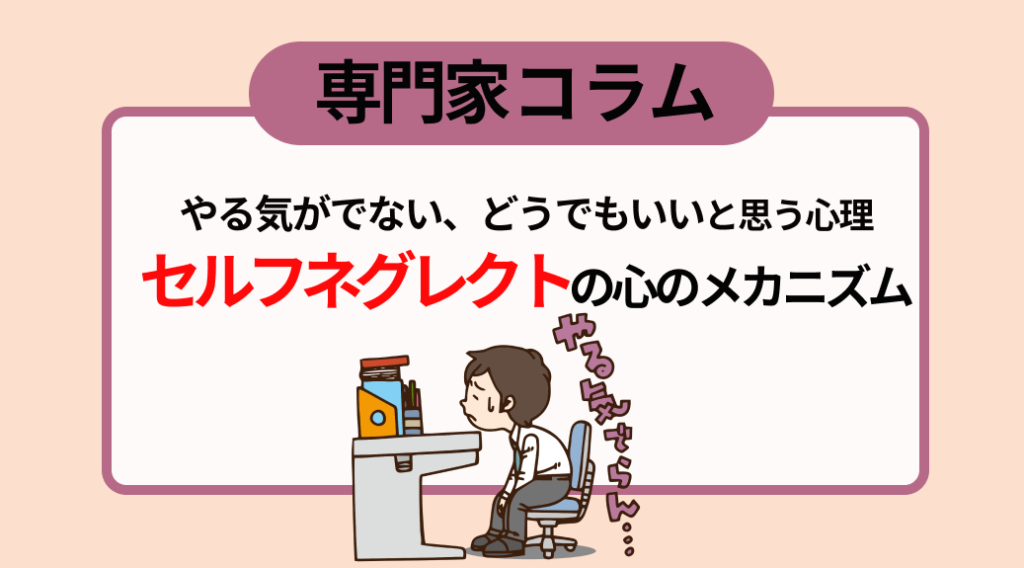-

忙しく働く世代のための睡眠の話― 循環器看護師として、どうしても伝えたいこと ―
夜遅く帰宅し、やっと一息ついて携帯電話を手に取る。「今日もよく頑張った」と思いながら、気づけば日付が変わっている。そして翌朝、重たい身体を引きずるように起きる。。。 これは特別な誰かの話ではなく、今を忙しく生きる私たち世代の日常です。 忙... -

ファビイングがもたらすコミュニケーションのズレ
【ファビイング(phubbing)とは?】 スマホが生活の中心になりつつある昨今ですが、「ファビイング」という言葉が注目されていることをご存じでしょうか? これは英語でphone(スマホ)とsnubbing(冷たくあしらう)を組み合わせた造語です。意味は、目の... -

その疲れ、寝ても取れないなら「眼精疲労」かも?オフィスワーカーのための処方箋
パソコンにスマートフォン、オンライン会議に電子書籍。すこし前まで対面や紙ベースで行われていたことが変化し、現代のオフィスワーカーは非常に目を酷使する環境で生活しています。仕事が終わるころには目の疲れだけではなく、肩こり頭痛まで感じていま... -

生成AIの悪用から子どもを守る|保護者に求められるデジタルリテラシー
生成AIは、私たちの生活を便利にしてくれる一方で、子どもたちにとって新たなリスクも生まれています。 近年では、AIで作られた偽画像や動画、実在しない人物になりすましたやり取り、性的な画像生成やディープフェイクなど、「大人でも見抜くのが難しい悪... -

【セミナーレポート】男性8割の組織で「プレコン」が浸透した理由とは?大成建設に学ぶ、性別を問わず社員の選択肢を広げるための仕組みづくり
2026年2月9日、ファミワンは「事例からプレコンセプションケアを学ぶ!―働きがいとライフプランの両立を支える、企業の健康支援とはー」をオンラインにて開催いたしました。 ファミワンではさまざまな業界の女性活躍や健康経営に関するイベントを開催して... -

忙しく働く世代のための運動習慣― 続かない私たちにこそ必要な、血管と体力を守るという考え方 ―
「運動したほうがいいのは分かっているんです。でも、なかなか時間が取れなくて」これは医療現場で本当によく耳にする言葉です。そして正直に言えば、循環器領域で働く看護師である私自身の実感でもあります。 仕事、家庭、社会的な役割に追われる毎日のな... -

「我慢が当たり前」になっていませんか ー子宮内膜症と自分の体を大切にするということー
【はじめに】 「生理痛が重いのは体質だから仕方がない。」 「みんな同じように我慢している。」 「痛み止めが効いているうちは大丈夫。」 そんなふうに、生理のつらさを受け流している女性は少なくありません。生理にともなう不調は、長い間「女性なら誰... -

2月は全国生活習慣病予防月間― ホワイト500要件にも入る、生活習慣病って、結局なに?―
「生活習慣病に気をつけましょう」 テレビ、健診結果、病院のポスターなどで、この言葉を聞かない日はないほど、生活習慣病という言葉は私たちの身の回りにあふれています。しかし正直なところ、「生活習慣病って何?」と聞かれて、すぐに自分の言葉で説明... -

〖飲みすぎは自己判断できない?〗アルコール依存症の兆候と適正飲酒の考え方
【】 仕事終わりの一杯、金曜日の飲み会、家での晩酌。お酒は、多くの人にとって日常生活の中に自然に溶け込んでいる存在です。 一方で、「最近、少し飲みすぎている気がする」「健康診断で肝機能の数値を指摘された」「家族や同僚から、お酒の量を心配さ... -

“やる気が出ない”“どうでもいい”と思う心理|セルフネグレクトの心のメカニズム
【セルフネグレクトとは?】 洗濯がたためてなくてもう何日も放置してしまっている。皿を洗えていなくていつもシンクが汚れている。お風呂に入るのがめんどうだ。冷蔵庫に賞味期限切れの商品がズラリ。食事を摂る気力が上がってこない。郵便物が開封されず...