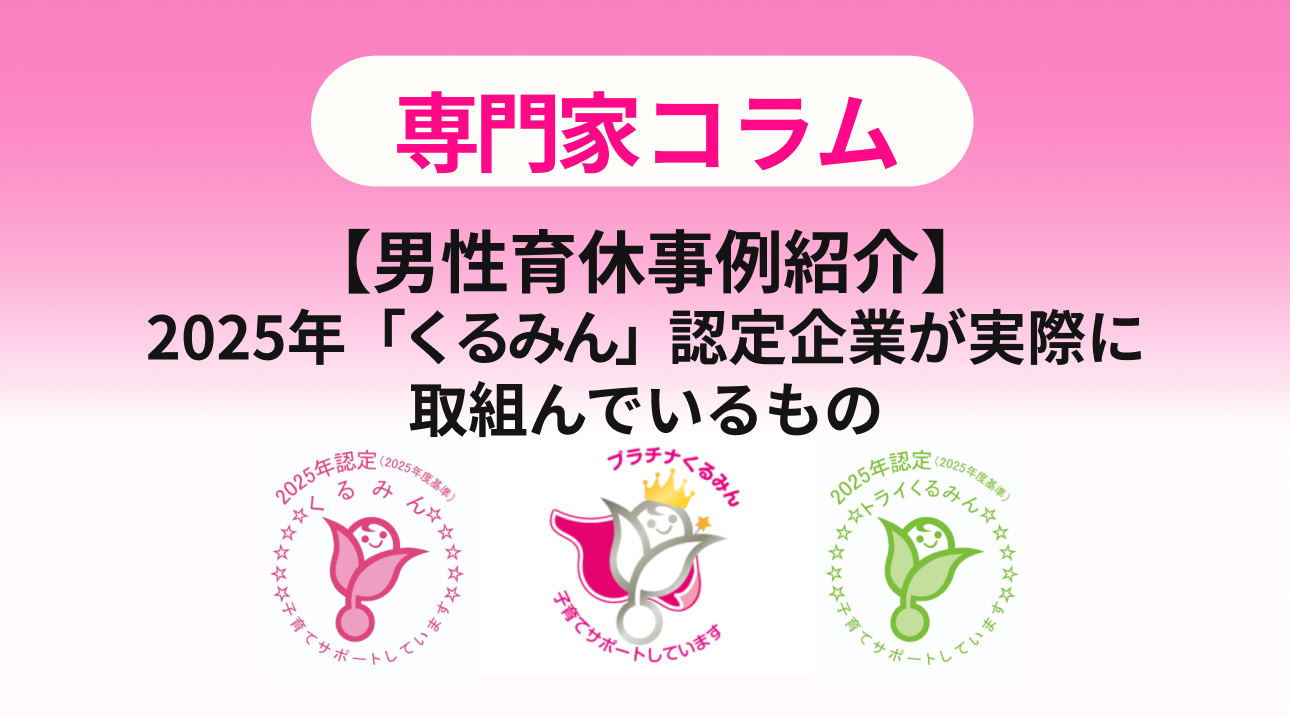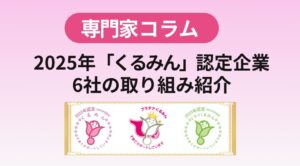はじめに
みなさんは、日本における男性の育児休業取得率をご存じでしょうか。
日本における男性の育児休業取得率は、2025年7月30日に厚生労働省が発表した「雇用均等基本調査」で初めて40%を突破しました。この大きな進展は、企業側の取り組みが実を結んでいることを示しています。
企業の取り組みは、次世代育成支援対策推進法に基づく**「くるみん認定制度」**によって評価されます。この認定要件には男性育休の取得状況も含まれており、企業の「子育てサポート」への姿勢が可視化される仕組みです。
今回は、実際に企業がどのように男性育休の推進に取り組んでいるのか、その具体的な事例をご紹介していきます。
くるみん認定とは
まず、「くるみん認定」について解説します。
「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、企業が「一般事業主行動計画」を策定・届出し、従業員の子育てと仕事の両立支援に関する一定の目標・取組を実施し、かつその目標を達成した場合に、厚生労働大臣から「子育てサポート企業」として認定を受ける制度です。
この認定を受けた企業は「くるみんマーク」を使用でき、採用・広報などにおいて、子育て支援に積極的な企業であることをアピールできます。
認定要件に男性育休が含まれている
ポイントは、「男性の育児休業取得率」などが、「くるみん」認定の評価項目に含まれているということです。
厚労省がまとめた「育児休業取得企業 好事例集」でも、「男性の育休取得を後押しするため、県の表彰やプラチナくるみん認定などの評価が、社員の背中を押すきっかけになっている」と紹介されています。
つまり、くるみん認定を目指す企業は、制度を整えるだけでなく、実際に男性社員が育休を取りやすくし、取得率という“成果”につなげていくことがポイントになります。
くるみん認定を受けた企業の中には、より一歩進んだ取り組み(男性の育休取得率が100%を超えるなど)を行っている企業「プラチナくるみん」や「くるみんプラス」といった、さらに上位の認定を受けられる仕組みがあります。
2025年「くるみん」認定企業の取り組み紹介
実際に「くるみん」に認定されている企業の男性育休推進のための取り組み事例を紹介していきます。
(認定年順に掲載)
日立システムズ
2023年「くるみん」認定
取り組み(一例)
- 男性育休取得者とその上司の「事例発表会」の実施
- 育休取得を後押しする職場であるために、職場の受容性を高める「誰もがいきいきと働く職場セミナー」の開催
- 育休取得を推奨するご案内メールを上司と当事者に対して個別で送付
- 男性育休を応援する冊子「夫婦で話そう。考えよう。パパ育休のこと」の自治体配布プロジェクトに参画し、従業員にもWebで公開。
- 新米パパ・ママの不安を解消するための「プレパパ・プレママセミナー」の開催
- 上司と当事者を対象とした、産休・育休からの職場復帰をサポートする復職支援セミナーの開催
- 会社制度や給付金・支援金、福利厚生、セミナー、先輩の体験談など、仕事と育児の両立に関する情報を網羅できる従業員向けポータルサイトの開設
- 男性の育児参加を後押しするため、「仕事と家庭の調和」を応援する「SMILE∞パパエプロン」を作成し従業員200人/年に配付
- 長期に育休を取得した男性社員とその上司が体験談を話す「男性育休パネルセッション」を開催
実績
2024年度時点で男性育休取得率約97.3%を達成。
富士薬品グループ
2024年6月「くるみんプラス」認定
取り組み
- 国や会社の制度、手続き方法などをまとめた、富士薬品グループ・オリジナル「子育て手帖SUKUSUKU」の配布
- 育児と仕事の両立についての教育
- 育児休業セミナーの実施(管理職向け・男性向け)
- 育児関連サービスの割引(保育、シッター等)を含む福利厚生サービスの導入
- 同じ背景をもつ従業員の横のつながりを作るため、育児休業者の会(SUKUSUKU サロン)の開催および交流目的の掲示板を設置
- フレックスやテレワーク、半日単位の年次有給休暇制度の導入・利用促進
- 育児休業を最長子供が3歳になるまで延長
- 育児短時間勤務制度を最長子供が小学校6年生になるまで延長
実績
男性育児休業取得率51%達成
三井不動産株式会社
取り組み
- ワーキングファザー座談会・育児座談会を社内で実施し、男性社員・その配偶者・上司間の育児・仕事の両立意識の向上
- 出産・育児に関する面談制度、産育休復帰時研修、さらにベビーシッター・家事代行費用の補助制度も備えており、育休そのものを取得しやすく、また復職もしやすい環境を調整
実績
2022年以降、男性育休取得率100%超を継続
株式会社LTS
2025年1月「くるみん」認定
取り組み
- フレックス、裁量、テレワーク等の多様な勤務制度整備と育児支援体制を導入。
- 職場風土づくりで育休取得を後押し。
実績
2024年度の男性育休取得率100%・復職率100%を達成
電通
2025年8月「くるみん」認定
取り組み
- 人事部門との連携をさらに強化し、各組織で従業員の育児休業に関する制度理解や取得促進の「個別の声かけ」を推進するなど、子育て世代に寄り添った密なサポートを実施
- 育休の平均取得日数の向上に伴い、長期離職後のスムースな復職支援を拡充
- 少人数の「復職時説明会」を高頻度で開催し、休業中の社内の取り組みや制度の変更点の共有などを行いつつ、復職者同士の対話機会も設け、子育て世代同士の「横のつながり」づくりを支援
- DEIに関する研修やネットワークづくりの機会提供といった全従業員向けの施策を通じ、継続的に育児休業への理解促進と取得者の不安を払拭
実績
男性従業員の育休取得率が103.1%(※複数回取得などを含む算出方式)
平均取得日数67.1日まで向上
ダイキン工業株式会社
2025年3月「プラチナくるみん」特例認定
取り組み
- 男性の育児休暇取得推進として、「子どもが生まれた男性社員とその上司に対する個別アプローチ」「男性育児休暇取得事例の社内共有」「全社的な意識改革」などを実施。
- 育休取得者・復職者だけでなく、その上司や関係者を巻き込んだ研修・セミナー(「仕事と育児両立セミナー」)を2012年より開催し、性別役割分担に関するアンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)を払拭する取組も実施。
実績
2023年度男性育休取得率88%達成
セイコーグループ
2025年10月「プラチナくるみん」認定
取り組み
- 2022年から最大4週間を100%有給で取得できる「出生時育児休業制度」を導入。
- 経営トップの啓発、社内セミナー、取得者の体験共有を実施。
実績
2023年度以降、男性の育休取得率100%を達成
課題と今後の展望
男性育休の促進やくるみん制度は着実に広がりつつありますが、まだ取り組んでいきたい課題も残っています。たとえば、男性の育休取得率そのものは上がってきたものの、「取得日数が短い」「制度はあっても使いにくい」といった声は少なくありません。制度が整っていても、職場の雰囲気や上司の理解が追いついていないと、「申し出にくい」「周囲の目が気になる」という心理的なハードルが生まれてしまいます。
また、企業規模や業種によって取り組みやすさにも差があります。特に中小企業では、代替人員の確保や体制づくりに余裕がなく、リソース面で苦しさを感じるところもあります。さらに、復職後のキャリア支援が十分でない場合、育休を取ったことがその後の働きにくさにつながるケースもあり、長期的な視点での支援が求められます。
一方で、これからの展望としては、社会全体に「共に育てる」という意味を持つ“共育(ともいく)”の考え方が広まりつつあり、夫婦で家事・育児を分担する文化がより定着していく流れがあります。実際、ニュースや行政資料でも「男性の家事・育児参画」や「長時間労働の是正」が取り上げられ、社会的な意識変化が加速しています。
企業の働き方改革やダイバーシティ推進が進むなかで、男性育休や育児支援制度は、採用や定着を左右する“企業の魅力”として重要度を増しています。くるみん認定やプラチナくるみん認定を取得する企業が増えることで、今後は企業間で「より働きやすさを高める取り組み」を進める流れが強まる可能性もあります。
このように、男性育休の促進には制度を整えるだけでなく、復職後のキャリア支援や、安心して取得できる職場づくり、上司・同僚の意識変化など、さまざまな側面からのアプローチが必要です。
おわりに
男性育休の取得促進と、企業のくるみん認定制度の活用は、子育て世代・働くママ・パパ・企業の三者にとって大きな意義を持っています。これから育休を考える方、制度整備を進める企業、働きながら子育てを続けている家庭の皆さんにとって、今回の内容が参考になることを期待しています。
【引用先】
・日立システムズhttps://www.hitachi-systems.com/recruiting/female/diversity.html
・富士薬品グループhttps://www.fujiyakuhin.co.jp/company/number.php
・三井不動産株式会社https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2024/0903/
・株式会社LTShttps://lt-s.jp/news/pressrelease/2025-03-27-1
・電通https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/1006-010953.html
・セイコーグループ株式会社https://www.seiko.co.jp/news/sgc/2025/202511131000.html
無料「くるみん認定チェックシート」ダウンロード
「くるみん認定」「くるみんプラス認定」取得に向けた取り組みをご相談いただけます。
不妊治療と仕事の両立支援や育児支援制度の整備をはじめ、認定取得を後押しする多様なサポートをご提供します。

1. 「まずは自社のくるみん対応度を可視化」
あなたの会社は、くるみん取得に向けてどの段階にありますか?
このくるみんチェックシートで現状ギャップを把握し、改善の優先ポイントを明確にできます。
2. 「不妊治療と仕事の両立支援もカバー」
「くるみんプラス認定」では、不妊治療支援も評価対象。
関連資料とあわせて、制度設計や支援施策のヒントが得られます。
3. 「無料で資料を入手・取り組みをスタート」
くるみんチェックシートのダウンロードは無料。
資料をもとに、社内で議論を始めたり、外部支援の相談も可能です。