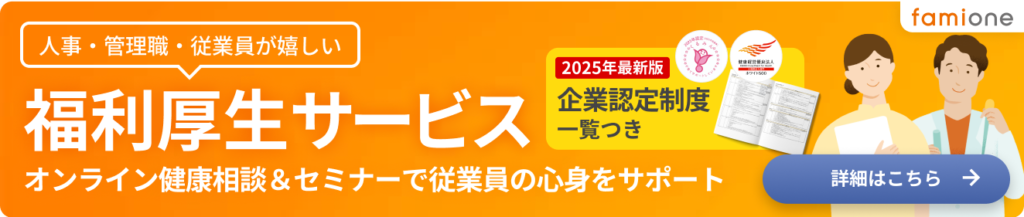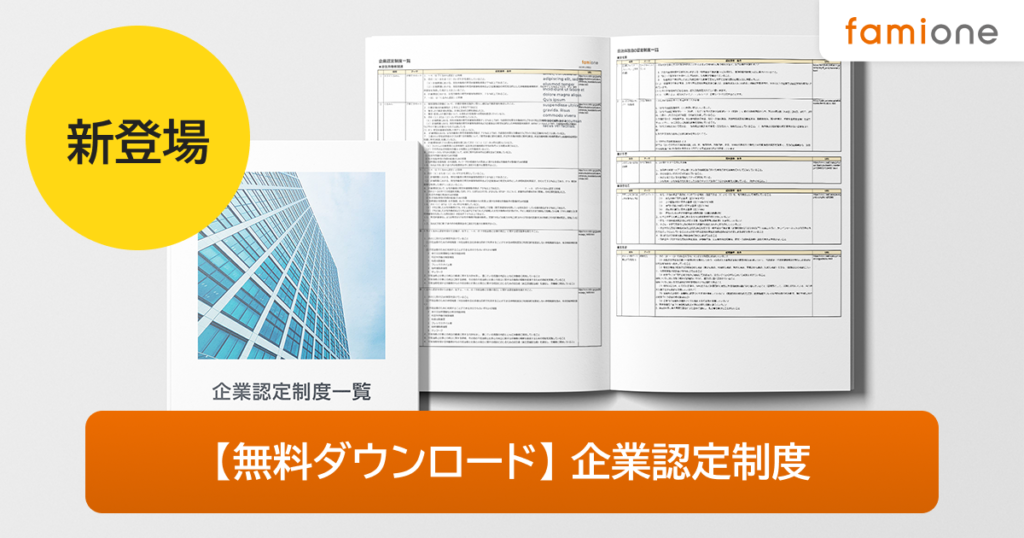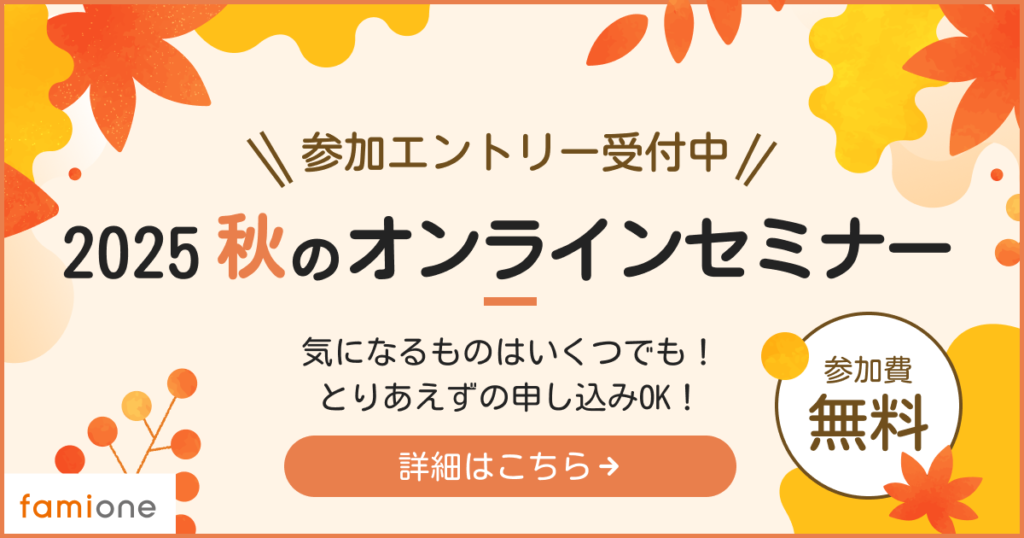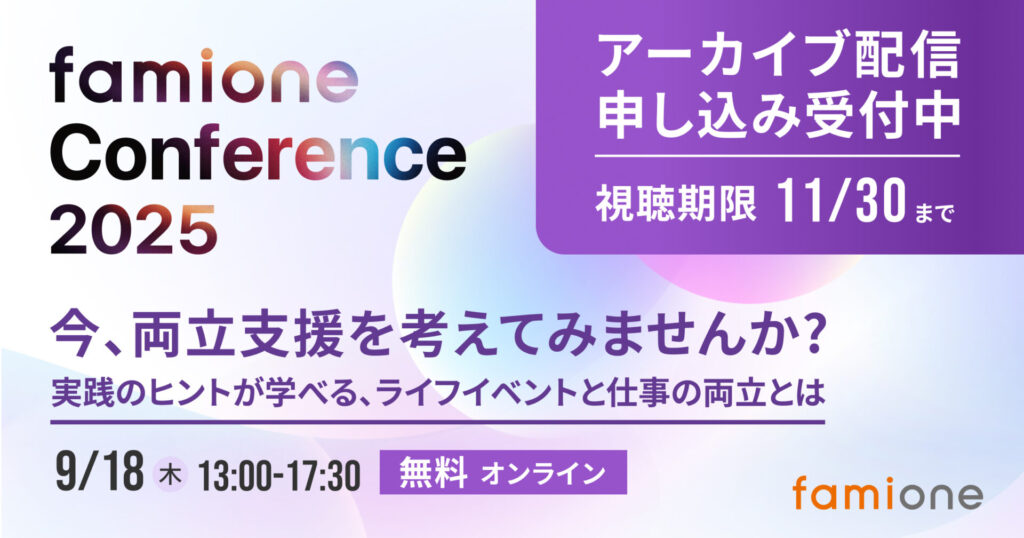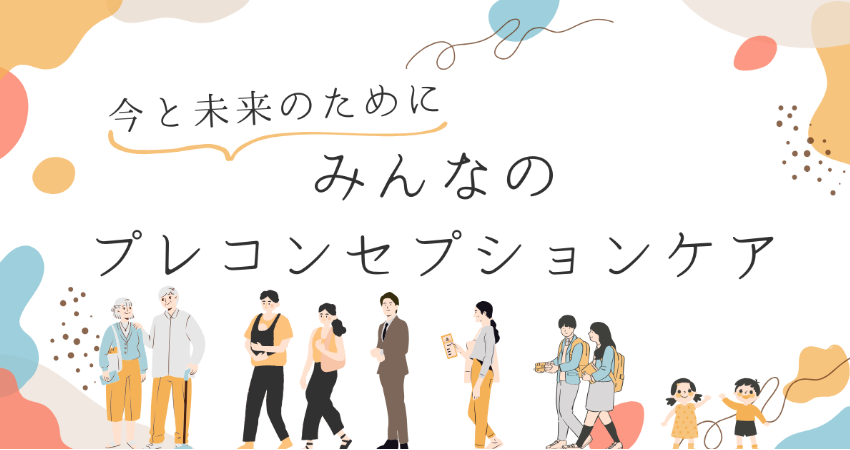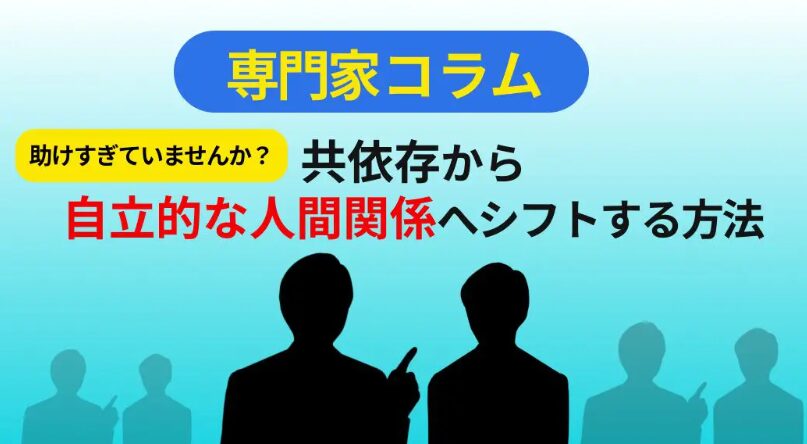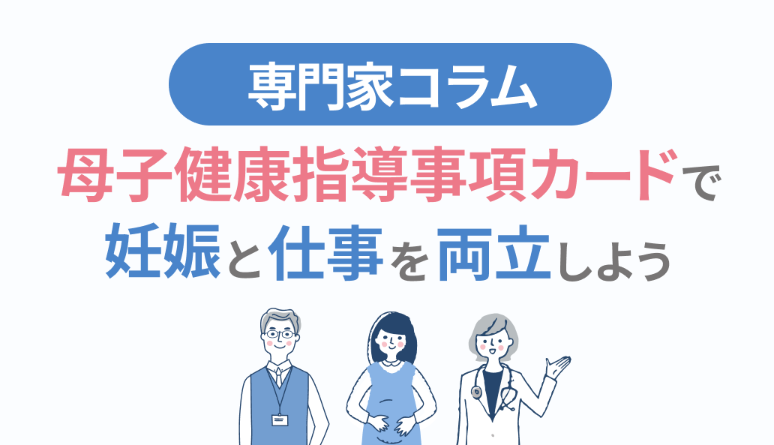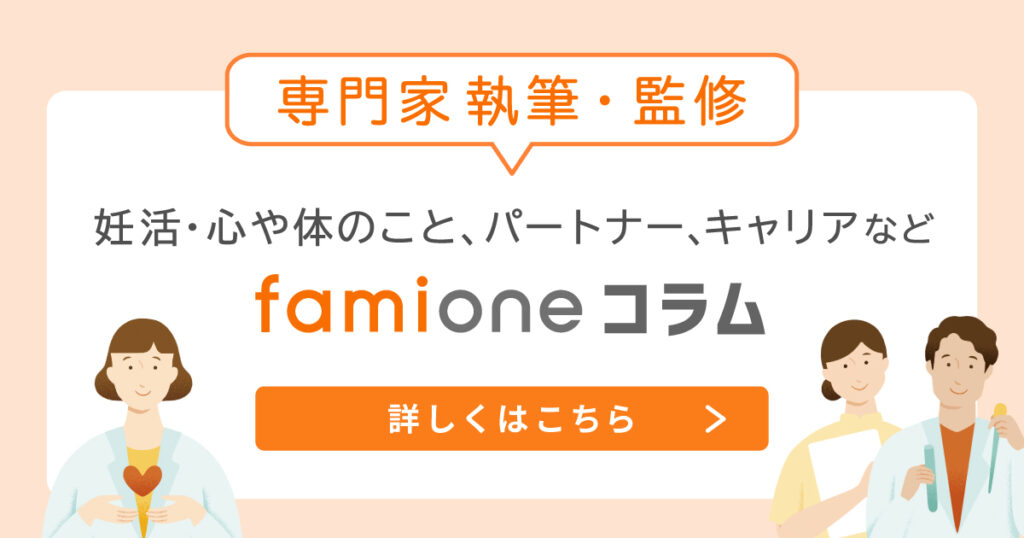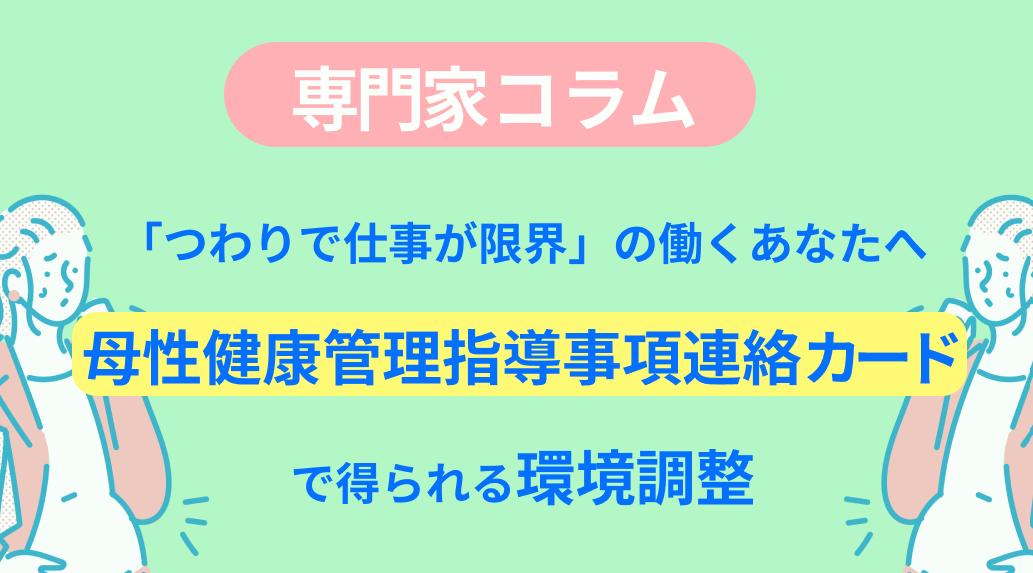
妊娠初期の悪心・嘔吐といった『つわり』は、半数以上の妊婦さんにみられ、この内、体重減少、脱水、電解質異常などがあらわれた『妊娠悪阻』は全妊婦の0.5~2%に発症すると報告されています。症状の程度やいつまで症状が持続するかは個人差があり、また同じ人であっても妊娠毎に症状やその程度が異なるのも実際です。
つわり・悪阻の原因は
妊娠悪阻の原因ははっきりとはわかっていませんが、こころと身体に負担をかけないよう安静と休養が大切になります。また少量ずつでも食事や水分摂取を頻回に行うことで栄養・水分補給をしていくことが必要です。
『つわり』は妊婦さんにとって、よくある症状としてご本人も周りもあまり心配されない場合もありますが、嘔気・嘔吐だけでなく、食事・水分摂取不良による倦怠感や集中力の低下、睡眠不足など様々な不調を伴い、日常生活においても支障をきたす場合があります。
実際に、皮膚や口腔内の乾燥など脱水の所見が認められる場合や、5%以上の体重減少があり水分の経口摂取が難しい場合、尿検査でケトン体の強陽性が続く場合などは点滴による治療が必要となります。そして、ビタミンB1は糖質代謝に必要な補酵素ですが、このビタミンB1が不足すると、眼球運動障害、失調性歩行、意識障害などWernicke脳症を引き起こす可能性があります。
他にも妊娠悪阻に伴う低カリウム(K)血症が原因の不整脈が報告されています。妊娠中は体内の循環血液量の増加などにより血清カリウムは妊娠前に比べ低下します。その上で食事摂取不良に伴うカリウム摂取量の低下と嘔吐によりカリウム喪失が加わり、妊娠悪阻では低カリウム血症に陥りやすいと考えられます。
つわり・悪阻の対策
では、こんなに症状がひどい場合も症状に対処しないのか、というとそうではなく、悪心・嘔吐のために日常生活が著しく制限される場合は、制吐薬が使用可能で、明らかな催奇形性や胎児毒性は報告されていませんので、しんどい場合は我慢し続けず、主治医に制吐薬について相談されたら良いと思います。また、必要に応じて補液など症状緩和・悪化の予防のために治療を行う場合もあります。しんどさは本人しかわからない部分なので、「つわりは誰でもあることだから」と我慢せず、まずは相談してみてください。
職場での対応
このように『つわり』といっても『妊娠悪阻』を含めると重症な場合もあり、家事や育児・仕事にも影響が出てくることは少なくありません。
また、仕事の業務内容によっては、妊娠前は難なくできていたことも、体調によってしんどくてままならない場合もあると思います。妊娠初期だと、職場へ妊娠したことを伝えていない場合もありますが、お仕事を休む際は、有給休暇を使用する場合は、体調不良などで取ることが可能です。しかし、体調不良による影響が仕事に頻回に出てくる場合は、直属の上司の方には妊娠を伝えておいた方が良いかと思います。この時、まだ職場の他の方に知られたくない場合は、安定期に入ってからお伝えしたい、などご自身の希望を伝えておいた方が良いでしょう。
母性健康管理指導事項連絡カードの活用
また、業務の内容や時間帯によって対応できるもの、困難なものがある場合は、上司に「どんな時に、どんな症状がでてつらいから、このように配慮してもらいたい」など、自身の体調と共に業務内容なども伝えると、職場側としても考慮しやすくなるかと思います。 ただし、このような配慮を求める際に主治医の診断書などの提出を求められる場合がありますので、親子手帳にある「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用しましょう。(もし親子手帳にない場合は、こちらの厚生労働省のHpからダウンロード可能です
男女雇用機会均等法では、事業者は、妊娠中及び出産後の女性労働者が、妊娠中及び産後の健診を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導事項を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更や勤務の負担軽減などの措置を講じる義務があります。この「母性健康管理指導事項連絡カード」は医師等から受けた指導事項の内容を事業主に的確に伝えるための連絡カードです。
妊婦健診時に、体調が優れなかったり、勤務する上で不安に思うことなどがあれば、遠慮なく医師等に相談しましょう。そして、医師等から、妊娠中の通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなどの症状に対応して勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、「母性健康管理指導事項連絡カード」に記入してもらい、会社へ提出しましょう。
通勤緩和・時間外労働などにも適用されます
また、妊娠悪阻以外でも体調や何らかの症状の程度によって妊娠中は職場生活において配慮を考慮してもらえるよう申請することが可能です。これは労働基準法や男女雇用機会均等法等によって制定されており、会社に規定がない場合やパートなどの方も会社へ申し出ることが可能です。
通勤緩和
交通機関の混雑による苦痛は、つわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあり、医師等から通勤緩和の指導があった場合には、妊娠中の女性労働者が申し出ることにより、時差出勤やフレックスタイム制度の適用、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更等、通勤緩和の措置を受けることができます。また、電車・バス等の公共交通機関を使っての通勤の他、自家用車による通勤も通勤緩和の措置の対象となります。
休憩などに関する措置
医師等から休憩に関する措置について指導があった場合には、妊娠中の女性労働者が申し出ることにより、適宜の休養や捕食、休憩時間の延長、休憩回数を増やす等休憩に関して必要な措置を受けることができます。ただし、法律では休憩回数を定めていません。健康状態には個人差があり、また、作業内容も個々によって異なりますので、状況に応じて母性健康管理に携わっている関係者(上司、健康管理部門、人事管理部門、産業保健スタッフ等)と相談し、適切な措置を講じてもらいましょう。
時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限
妊娠中は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。変形労働時間制が適用される場合も、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。
軽易業務転換
妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。
危険有害業務の就業制限
重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所等における業務については、妊娠・出産機能等に有害であることから、妊娠中はもとより、全ての女性を就業させることが禁止されています。
男女雇用機会均等法について知っておこう
もし仮に、配慮を求めた際に妊娠・出産、産前産後休業、育児休業等を理由に解雇、不利益な異動、減給、降格、パートへの契約変更の強要、雇止めなど不利益な扱いを受けた場合、これらは男女雇用機会均等法、育児・介護休業法で禁止されており、「違法」になります。
我慢し続けるのではなく、安心して妊娠・出産等と仕事を両立していくために、様々な制度を活用し、妊娠・出産という大切な期間を楽しんでいただければと思います。
また、同僚や上司として妊婦さんに対してどのように関わるべきか悩むこともあるかと思います。妊娠・出産に伴う不調や症状は個人差があり、また体力・耐力も人それぞれ違い、判断が難しい場合もあるかと思います。しかし、1番大切なのは、相手の方がどのような状況で、どのようなサポートを求めているのか、しっかりと耳を傾け話し合い、働きながら安心して子どもを産むことができる環境を整備することだと思います。いつもフラットな相談しやすい雰囲気づくりをしていただき、サポートいただければと思います。
マタニティー・ハラスメント、逆マタハラなどという言葉がありますが、お互いに気持ちよく安心して働けるように、コミュニケーションを図り、お互いを理解・支援しあえる職場を一緒に作り上げていただきたいと思います。
【引用・参考文献】
・産婦人科診療ガイドライン産科編2023 日本産科婦人科学会
・厚生労働省 母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について
・厚生労働省 働く女性の母性健康管理のために