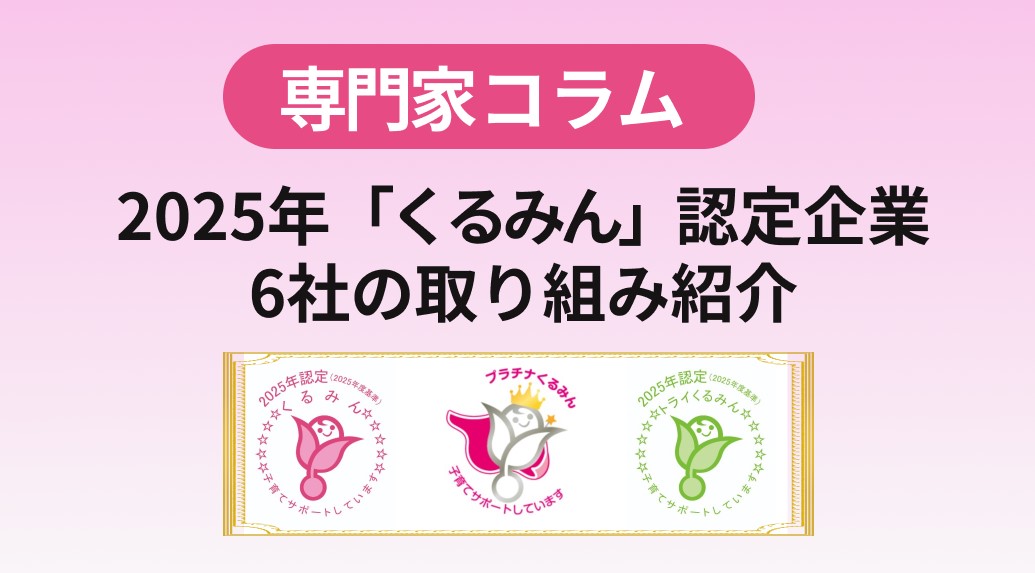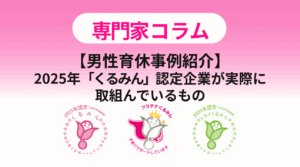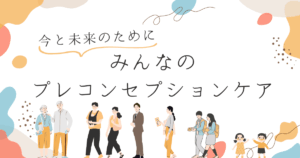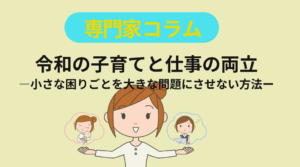はじめに
「くるみん」認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、厚生労働大臣が子育てサポート企業として認定する制度です。企業が労働者の仕事と子育てに関する行動計画を策定・実施し、一定の基準を満たすことで認定を受けることができます。より高い水準の取り組みを行っている企業には「プラチナくるみん」認定制度も設けられています。
さらに、2022年には仕事と不妊治療の両立支援にも積極的に取り組んでいる企業を認定する制度として「くるみんプラス認定」も始まりました。
今回は2025年2月時点で認定されている企業の中から6社をピックアップして、実際の取り組みを紹介していきます。
【ファミワン公式】「くるみん認定チェックシート」でくるみん認定をチェックしてみませんか?ダウンロードは無料です。
実際の取り組み紹介
①株式会社JTB【くるみん】
旅行サービスを提供する会社で、規定の改訂を積極的におこなうなど、子育て世帯に寄り添っています。
【主な取り組み】
①産後パパ育休
コアタイムなしの完全フレックスタイム制の導入。
②テレワーク勤務規程の改訂
在宅勤務の実施可能日数の上限を撤廃。
②資生堂【くるみん】
日本を代表する総合化粧品会社で、多様な働き方を認めることで家族とキャリアの両立を支援しています。
【主な取り組み】
①育児時間制度
資生堂では、子どもが小学3年生になるまで1日最大2時間の勤務時間を短縮可能
②看護休暇制度
小学校入学前の子どもの病気・ケガの看護や、子どもの健康診断・予防接種のために、1時間単位で取得できる有給休暇制度
③育児期社員への補助金
国内の資生堂グループの子どもを扶養する社員に対しては、子どもを保育園やベビーシッターに預ける際の保育料や子どもの教育費を補助するための手当を支給
③株式会社富士薬品【くるみんプラス】
医薬品の研究開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業で、2024年にくるみんプラス認定を受けています。
【主な取り組み】
- 国や会社の制度、手続き方法などをまとめた、富士薬品グループ・オリジナル「子育て手帖SUKUSUKU」の配布
- 育児休業を最長子供が3歳になるまで延長
- 育児短時間勤務制度を最長子供が小学校6年生になるまで延長
- フレックスやテレワーク、半日単位の年次有給休暇制度の導入・利用促進
- 「不妊治療と仕事の両立のハンドブック」の配布
- 不妊治療の教育と相談窓口の設置
- 私傷病休職制度を不妊治療に適用
④味の素AGF株式会社【プラチナくるみん】
コーヒーやスティック飲料を中心とした飲料製品を製造・販売している企業で、2017年には食品業界で初の「プラチナくるみん」と「えるぼし」最高評価のダブル取得をしています。
【主な取り組み】
①妊婦による特別休暇
妊娠中に10日間取得可能
②配偶者出産時の特別休暇
子が生まれてから14日以内に5日間取得可能
③男性育休(こどもスマイルムーブメント)
2010年頃から男性育休についての取り組みを開始
⑤ピジョン株式会社【プラチナくるみん】
育児用品の製造・販売を手がける会社。働き方スローガンに「決まった時間の中でsmartに働き、プライベートをsmileでいっぱいにする」というものを掲げています。
【主な取り組み】
①ワークライフバランスに関連する当社独自の制度
- 19時退出(退社)ルール:遅くとも19時までには会社を退出するというルール
- ひとつきいっしょ:1カ月間、有給で取得できる育児休業制度(男女共に利用可能)
- 復職サポート:復職前の人事面談、制度説明と復職先部門長面談、復職ママ会の実施など
②授乳・さく乳室の設置
授乳・さく乳室」を設置し、当社社員のみならず、近隣に勤務・居住するママと赤ちゃんにも利用できるようになっている
その他にも社員で作り上げる育児制度プロジェクトも実施されており、社員の生の声を反映した育児制度の拡充を図っているようです。
⑥丸紅株式会社【プラチナくるみんプラス】
【主な取り組み】
①保育サービス費用の会社負担
「復職時保育サポート手当」、「出張時保育サービス手当」を導入
②育児・看護・不妊治療のために取得可能な特別休暇(有給)
ファミリーサポート休暇(5日/年)および特別傷病休暇(累積最大50日)
③妊活・不妊治療のオンライン相談
④先進医療支援制度
不妊治療等を含む厚生労働省が定める先進医療を受けた場合の費用補助
【ファミワン公式】「くるみん認定チェックシート」でくるみん認定をチェックしてみませんか?ダウンロードは無料です。
おわりに
今回は、「くるみん」「プラチナくるみん」「くるみんプラス」認定企業の取り組みを6社ご紹介しました。
2022年には不妊治療の両立支援を認定する制度として「くるみんプラス認定」も始まり、育児と仕事の両立支援はもちろん、妊娠・出産・育児・不妊治療など、あらゆるライフステージに寄り添う支援体制が広がっています。
無料「くるみん認定チェックシート」ダウンロード
「くるみん認定」「くるみんプラス認定」取得に向けた取り組みをご相談いただけます。
不妊治療と仕事の両立支援や育児支援制度の整備をはじめ、認定取得を後押しする多様なサポートをご提供します。

1. 「まずは自社のくるみん対応度を可視化」
あなたの会社は、くるみん取得に向けてどの段階にありますか?
このくるみんチェックシートで現状ギャップを把握し、改善の優先ポイントを明確にできます。
2. 「不妊治療と仕事の両立支援もカバー」
「くるみんプラス認定」では、不妊治療支援も評価対象。
関連資料とあわせて、制度設計や支援施策のヒントが得られます。
3. 「無料で資料を入手・取り組みをスタート」
くるみんチェックシートのダウンロードは無料。
資料をもとに、社内で議論を始めたり、外部支援の相談も可能です。