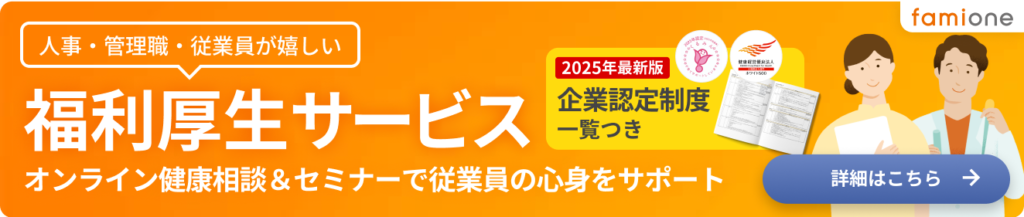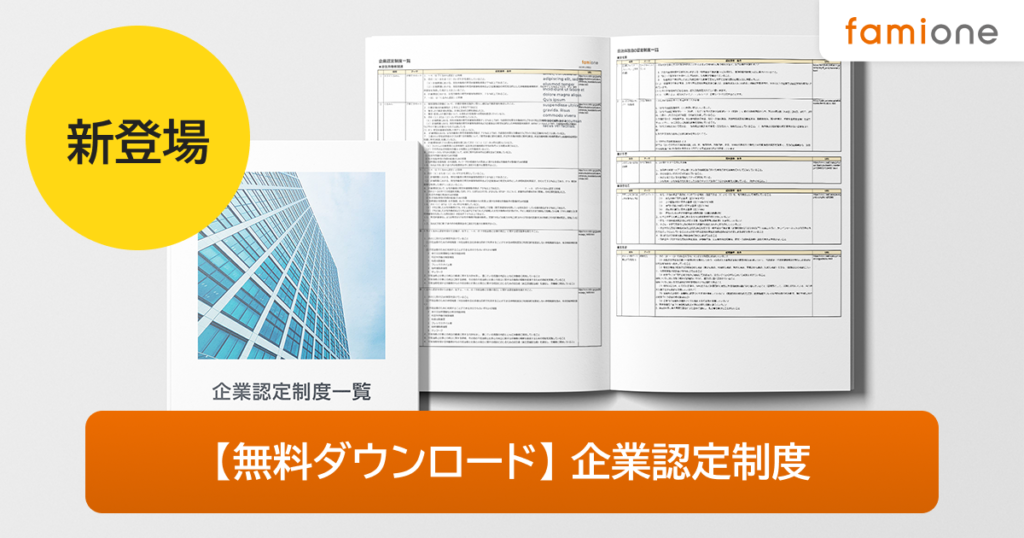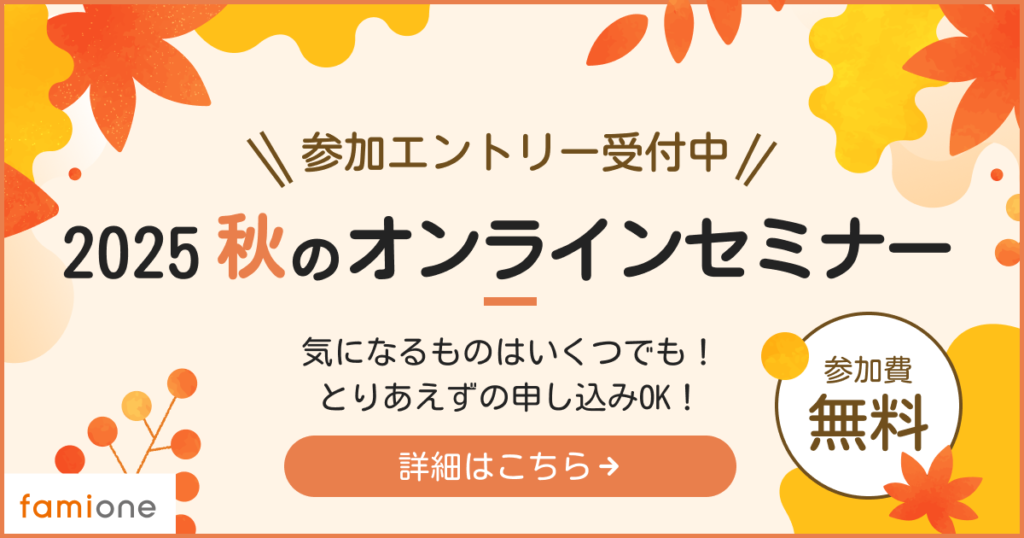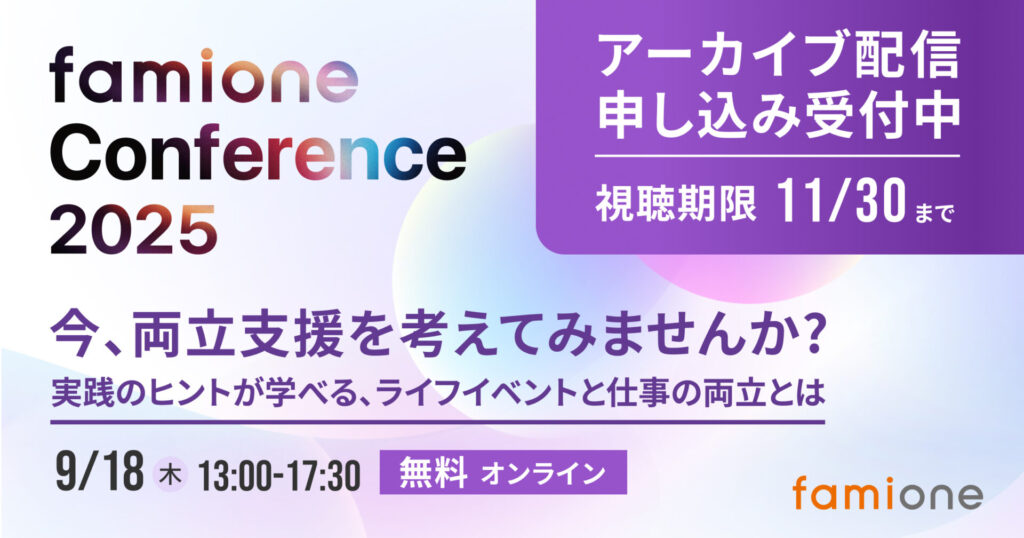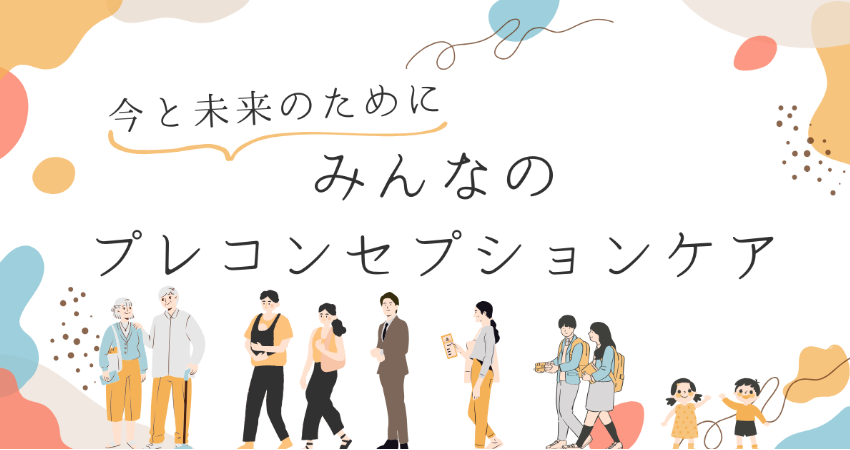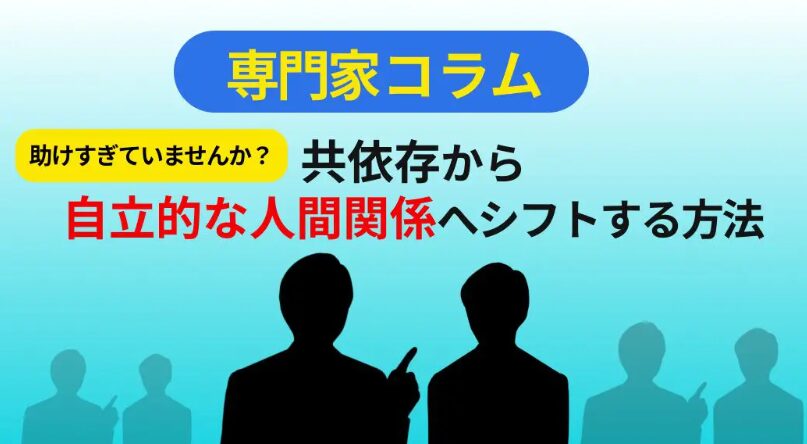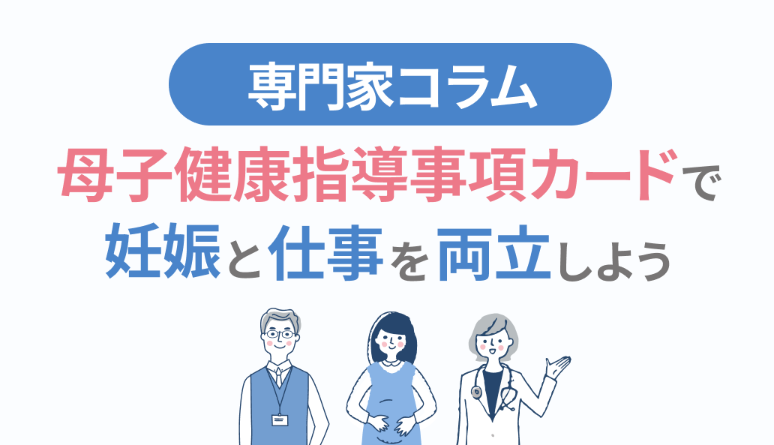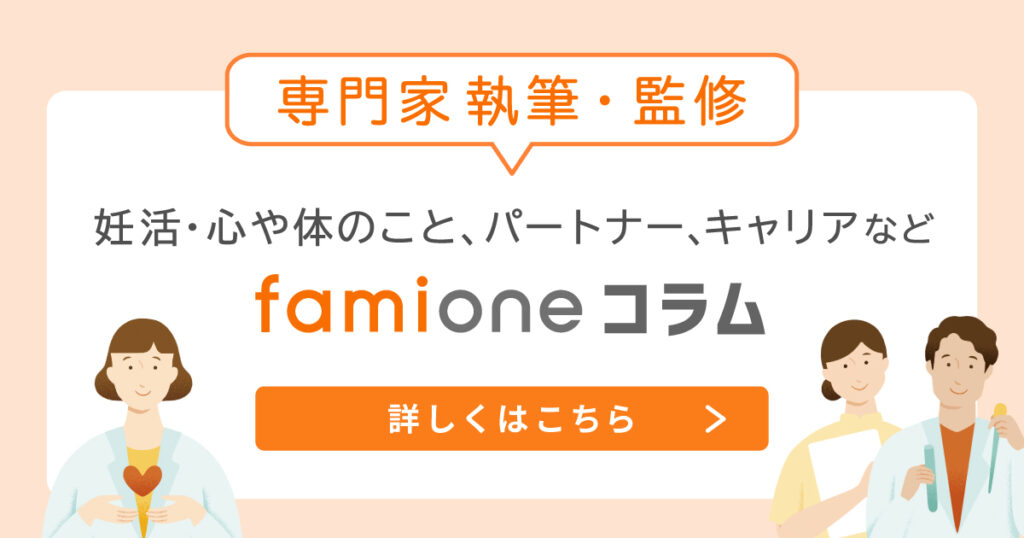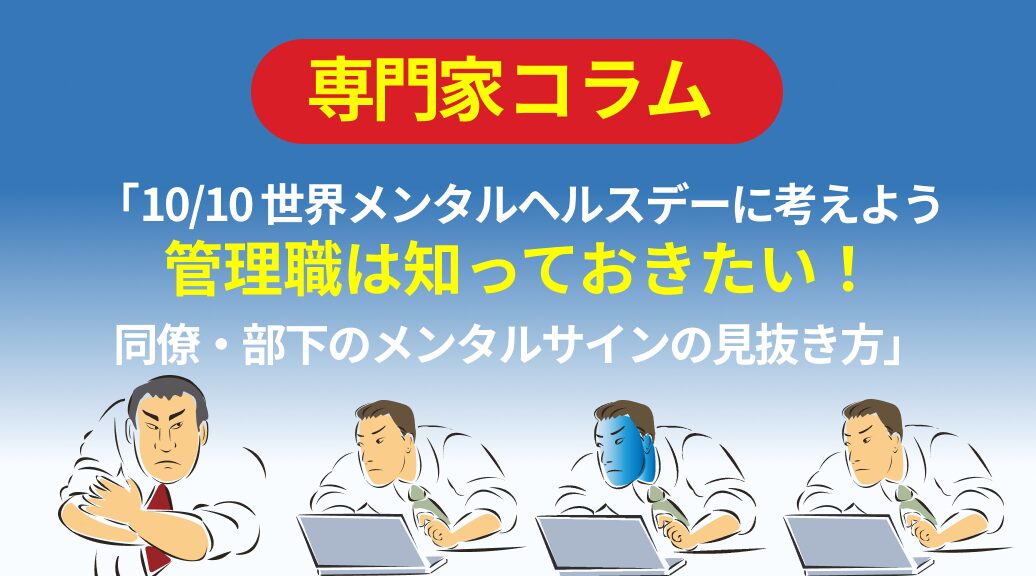
10月10日は世界メンタルヘルスデー
「メンタルヘルス」という言葉が使われ始めたのは、英語圏の国々では20世紀初頭から使われ始めましたが、日本では1980年代に一般的に使われ始めました。かつては、「精神衛生」「精神保健」という言葉が主に使われていました。カウンセリング制度やストレス対策が企業で始まったことで「メンタルヘルス」という言葉も普及していきました。「メンタルヘルス」は単に「精神疾患の有無」ではなく、自己実現・社会参加・ストレス対処能力などを含む広義の心の健康を意味します。
10月10日は「世界メンタルヘルスデー」です。これは、1992年に制定された国際記念日で、心の健康への理解と支援を広げることを目的としています。今回は近づく10月10日の世界メンタルヘルスデーの機会に、同僚や部下など周りの人のメンタルの動きを見るポイントについてお伝えしていきます。ぜひお役立ていただけると嬉しいです。
普段から周りの人のメンタルをよく観察する視点を持つ
まず大切なのは、よく観察する意識を持つことです。観察しなければ、以前とどう変わったのかはわかりません。メンタルの状態を確かめようとする視点を持つことが大切です。
心は目に見えないと言われますが、私はそうは思いません。実は人のメンタルの状況は目に見えています。心と体は密接な関係があるので、相手の状態を測るには、その人の服装やしぐさ、態度、行動などとよく観察すると見えてきます。朝、いつものように挨拶を交わすときに、「今日はいつもより元気が無いな。昨日夜更かししたのか?」とか、「声に張りがあって元気そうだな。仕事もプライベートもうまくいっているんだな」とか、思うことがあると思います。
毎日の様子を観察してみると些細なことから、相手の状態を測ることができるのです。普段から同僚や部下の様子を気にしておきましょう。知らない間にメンタルダウンしてしまい、休職することになったと知るようなことがあるとびっくりしてしまいまね。特に部下は自分のチームメンバーにあたりますので、管理していくことは上司の役割といえます。部下のメンタルについても気遣っておくことは仕事の一環と言えます。では、どこをどう見ていくと良いかについて考えていきましょう。
メンタル不調の代表的なサイン(部下・同僚に見られる兆候)
以下のような変化が見られたら、メンタル不調の可能性があります。
• 遅刻や欠勤が増える。元々は時間厳守だった人が急に遅れるようになる
• 集中力の低下・業務ミスの増加。以前はあまりなかった些細なミスが頻発するようになる
• 会話が減り、表情が暗くなる。発言や雑談が減り、笑顔が消える
• 業務への意欲が低下。新しい仕事への関心が薄れ、責任感が見られなくなる
• 身だしなみの乱れ。服装や髪型に気を使わなくなる
上記のような以前との違いに気づいたら、もしかしたら心がしんどくなってしまっているのかもしれないと考えてみましょう。理由は体の不調かもしれません。しかしたとえ体の不調だとしても、体のことは心にも影響を及ぼします。相手に何が起こっているのかを想像してみるところからメンタルヘルスの試みは始まります。
側にいる人としてできる声掛け
では次に、同僚や部下の異変に気づいたら、どうしたらいいのでしょうか? なんと声をかけたらいいのか難しいなと思われる方も多いかもしれません。「大丈夫だよ」と声かけると逆効果になってしまうこともあるかと思うと、相手の不調に気づいていても気安く声掛けが難しいなと感じても仕方がないことでしょう。ここではどう声掛けをしていくと良いか考えていきましょう。
①まずは、「話す機会」を作りましょう。自分が上司だとしたら定期的な1on1面談を持つのも一つの対策になるでしょう。同僚の場合はどうでしょうか。「最近どう?」などの軽い声掛けをしてみるところから始めてみるといいでしょう。相手の様子によっては、ランチや飲みに誘うこともできるかもしれません。
②話す機会を作れたら、まずは聴くことに徹しましょう。相手が話したいことを話せる空気を作るようにし、頷きやあいづちを多くして、しっかりと話したいことを話してもらいましょう。途中で話を奪わず、アドバイスは控えて、吐き出してもらうことが大切です。
③しっかり話を聴くことができたら、次に「共感」や「承認」します。例えば、「仕事は今そんな状況だったんだね。知らなかったよ。そんな大変な中、ずっと頑張ってたんだね」とか、「それは悩んでしまうね。しんどいんだね」など。相手の立場に立って、相手が感じている感情を代わりに口にしてみるようにしましょう。たとえ相手の感情と合っていなくても、相手は気にしてくれていることが嬉しく感じると思います。伝えてみることが大切です。
④専門家につなぐことも意識しましょう。社内のEAP(従業員支援プログラム)や相談窓口、病院などを進めてみることも必要であれば伝えていきましょう。
世界メンタルヘルスデーJAPAN2025のテーマ
2025年の世界メンタルヘルスデーのテーマは「サービスへのアクセス:災害や緊急事態におけるメンタルヘルス」です。非常時においても誰もが適切な心のケアを受けられる社会の実現を目指しています。「どんな状況でも、誰も取り残さない」メンタルヘルス支援の在り方を問い直すものになっています。
日本の今年のテーマは「つながる、どこでも、だれにでも」です。厚生労働省は「こころを支える輪を広げる」ことを目的に、自治体や企業と連携したイベントを展開しています。厚生労働省とNPO法人シルバーリボンジャパンが連携し、全国でライトアップイベントやワークショップを開催。東京タワーや京都タワーなどがシルバー&グリーンにライトアップされ、心の健康への関心を高める象徴的な取り組みが行われます。
管理職自身のセルフケアも忘れずに
部下のメンタルヘルスももちろん重要ですが、自分自身のメンタルケアも忘れないようにしていきましょう。上司である自分のメンタルを崩すと、チームにも多大な影響があるでしょう。10月10日の世界メンタルヘルスデーを機会に、自分自身の心が疲れすぎていないか、しんどく感じていることが解消されずに放置されていないか、立ち止まって考えてみると良いと思います。この機会に、職場の「こころの健康」について考え、行動を起こしてみませんか?