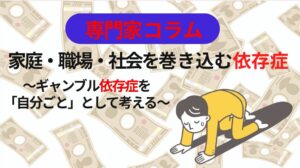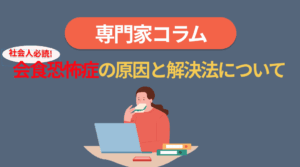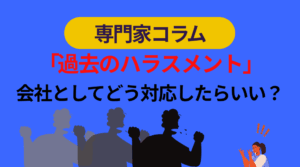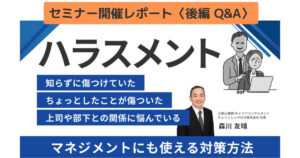ハラスメントの問題は日々あちこちで起きています。ちまたで話題になっている名前の付いたハラスメントを拾うとさらに多くのハラスメントで困っている現場があることがわかります。
例えば、リストラハラスメント、ジェンダーハラスメント、スモークハラスメント、アルコールハラスメントなどです。項目を見ていくと感じるのは、他人に迷惑をかけないことが大切だということではないでしょうか。
今までは「気遣い」や「思いやり」といった言葉でしかなかったことが、「ハラスメント」という名称でカテゴリー分けして叫ばれているように感じます。他人を思いやる気持ちはあったとしても、自分と相手は違っているので、どういうことが思いやりと言えるのかは難しいことだと思います。
「他人への思いやりを大事にしましょう」→「ハラスメントはやってはいけないこと」になっていったことは少し残念にも感じますが、何が良くないのかはわかりやすくなったと思います。
今回はペイシェントハラスメントについて、その定義、対策や法律がどのように考えられているかを見ていきましょう。
※ペイシェントハラスメント(ペイハラ)とは、医療機関で患者やその家族から医療従事者に対して行われる迷惑行為のことを指します。具体的には、暴力や暴言、セクハラや不当な要求などになります。
ペイシェントハラスメントはいわゆるカスタマーハラスメントに該当します。厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルでは、以下のように定義されています。
(出典元:厚生労働省 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!、令和4年2月25日)
ペイシェントハラスメントとは
患者や家族からのクレームや言動のうち、要求の内容の妥当性に照らして、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、医療従事者の就業環境を害するもの。
具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます:
・身体的な攻撃(暴行・傷害)
・精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言)
・威圧的な言動(土下座の要求など)
・執拗な要求(過剰な謝罪の要求、診療費の不払い要求)
・性的な言動(セクシャルハラスメント)
項目を見ていくとわかると思いますが、パワーハラスメントとセクシャルハラスメントと概ね同じ項目になっています。ハラスメントについてはたくさんのカテゴリーがあるように感じてしまいますが、大きくはパワーハラスメントとセクシャルハラスメントを抑えておけば迷うことは無くなるでしょう。ペイシャントハラスメント問題は医療現場の環境を悪化させるだけでなく、医療従事者の精神的負担を増大させるため、適切な対策が求められています。次に現場で起きている具体的な事例を見ていきましょう。
現場で起こっている具体的事例の紹介
ペイシェントハラスメント(ペイハラ)の具体的な事例として、以下のようなケースが報告されています:
待ち時間への過剰なクレーム:診察の順番が遅いことに腹を立て、大声で怒鳴る、受付スタッフに暴言を吐く。
診療内容への不満:医師の診断に納得せず、診療方針の変更を強要する、病院に居座る。
金銭的な要求:治療費の支払いを拒否し、病院側に補償を求める。
暴力行為:医療スタッフに物を投げつける、殴る・蹴るなどの身体的攻撃。
セクシャルハラスメント:看護師や医師に対して不適切な言動を繰り返す、身体を触る。
SNSでの誹謗中傷:病院の対応に不満を持ち、インターネット上で悪評を広める。
これらの行為は、医療従事者の精神的負担を増大させるだけでなく、業務の妨害にもつながります。ペイハラの防止には、病院側の毅然とした対応や、患者との適切なコミュニケーションが重要です。この後は防止策について見ていきましょう。
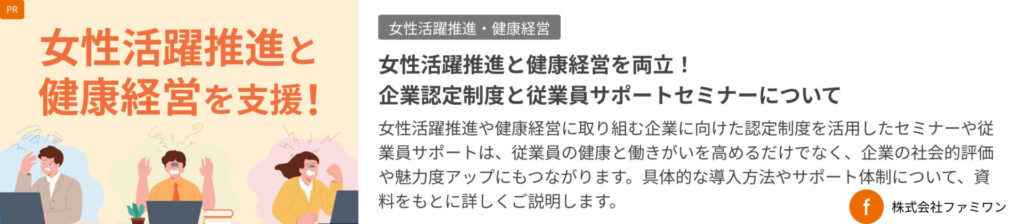
ペイシェントハラスメント防止策
- ペイシェントハラスメント(ペイハラ)を防ぐためには、医療機関が組織的な対応を強化し、職員が適切な対策を講じることが重要です。以下のような防止策が推奨されています。(※1)
(※1)厚生労働省「医療従事者に対する暴力・ハラスメントの防止に関する報告書」(2023年) 日本医師会「医療機関における患者等からのハラスメント(暴言・暴力等)への対応指針」
患者への周知
- 院内に「ハラスメント禁止」のポスターを掲示し、迷惑行為が許されないことを明示する。
- 公式サイトやパンフレットで、医療機関の対応方針を事前に案内する。
職員の対応強化
- 毅然とした態度を保ち、不当な要求には応じない。
- 複数名で対応し、職員が一人で対応しないようにする。
- 時間をおいて再対応することで、冷静な対応を促す。
証拠の確保
- 記録を残す(日時・内容・対応経緯をメモ)。
- 防犯カメラの設置で迷惑行為の証拠を確保する。
職員のメンタルケア
- 相談窓口の設置で、ペイハラを受けた職員が適切なサポートを受けられるようにする。
- 研修の実施で、職員が適切な対応方法を学ぶ。
法的対応の準備
- 警察や弁護士との連携を強化し、悪質なケースには法的措置を検討する。
- 業務妨害や暴行に対する法的対応を明確にする。
これらの対策を講じることで、医療現場の安全を守り、職員が安心して働ける環境を整えることができます。
ペイシェントハラスメント防止策として、コミュニケーション力を上げていく
患者やその家族の行き過ぎた要求は見てきた通りペイシャントハラスメントに該当しますが、そもそものコミュニケーション力を上げていく努力も必要でしょう。患者を怒らせてしまうとか、過度に不安がらせてしまうことがなければ、多くのハラスメントを減らせることに繋がっていくと思います。最後に医療従事者のコミュニケーション力向上について考えていきましょう。
医療従事者のコミュニケーション力を向上させるには、患者との信頼関係を築き、チーム医療を円滑に進めるためのスキルを磨くことが重要です。以下のような方法が推奨されています。(※2)
(※2)厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル(令和5年3月)」
コミュニケーション力向上のポイント
1.アクティブリスニング(傾聴)を実践する
- 患者の話を遮らず、適切な相槌を打つ。
- 「それは大変でしたね」「お困りですね」と共感を示す。
- 要点を繰り返して確認し、誤解を防ぐ。
2.分かりやすい説明を心がける
- 専門用語を避け、日常的な言葉で説明する。
- 図やイラストを活用し、視覚的に理解しやすくする。
- 短く簡潔に伝え、患者が理解しやすいようにする。
3.非言語コミュニケーションを意識する
- 穏やかな表情と落ち着いた声のトーンを保つ。
- アイコンタクトを取り、患者に安心感を与える。
- 身振りや姿勢で親しみやすさを表現する。
4.チーム医療の円滑化
- スタッフ間で情報共有を徹底し、誤解を防ぐ。
- 定期的なミーティングを行い、連携を強化する。
- 相手の意見を尊重し、協力的な姿勢を持つ。
5.研修やトレーニングを活用する
- コミュニケーションスキル向上の研修に参加する。
- ロールプレイを通じて実践的なスキルを磨く。
- フィードバックを受け、改善点を見つける。
これらの方法を取り入れることで、患者との信頼関係を深め、医療現場での円滑なコミュニケーションが可能になります。ペイシェントハラスメントを「させない」ために出来ることはしっかりと学び能力を向上させていきましょう。
無料 オンライン健康相談&セミナー「福利厚生サービス」ダウンロード
企業の福利厚生施策として、従業員のライフステージに寄り添うサポートサービスです。
直近3年間で400回以上のセミナー実績や、利用促進につながる広報制作、全員が資格を有する専門家の相談対応をご提供しています。さらに、女性活躍推進や「くるみん」などの企業認定制度に対応した基準・条件にも沿った施策をご提案します。

1. 豊富な実績で安心
直近3年間で400回以上のセミナー開催実績。
実例に基づく具体的なノウハウをご提供します。
2. 利用促進の仕組みもサポート
広報制作サンプルを活用し、従業員が参加・利用しやすい仕組みを構築できます。
3. 専門家が直接伴走
全員が資格を有する専門家による相談対応。
女性活躍推進や「くるみん」などの認定制度にも準拠した施策をご提案します。