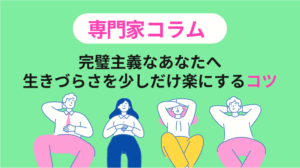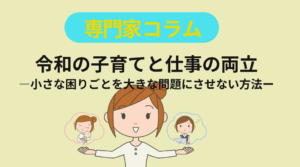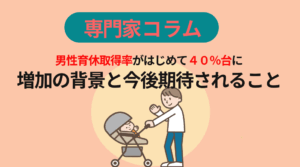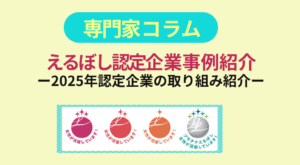はじめに
昭和生まれ昭和育ちの私にとって、「週休3日制」という言葉は馴染みもない上に耳に入っても実感が伴ってこないですが、最近ちょいちょい耳にするようになってきました。
私が子どもの頃は週休1日制が主流でした。言わずもがな、「週休3日制」というのは、1週間の内3日間を休日とする働き方のことです。最近では、週休3日制を導入していく企業が大企業中心に増えてきています。日本では現在は義務化されてはいないので、企業が自主的に導入する形になっています。
厚生労働省の調べによると、日本の企業で週休3日制を導入している企業は、現在7.5%です。まだまだ導入している企業は少ないですが、AIやロボットの台頭や、健康経営を目指す企業が増えて働き方改革がさらに進んでいく中で、週休3日制を導入する企業は増えていくことでしょう。
日本での実例を紹介
既にいくつかの企業が週休3日制を導入しています。以下のような企業が代表的な事例です (2025年4月23日時点):
- ヤフー株式会社:「えらべる勤務制度」を導入し、社員が柔軟に働き方を選択できるようにしています。
- 日本マイクロソフト株式会社:「ワークライフチョイス」を実施し、週休3日制の試験的導入を行いました。
- 株式会社電通:「インプットホリデー」として、社員が学びや自己研鑽のために休暇を活用できる制度を設けています。
- 佐川急便株式会社:1日の労働時間を8時間から10時間に変更し、週休3日制を実現。
- 株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ):変形労働時間制を採用し、週休3日を選択できる仕組みを導入
週休3日制の種類
上記の大企業の取り組みのように主に3つのパターンがあり、企業によって運用方法は違います。どれを選択するといいのかは従業員と話し合って決めていくのもいいかもしれません。従業員が自ら決めていくのであれば、制度に対する納得感も高くなることでしょう。
①給与維持型 労働時間を短縮しつつ、給与を維持する方法
②労働時間維持型 1日の労働時間を増やし、週の総労働時間を維持する方法
③給与減額型 休日を増やす代わりに、給与を減額する方法
次に週休3日制にするメリットとデメリットを見ていきましょう。
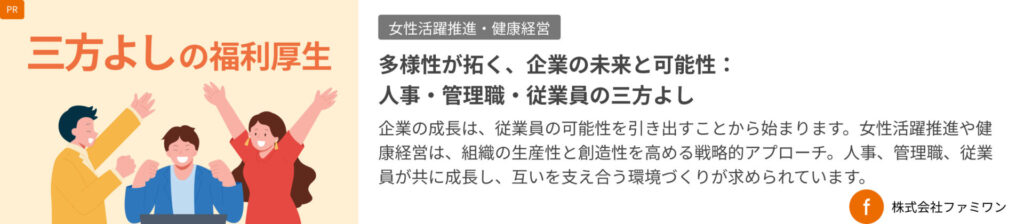
週休3日制のメリットとデメリット
現時点では、週休3日制の義務化は予定されていませんが、政府は企業に対して導入を促す動きを見せています。選択的な制度としての普及を目指している段階です。
ここでは、「週休3日制」のメリットとデメリットを見ていきましょう。
≪メリット≫
・ワークライフバランスの向上
・ストレス軽減とリフレッシュ効果
・離職率の低下と人材確保
・生産性が向上する可能性
メリットを見ていくと興味深いのは、労働時間が減っても生産性が向上する可能性があるというところでしょう。業務改善として仕組みを変更し、AIや機械に実行してもらうことを増やしていく機会になることも予想されます。また従業員が余暇をしっかり取ることで元気になり、モチベーションアップに繋がり生産性が向上することも予想できます。
次に、デメリットも見ていきましょう。
≪デメリット≫
・給与減少のリスクがある(給与減額型の場合)
・1日の労働負担が増加する(労働時間維持型の場合)
・業務の進捗やビジネスチャンスへの影響
海外での取り組み
海外ではヨーロッパ諸国を中心に週休3日制の試験導入が進んでいます。既にアイスランドでは労働時間を短縮しながら、生産性を維持する試みに成功しています。
≪各国の取り組み≫
- アイスランド:2015年から2019年にかけて政府主導の大規模実験を実施。給与を維持したまま労働時間を短縮し、生産性の維持と従業員の幸福度向上が確認されました。
- ベルギー:ヨーロッパで初めて週4日勤務を法制化。給与を減額せずに週4日勤務を選択できる権利を認めました。
- ポルトガル:「100:80:100モデル」を導入。100%の生産性を維持することを条件に、80%の時間で100%の給与を支払う試みを実施。
- アメリカ:週休3日制の法案が審議されており、所定労働時間を40時間から32時間に減らし、超過分に追加の残業代を支払う制度を検討中。
- 日本:政府が選択的週休3日制の導入促進を掲げており、一部の企業や自治体で試験的な導入が進んでいます。
おわりに
ここまで「週休3日制」についてどのような動きが起こっているか見てきました。
皆さんはどう感じたでしょうか?中小企業にはまだまだ考えられないなと思われるかもしれません。少し先の話になってくるとは思いますが、世界を見ると、すでに動いている国も多くあることに気づくでしょう。日本がいつものように世界に後れを取ることも国としての問題となってくることも容易に考えられます。少し先の未来を見据えた健康経営、組織改革、人材育成を考えていく必要があるでしょう。